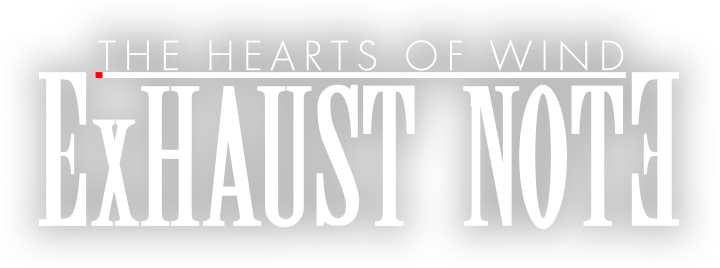novels
白亜の檻
第1章 邂逅(かいこう)
1.
今日も白い朝がやってきた。
バイク雑誌やらパソコン雑誌が床に落ちている以外はそれなりに小奇麗な、フローリングの部屋にカーテン越しの朝陽が差し込んでいた。
いつからか無粋な電子音が静寂(しじま)を破ると、薄いブルーのベッドの上で引っかぶっていた毛布の中から手だけがふらふらと所在なげに「それ」を探し始める。
先ほどから五月蝿(うるさ)いほどの騒音を撒き散らしている「それ」を見つけた手は、スヌーズなんて効かせることなく真っ先に目覚ましをオフにした。
「勘弁してよ、チャットで昨日遅かったんだから……」
薄いブルーの毛布に包まった物体は名残惜しそうにモゾモゾと動いて、引っつかんだままの「それ」……目覚し時計をちらりと見やる。
「! うお! やべぇっ!」
その瞬間素っ頓狂な声をあげた物体はバネか何かで弾かれるように、やはり薄いブルーのシーツのかかったベッドの上に仁王立ちになった。
時計の針は8時を指している。
それなりに整った顔立ちは、現在しかしながら少しばかり苦悶に彩られている。
ズル休みを思案しているのか10秒ほど固まっていた男は、それでもバタバタと慌ただしく洗面に駆け込む。寝癖直しを頭に振りまいて多少爆発気味の茶色い叢(くさむら)のような髪を櫛で整え、30秒程度で歯磨きを終わらせてライダースジャケットに身を包むまで起床からきっかり5分。
ヘルメットを引っつかむと、風のように誰もいない部屋を後にした。
鳴川郁人(なるかわいくと)が一人暮らしをはじめてかれこれ2年になる。
文系の普通科大学に入った彼は、しかし以前からの趣味を仕事に活かすべくシステムエンジニアを目指して情報処理技術者資格を取得し、3年前に晴れて近くのソフトウェアベンダーへプログラマとして就職を果たした。
家は近かったのだが、パソコンを触るのはどうしても夜中になるため家人に気を遣ったのもある。早く家を出たかったというのもあった。
そんな訳でこの閑静な住宅街にある小さな1DKを借りたのが2年前。
最近自炊には慣れてきたものの、やっぱり朝が弱くてたまに朝バタバタしている。
郁人が単車の免許を取っていて良かったと思うのはこんなときだ。何せ この近辺の朝の通勤渋滞といったら国道に出るまで30分なんてざらで、とてもじゃないが車で通勤する気にはなれない。かといって、郁人の会社と言うのが郊外にぽつねんとあるものだから電車とバスでは不便極まりない。
郁人はよほどの悪天候でない限りは愛車のドゥカティ・モンスター900を走らせて通勤するのであった。
駐輪場からモンスターを引っ張り出した郁人はそのまま少しばかり開けたところまで単車を押してエンジンをかける。車体のチェックやタイヤの空気圧を見ている間に軽く暖気を続け、風の様に支度を整えた郁人は、愛車にうち跨ってギアをローに入れた。
澄んだ空気に満ちた初夏の朝、湿気のないキリリとした空気をテルミニョーニマフラーの重低音が震わせる。
うねるようなデスモエンジンの排気音を逆巻いて、郁人のドゥカティは黄色い矢のようにアスファルトの路上を滑り始めた。
渋滞で居並ぶ車の横を注意深く通り抜け、国道に出たモンスターは街の外へと猛然とダッシュする。
郁人の会社は鬱蒼とした森を抜けた郊外にあった。
ちょっとしたワインディングになっているから郁人はこの道を通るのが好きだった。
とりわけ今日は時間がないのでかなりのハイペースで、車と言う車を片っ端からパスしていく。
高らかなエキゾーストノートが森全体に轟くように咆哮した。
足回りに一通り手の入った郁人のモンスターは、ミズスマシのようにワインディングロードを駆け抜ける。空冷904ccのLツインエンジンはキャブレター仕様で馬力こそたいした事はなかったが、そんな瑣末なことは単車の魅力とあまり関係がないことをモンスターは郁人に教えてくれる。アクセルを開けるということがこれほど気持ちのいいものだと郁人はモンスターに乗って初めて知った。
確かにキャブレターをレーシングキャブレターに換えればパワーは出るだろうが、この楽しさはなくなってしまうよと行きつけのオートバイ店の主人に言われて、キャブレターの交換は見送った。
以来、郁人は暇を見つけてはツーリングに出かけていた。
今はとにかく走ることが愉しかった。
おかげで今年26になるというのに彼女一つ作らないで、全国を走り回っている。
そんな郁人が一人暮らしをはじめると聞いた友人・親戚一同が俄かに色めきたったものだが、経過は今までどおり。
口の悪い友人は「奴は単車と結婚してるから」と言い切る始末であったが、本人も暢気(のんき)なもので、全く意に介した様子はない。
友人も殆どがバイク仲間かパソコン関係の友人ばかり。尤も会社の単車仲間は、ほぼ例外なく郁人にその道に引きずり込まれた人ばかりで、休日ともなれば誰となく集まっては走りに行っている。
郁人はそんな生活に満足していたし、チャットやBBSで妻帯者の友人の嘆き節を聞くにつけ一人身の気楽さをありがたがっていたくらいだから、身を固めようなどとこれっぽっちも考えないのは無理からぬことと言えた。
郁人が会社の門をくぐったのは始業5分前。
いつもの場所にモンスターをパークさせると全速力で社屋に駆け込みタイムカードを押す。時刻は8時29分。
ジジッと小さな音を立ててカードに数字が印字された直後にカタッという小さな音を立てて時計の針が30分を指した。
「……新記録達成」
ふーっと息をついて郁人はぼそりと誰に聞かせるでもなく呟いた。勝利をかみ締める一瞬である。
そんな時、
「おはよう、鳴川クン」
冷たく澄んだ声が郁人の背後から掛かった。たらり、と郁人の頬を伝う一筋の汗。
ゆっくり振り向いた郁人は
「おはようございます」
とやや引きつり気味の声で応じた。
同じ開発課の課長、高階玲子(たかしなれいこ)である。玲子はやや神経質そうに細身の眼鏡を持ち上げた。女性としては長身痩躯の玲子の身長は郁人とそう変わらない。髪は長いが後ろできつくまとめられ、美人ではあったがどこか人を寄せ付けない空気をまとっていた。
郁人はげんなりした。このやり手のキャリアウーマンはいちいち郁人に突っ込んでくださる。
こんな2枚目半のチビを虐めて何が愉しいのか分からないが、郁人にとっては天敵みたいなものだ。
歳は郁人の一つか二つ上だけだった筈だが、そのやや切れ長の目で眼鏡の奥からじっと見つめられると郁人の背中は妙な汗でじっとりと濡れるのであった。
「今日も暴走?」
郁人の身なりをさらりと見て玲子が頬ひとつ歪めずに訊いた。
「いえ。安全運転には留意しております」
対する郁人も最近はこのクールビューティーに対する態度をわきまえている。こんな時にヘラヘラしようものならきっちりお灸を据えられるという事は入社1年目で骨身にしみている。
至極真面目な返答を玲子に返す。
「そう願いたいわね。これ以上人手不足になったらたまらないもの」
そう言った玲子は軽く息をついた。
それから少しばかり郁人を見つめて、
「三木クンが今朝出勤途中にバイクで事故に遭ったらしいわよ」
突然の爆弾発言に郁人の思考が一時的に停止する。
「なんですって?」
「聞こえなかったの? 事故に遭ったのよ」
三木敬一郎(みきけいいちろう)は郁人の1年後輩に当たる。同じ開発課で真っ先に単車の世界に引きずり込んだ、いわば一番弟子のようなものだ。
ちょっとばかりそそっかしい所があるので郁人としてもやや心配なところはあったのだが、まさか事故に遭うとは。
三木に単車を勧めた自分を呪いながら「容態は? 無事なんですか?」と訊いた。
玲子はちょっと肩をすくめて
「まだ分からないわ。お母様から先刻連絡を受けたばかりだもの。搬送先は美杉病院だということしか……」
美杉病院といえば通勤途中の森の奥に建っている救急総合病院で、なかなかの技倆(うで)との評判だ。
「とにかく私はこれから美杉病院に行って来るから、何かあったら携帯に連絡くれるか病院で呼び出してもらって」
そう言って踵を返そうとする玲子に郁人は「待ってください」と声を掛けた。
「僕も行きます。同じ単車乗りで、彼に単車を勧めたのは僕です。何か役に立てることやわかることがあるかもしれません」
玲子は首を振った。
「これ以上人員を割く訳には行かないわ。例の解析プログラムの納期、今日まででしょ。心配なのは分かるけど、今はあなたの責務を果たしなさい。」
そして郁人に向き直った玲子は郁人の肩に手を置いて
「それが終われば今日は特別に休憩時間を3時間あげます。行ってあげなさい」
ふと玲子の目元にやさしい微笑を見たような気がしたが、次の瞬間風のように玲子は社の玄関口へと消えた。
郁人は複雑な視線を玲子の消えた玄関口へと投げていたが、やがて小さな溜息をついて自らに言い聞かせるように「大丈夫」と呟いた。
――――
三木のことが気になって今ひとつモチベーションの上がらなかった郁人だが、何とか午前中に作業が終わりデバッグ作業に移っていた。
開発課のドアが開いたのは、郁人がそろそろ昼食を摂ろうかと伸びをしたところだった。
社に戻ってきた玲子はいつもの貌(かお)で郁人の席へと歩み寄る。郁人もそれに気づいて立ち上がった。
「安心なさい。重傷だけれど命に別状はないわ」
玲子の「重傷だけれど」というセンテンスに少しばかり苦いものを感じたが、とりあえずは「そうですか」と胸をなでおろす。
「意識もしっかりしてるし、例の仕事が済み次第行ってあげなさい」
いつもの、少しばかり情の薄い口調でそれだけ言って自席へ戻ろうとする玲子に「三木の怪我の具合はどうでしたか?」と訊いた。
怪我によっては見舞いに行くタイミングを考えたほうがいいこともある事を郁人は知っていた。玲子は振り向くと少しだけ微笑んだ。
「大丈夫よ。鎖骨と腿(あし)を折ったけど、治ればまた単車に乗れるらしいから」
そう言ってからちょっとだけ表情を曇らせて「出来ればもう乗っては欲しくないけどね」と続けた。
まぁ、単車に興味がない人の意見というのは概ねそんなところだろう。単車を勧めた郁人もまるで無関係という訳にもいくまい。
玲子の最後の言葉にそんな居心地の悪さを感じた郁人は、
「じゃ、ちょっと見てきます」
とだけ言い残してオフィスを後にした。
社を出る前に購買で熨斗袋と社員食堂でパンとコーヒーのパックを買った郁人はウエストバッグにすべてを押し込んで駐輪場へと向かった。
ここから美杉病院は単車で15分ほどの距離にある。その間に店らしいものはないから今回は手ぶらで行くことになるが、事態が事態だけに致し方あるまい。
郁人はドゥカティに跨るとエンジンをスタートさせ、ゆっくりと走り出した。
雲ひとつない青空に初夏の太陽は高く輝き、森から吹く風はわずかに湿り気を含んでいた。
木々の萌えるにおいがヘルメット越しにも鼻腔に届いた。行き交う車もまばらな森の路を、空冷Lツインが詠う。
仕事をするのも馬鹿馬鹿しくなるようないい天気の日和に、自然を体いっぱいに感じながら単車を走らせると自然と頬がほころぶ。
これから病院に見舞いに行くってのに、不謹慎だよなぁ……と思い直しては軽く頭(かぶり)を振って緩んだ顔を引き締める。
程なく緑に滲む彼方から白い影が郁人の視界に飛び込んできた。緑の世界に唯一の虚空の色彩がぽかりとそこに鎮座して、狂おしいほどの命の光の中で限りなく重くのしかかっていた。
2.
郁人は純白の建物をゆっくり見ながら入り口を探した。
静かだった。
テルミニョーニマフラーの吐き出す勇ましいエキゾーストノートと乾式クラッチのカラカラと言う打音が周囲を威圧するように響き渡る。
駐輪場と思(おぼ)しきスペースを発見した郁人はそろりとモンスターをパークさせてキーをオフにした。
刹那訪れる静寂。
どこかで小鳥の囀(さえず)る声が聞こえる以外は、木々の葉擦れの音しかしない。
病院はかなり大きい。個人の名を冠しているが、その規模は大学病院にも匹敵するだろう。
ざっと見渡すだけでも3つの病棟が見える。奥にもまだスペースがありそうだった。
それぞれの病棟は渡り廊下でつながれており、そのすべての壁は白く塗りこめられている。
平日の昼ということもあってか駐車場、駐輪場とも車は少なく、人気(ひとけ)もまばらであった。
郁人はヘルメットを取って小脇に抱えると、玄関へと足を進めた。
玄関の自動ドアが開くと病院特有の消毒液の匂いが郁人を出迎えた。正直この匂いは好きではない。何度かお世話にはなったところだが、慣れることはなかった。
郁人は総合案内のプレートの前で入院病棟を探す。
総合受付から最も遠いD棟と呼ばれる病棟が外科の入院病棟のようだ。
郁人はD棟の受付に向かった。渡り廊下を越えて棟内に入ると入院病棟独特のむっとする匂いが消毒液の匂いに混ざり込んで胸が悪くなりそうだった。
院内も白を基調にまとめられており、清潔感が溢れてはいるが郁人は基本的にこの雰囲気が好きにはなれない。
まぁ、病院がダイスキという人は少数派だとは思うが。
受付で敬一郎の病室を訊いた郁人は金封の用意をして部屋に向かった。
敬一郎が運び込まれた病室は4階の6人部屋であった。
開け放たれた扉を軽くノックしてベッドを探すと「鳴川さん?」と声を掛けられた。
振り返ると一番手前のベッドで敬一郎がひらひらと左手を挙げていた。
郁人は破顔して
「心配させやがって、この馬鹿弟子が!」
熨斗袋でぺしぺしと敬一郎の頭を叩く。
「イタ! 痛いっス! 怪我人に横暴っス!」
「これのドコが怪我人なんだよ?」
そう言って郁人は敬一郎を眺め回す。
右足はギブスで固められた上に吊り下げられ、右腕も固定されている。
半端な格好で単車に乗るなと口を酸っぱくして言い続けたおかげか、それ以外に目立った外傷はない。
「立派な怪我人じゃないっスか」
おどけたように言う敬一郎の枕もとまで椅子を引き寄せて座り込んだ郁人は、
「それだけ軽口が叩けりゃ十分だろ」
と笑った。
熨斗袋を敬一郎に渡した郁人は「で?」と言葉を継いだ。
「何がどうなった?」
敬一郎が言うにはこうだ。
朝、いつもの時間に愛車のXJR1300で河原沿いの市道を走っていたら、交差点で対向右折車と接触したということだ。事故現場は緩くカーブしており見通しが悪い上、直前を大型車が走っていたので見落とされた様だ。
横から追突された敬一郎は右折車のボンネットの上に放り出されて腓骨と鎖骨を骨折。膝の靭帯を断裂してしまったので手術が必要ということだった。
相手は普通のおばさんらしく、話がこじれることもなさそうでやれやれといったところらしい。「ということで全治3ヶ月っス。俺が休みの間がんばって働いてくださいっス」
にこやかに言う敬一郎に郁人は
「それが迷惑だっつーの!」
とデコピンをしながら苦笑する。
「おまえの仕事の内容書き出しておけよ。スケジュールも忘れるな」
「はいっス」
返事だけは良い敬一郎であった。
「それとあと何か必要なものはあるか? 本ぐらいなら用意してやるぞ?」
「あ、それじゃ美人で巨乳の看護婦を……」
「……元気そうだな。明日出社するか?」
「いえいえ、滅相もございませんっス。ゴホゴホ……」
郁人は大きく溜息をついた。人間の軽さでは郁人も人後に落ちないつもりだが、この男には到底敵いそうにない。
本気で心配した自分がバカのようで頭を抱えていると、
「鳴川さん、ひとつお願いしてもいいっスか?」
敬一郎がややあって訊いた。
「……なんだ?」
敬一郎はベッド横の台上から小さな紙片を取って郁人に渡した。
「そこに俺のXJRがレッカーされてるっス。どんな様子か……直りそうなのか、どれくらい掛かりそうなのか見てきてもらえないっスか?」
人間は無事だった。次に愛車を心配するのは単車乗りとして当然だろう。
「分かった」
郁人はうなずいた。同じ単車乗り、その心中察せぬはずはなかった。
「……そうっス!」
敬一郎が素っ頓狂な声をあげた。
「まだお茶も出してなかったっスね。缶コーヒーでよければ確かそこの冷蔵庫に……」
そう言われてみれば郁人は昼も食べていない。
「いや、いいよ。昼飯にパンとコーヒーを買ってきてたの、忘れてた」
ウェストバッグの中で若干つぶれたパンと缶コーヒーを取り出してみせる。
「俺のはないんっスか?」
「……阿呆」
敬一郎と郁人の掛け合いは終始和やかであった。
「さて」
昼を食べた後、ひとしきり話し込んだ郁人はそう言って立ち上がった。
時計を見てみるといつしか2時を回っている。こんなときの時間はあっという間である。
「姐(あね)さんに『休憩は3時間』と釘を刺されてるんでそろそろ社に戻るよ。今日中に単車を見て明日の終業後にでもまた来る」
「ご迷惑をおかけしますっス」
頭を軽く下げた敬一郎に軽く左手を挙げて郁人は部屋を出た。
郁人が駐輪場まで戻ってモンスターのエンジンをスタートさせると、不意に郁人は誰かに見られているような、妙な気配を感じて周囲を見回した。
「……気のせい……か?」
そう一人ごちて、なお釈然としない思いを眉間に刻みながらヘルメットを被る。
ひとつアクセルをブリッピングしてエキゾーストノートが周囲の空気を震わせると次の瞬間、昼下がりの森の中へと黄色いドゥカティは吸い込まれていくのだった。
その日、郁人はいつもより早めに仕事を切り上げた。
敬一郎に渡されたメモに書かれた場所はそう遠くはないが、日が落ちて暗くなってしまうと単車の状態を見誤る可能性がある。
日はずいぶん長くなってきたとはいえ、時間はあるに越したことはなかった。
「あら、もう上がり?」
手早く帰り支度をする郁人に天敵の声が掛かった。郁人は内心激しい舌打ちをした。
玲子はというと厭味を言う、というよりは事実の確認程度に考えているようで涼しげな瞳で郁人を見ていた。
郁人はその胸中などおくびにも出さず、営業用スマイルで「はい」と答える。
「三木の奴に単車の処理を任されまして……」
と、あることないこと吹聴する。まぁ、単車のことを頼まれたのは事実であるので、全くの嘘八百と言う訳ではない。
「そう」
あまり関心のないような声で玲子がうなずく。
「仕事もそれくらい熱が入ってくれると助かるんだけど」
「は。一層努力いたします」
「お願いするわ。……気をつけて帰りなさい」
身を翻した玲子は足早に立ち去った。いつもならもう少し絡んでくるのだが、流石に今日はそういう気分ではないらしい。
郁人にとってはありがたいことだった。
メモ書きされた場所は単車屋というよりは解体工場といったほうが正しそうだった。
郁人の会社から単車で20分ほどのその場所は、郁人の既知圏外であった。
モンスターを降りた郁人は紅に染まる工場の敷地内を見回した。あたりに人影はなく、熾(おこ)り火のような太陽が山のように積み上げられたスクラップを紅く照り付けていた。
時の流れが歪んだような、妙な眩暈(めまい)を感じる。
郁人はふるふると頭を軽く振って、敬一郎のXJRを探し始めた。
何分と経たないうちにXJRが見つかった。
一瞬それと判らぬほどに、破壊された「物体」。
横から追突された衝撃でフレームが飴のように曲がり、エンジンのクランクケースは陥没して、無気味に走った亀裂から黒いにじみが見えた。マフラーは既になく、スイングアームもフロントフォークも見事にひしげている。
ホイールもスポーク部分から折れており、正常に回転するとは思えなかった。
しばらく言葉を失っていた郁人だが、
「……よくこれで生きてたよな」
と誰へとなく一人ごちた。
生死の紙一重の境目を見た気がしたのだ。
郁人は軽くXJRを見回した。被害状況を確認するというよりは、使えるパーツがあるか探したほうが早そうだ。
「……キャブレターくらい、かな?」
郁人はお手上げといった風に苦笑する。
それはXJRにとっては死の宣告に等しかった。これを修理するとすれば 新車価格以上の修理費用とクラッシュのダメージを持病として抱えることを覚悟しなくてはならない、ということだ。
現行の量産車である以上、修理するメリットなどどこにもないのだった。
残念だがこのXJRは廃車にする以外になさそうだ。
郁人はちょっと寂しそうに微笑んで、XJRの無残に変形したタンクを撫でた。
「お疲れさん」
そう小さく呟いて、郁人は工場をあとにした。
翌日の終業後、郁人はやはりモンスターで美杉病院を訪れた。
やはりちょっと早めに切り上げた郁人は、西日に染まる真白い巨塔を横目に見ながら直接入院病棟に入っていった。
出勤途中のコンビニで買ったバイク雑誌などを見舞いに、郁人は敬一郎の部屋に入る。
敬一郎はぼんやりと天井を見つめていた。
「よ」
郁人は軽く手を挙げて敬一郎を呼んだ。
「鳴川さん」
ぱぁっと表情を輝かせて敬一郎が返事した。
「待ってたっスよう。寂しかったっスよぅ。早く鳴川さんの手で俺を暖めてくださいっス」
「気持ち悪いコトゆーな」
郁人は持っていた雑誌でべしべしと敬一郎の頭を叩く。
「イタ! 痛いっス! 怪我人に横暴っス!」
「お前、怪我よりアタマ診てもらえ」
「ナニゲに酷いコト言われてる気がするっス」
二人は笑ったが、単車の話になると流石の敬一郎も沈んだ。
「そっスか。全損っスか」
どこか力のない敬一郎の肩をぽんぽんと叩いた郁人は
「ま、過ぎたことを悔いても仕方がないさ。それより保険はそれなりに下りるんだろ? ニューマシーンを何にするか考えてた方がよっぽど建設的というもんだ」
しんみりしないよう努めて明るく言ったが、敬一郎は笑って答えた。
「それっス。今度はレプリカにして鳴川さんを追っかけまわすってのはどうっスか? 個人的にはファイヤーブレードとかR1なんてイケてると思うんスけど」
「それはやめておけ。お前だと死にかねん」
敬一郎は既に立ち直っていたようで悪びれもせずに言ったが、郁人は真顔で突っ込んだ。
この男は周囲にどれだけ心配かけたかなんてこれっぽっちも考えていないのだろう。
「それじゃアプリリアのミレRとか?」
「却下」
む~ん、と唸る敬一郎はポンとベッドを叩いた。
「レプリカがダメならアプリリアのトゥオーノとかMVアグスタのブルターレとか……」
「それは別の意味で何か癪にさわるからダメ」
「そりゃないっスよ~」
勿論本気というわけではなく、終始和やかに笑いさざめきながら二人はああでもないこうでもないと、敬一郎の体が治った後の事を話していた。
ふと、郁人が窓から覗く茜色の空に気づいて立ち上がる。
開け放たれた窓の向こうに続く森の緑と稜線の彼方に沈み行く洛陽が、世界を赫(あか)く染めていた。
「じゃ、そろそろ俺は帰るよ。また気が向いたら見舞いにくる」
「お願いするっス。俺、構ってもらえないと寂しくて死んじまうっス」
郁人はしかたないなぁと言う苦笑を頬に刻んで言った。
「分かった分かった。近いうちに、な」
郁人は軽く手を挙げて病室を出た。
入院病棟を出た郁人は駐輪場へと急いだ。
この森周辺は街燈が殆どないので、日が落ちてしまうと真っ暗になるのだ。とりあえず明るいうちに森を出たかった。
日は長くなりつつあったが、さすがに時間が遅い。
地に落ちる影は長く、次第に弱々しくなっていく。
そんな時間の駐輪場は既に閑散としていたが、郁人の見慣れた黄色いドゥカティのそばに人影があった。
郁人は少しばかりの不安を覚えて歩調を速める。
施錠はしっかりしてあるものの、自分のいないところで愛車の近くに人影があるといい気分はしない。それが好感を持って見られているとしてもだ。
人影は郁人に気づくとさっと車体の後ろに隠れた。いよいよもって挙動が怪しい。
いつしか郁人は軽い駆け足になっていた。
「あの、なにか……」
ドゥカティのそばまで走り寄って人影に問い掛けた。
人影は吃驚(びっくり)したように
「ひ……ひゃい!」
と奇妙な声をあげて飛び上がった。
それは小さな、幼いと言ってもいいくらいの女の子だった。
3
郁人はぽかんと少女を見つめていた。
年恰好は中学生くらいだろうか。
腰まで伸びたさらさらの長い髪が風に踊るように揺れていた。整った目鼻立ちもさることながら一際この少女を印象付けたのはその抜けるような、真白い新雪のごとき肌であった。
パウダースノーを思わせるきめ細かな肌は、何者にも触れられたことのないかのような静謐な輝きを放っている。
緩やかに着た大き目のTシャツに膝上丈のスパッツというくだけた服装から見て、家族のお見舞いにきているようだった。
単車泥棒と間違えたことを少しだけ後悔しながら、郁人は
「あ、いや、な、何かあったのかな?」
と慌てて語調を緩めて言い直した。
少女は慌てた様子で
「あ、その、いや、あわわ……」
と要領を得ない返事をした。
少女は人という字を手の平に書くと幾つも飲み込んで、自分を落ち着かせようとしているようだった。
それから深呼吸をして、郁人の問いに少女が答える準備が整うまでたっぷり5分を要した。
郁人はその様子を一部始終見ながら、また妙なのに掴まっちゃったなぁと内心苦笑した。薄闇は迫りつつあったが、この状況で少女を蔑ろにできるほど郁人は人間ができてはいない。
「えーっと、あ、あの! このバイク、す…すす、すっごく可愛いですね」
非常に当り障りのない、見事なまでに気の利かない誉め言葉だったが、郁人は「ありがと」といって微笑んだ。
「で、でもでも! すっごい音がするんですよね!? どぅーんって……」
少女は郁人の返事に気をよくしたのか、少しばかり饒舌になって続けた。
対する郁人はというとちょっとばかり居心地が悪そうに苦笑した。
「そりゃそうだよね。これだけ静かな場所だからよく聞こえるよね……」
確かにモンスターのテルミニョーニマフラーから奏でられるエキゾーストノートは、オートバイやクルマに興味のある人にこそ天上の音楽にも喩えられようが、興味のない人にとってはただの騒音でしかない。
少なくともこの音を聞きながら眠りにつける人など稀少と言わざるを得ないだろう。
毎日毎日この付近の峠を走っていればここまで聞こえてくるのは必定。郁人も遠慮会釈なく全開で走っていたりするのでこういう話が出てきても不思議ではない。
「ごめん、五月蝿かったんでしょ? もうちょっと静かに走るようにするね」
申し訳なさそうに手を合わせる郁人に、最初要領を得なかった少女が真っ赤になって否定した。
「あ、ちっ、違うんですっ! 別にうるさくて苦情とか、そんなんじゃないんです!」
郁人は訝るように少女を見た。
確かに少女に騒音に対する嫌悪感や当てつけのようなものは感じられない。さっきの言葉も額面どおりに受け取っていいのかもしれなかった。
「……単車……好きなの?」
意外……と言う響きを微かに乗せて少女に訊いてみた。
少女は少しはにかみながら笑う。
「というか、この単車が好きです。……初めて見たんですけどね」
最初のおどおどした様子はなくなりつつあった。
理解者を得たような、心なしか安心したような声だった。
郁人は意識しなかったが、その表情に少しばかりの翳りがあったのだろう。少女はたちまち元の不安げな声音に戻って
「えと、あの、や、やっぱり……へ……ヘンですか?」
郁人は慌てて
「あ、いや! ヘンじゃない。全然ヘンじゃないよ!」
ぶんぶんと諸手を振って、躍起になって否定した。
「そ……そうですか。よかった……」
少女は小さな胸を撫で下ろすような仕草を見せた。郁人はやれやれといった風に息をつくと、少女の仕草にどこか安堵を覚えて微笑んだ。
「ま、気に入ったんならゆっくり見なよ。時間はたっぷりあるさ」
闇に侵食され始める空をちらりと見やった、郁人の内心は勿論口には出なかった。
少女の顔に見る見る喜色が浮かんだので郁人はそれでよしとした。
少女は座り込んで郁人のドゥカティを眺め始める。駐車場の照明として建てられた水銀灯がゆっくりと光を放ち始め、ドゥカティは昼の陽(ひ)と違う艶めかしい光彩を照り返す。
少女の目に映るそれはまるで宝物でも見るようにきらきらと輝いているのだった。
「さて、俺はコーヒーを買ってくるけど何か飲むかい?」
一心不乱にドゥカティに見入る少女へ郁人は声をかけた。
「え? あ、いえ、そんな、そんなですよ?」
急に現実に引き戻されたように少女が飛び上がって遠慮した。郁人は苦笑した。
「缶ジュースくらいで遠慮しなくてもいいさ。コーヒーは飲める? それとも紅茶??」
少女は真っ赤になって俯いてから
「……あ、そ、それじゃ、ミネラルウォーターで……」
「水でいいの? 別に値段は変わらないから何だっていいんだけど?」
「いえいえ、水でいいんです。すみません」
少女は微笑んだが、今の郁人にその奥の表情を読み取ることはできなかった。
郁人はそれだけを聞くと自動販売機コーナーへと足を向けた。駐車場の端にある自販機コーナーでコーヒーとミネラルウォーターを一つずつ買った郁人は、考えてみればコーヒーと水が同じ値段というのも納得できないなぁ、などと考えながら少女とドゥカティの元へと戻った。
ドゥカティが見えるところまで戻ると人影が二つに増えているのに気づく。
一人は先ほどからの女の子だったが、もう一人は看護婦のようだ。
見慣れた薄いブルーの半袖ナースウェアで遠目にもよく分かる。少女と何かを話しているようだったが、郁人に気づいた看護婦は少女に別れを告げて病棟へと戻っていくようだ。
「どしたの?」
郁人が声をかけると、少女は思いっきり頭を下げた。
「ごめんなさい! 私もう帰らなきゃ! すっかり遅くなっちゃったから……」
見ればもうすっかり日も落ちていた。確かに女の子が出歩く時間ではなさそうだ。
「ああ、ほんとだ」
時計を見ながら少し逡巡した郁人は
「君はどこに住んでるの? 近くだったら送っていくけど?」
少女に訊いた。
「いえ、いいんです。すぐそこですから、歩いて帰れます」
言うが早いか少女は走り出していた。
「あ、おおい!」
郁人は呼び止めたが少女はそのまま走った。そして、気が付いたように足を止めてくるりと振り向いた。
すっかりまばゆく輝いている水銀灯の下で力いっぱい両の手を振って、夜の闇の中へと消えていった。
まるでタイフーンにでも揉まれたような気分だったが、郁人も悪い気はしなかった。
あれだけ自分をストレートに出せるというのは、あの年頃の特権なのだろう。ちょっとばかり羨ましく思った郁人だったが、不意に「あ……」と声を漏らした。
痛いほどに冷えたミネラルウォーターとコーヒーが郁人の手の中にあった。
小さな溜息をついた郁人は「仕方ないな~」と困ったような、そのくせ少し嬉しそうな響きをのせて呟いた。
何故かまたあの娘に遇えるような、そんな気がした。
-----------------------------------------
その週末、郁人はやはり敬一郎の見舞いに美杉病院へと向かった。
街を抜け、いつもの峠に差し掛かると一際甲高いエキゾーストノートが後ろから迫ってくる。
郁人のモンスターはさほどゆっくりしたペースではなかったのだが、モンスターのバックミラーに影が現れると、それはぐんぐんと大きくなっていった。
「四輪……BMW?」
紅い車体とキドニーグリルをバックミラーに認めたその瞬間、郁人のモンスターの傍らを凄まじい勢いで深紅のBMWがパスしていく。
リアゲートに刻まれたエンブレムはM3。
3.2リッター・NA直列6気筒ツインカムエンジンから343psを叩き出す怪物マシンである。
「こんにゃろうめ」
四輪対二輪というのは些かアンフェアだったが、郁人はM900に鞭を入れた。
M3のドライバーはこの道を知悉しているようだった。
かなりの速度でコーナーに突入すると、紅いM3は僅かにカウンターモーションを起こしてそのまま身の毛もよだつようなスキール音を立てながら向きを変えていく。
「……慣性ドリフトですか?」
郁人は幽霊でも見たような、全く信じられないものを目の当たりにした者の声で吐き捨てた。
軽量なM900もブレーキングポイントに差し掛かる。ブレンボのブレーキシステムが目も眩むような速度から一気に車体の速度を削ぎ落とす。
M900のリアタイヤはその瞬間完全に宙を舞い、オーリンズ製のフロントフォークが目いっぱい沈み込む。
郁人の腰がイン側に預けられ、ブレーキのリリースと同時にM900は地面に吸い寄せられるようにバンクした。
眼前には進路に対してほぼ直角に横を向くM3の車体。
郁人はできるだけコーナーの出口だけを見るようにした。
郁人の膝が路面をこする直前にあてがうように大きく開けられたスロットル。M900は猛々しい唸りを上げてコーナー出口に向かって猛然とダッシュをはじめる。
M3は最小限のカウンターステアで、するすると前に出て行く。
郁人の鼻腔にゴムの溶ける刺激臭が微かに届いた。
対向車線に殆どはみ出ることなくドリフトを極めたM3のドライバーの技量は驚愕に値した。
「♪~」
郁人はヘルメットの中で口笛を吹いた。
「こいつはすげーや」
決して広いと言えぬこの峠道で300psオーバーのじゃじゃ馬を完璧にコントロールするのは至難の技だ。
「俺負けちゃうかも」
そう呟いた郁人の顔は愉しそうだった。乾いた上唇を舌がなめる。
確かにスタビリティに優れる四輪は二輪に比べて優位だが、加減速の激しいせせこましいフィールドではその重量があだになりやすい。そしてこの先はトリッキーな変則コーナーがしばらく続くこの峠最大の難所なのであった。
M3のテールへぴたりとつけたM900が右へ出る。タイミングを合わせるかのようにブレーキをきっかけにM3がテールスライドをはじめた。
左、右、左と連続で小さなRを刻むシケインの入り口が郁人の眼前に広がる。
街路ミラーで対向車のない事を注意深く確認してM3のアウトからドゥカティは並びかけた。ここで並んでしまえば次の右でインを獲れる。よしんばここで刺し切れなくても次の左コーナーでアウトからかぶせてやればM3は引く以外にない。
郁人がこの峠で最も得意とするセクションだった。
紅いM3は不気味にうねるブラックマークをアスファルトに刻みながら、正気とは思えないような速度で左コーナーへと突撃する。
郁人は何か事あれば吹っ飛びそうなドゥカティの車体をなだめすかしながらM3の隣をキープしつづける。
強烈なGが郁人とドゥカティをコーナーのアウトへと押し付ける。一つ目の左コーナーが終わりきらないうちに右コーナーが見えた。
左へとモンスターが回頭をはじめた瞬間から、郁人がスロットルを開けながらアウト側へと腰をずらす。
人差し指で切るようにレバーを引いて一瞬間ブレーキをかけると、ドゥカティは弾かれたように反対側へと切り返し始めた。
凶暴なまでの遠心力が郁人を車体から振り落とすように右から左に入れ替わる。右へのフルバンクへ移行を終えた郁人のすぐ隣を狂気のような速度で並走するM3に、退く意思はなさそうだった。
左へのテールスライドが収束するとM3のテールは右へと流れ始めた。
両車は全く譲らずに最後の左コーナーを目指す。
左コーナーのアプローチのためにさっきと同様一瞬フロントブレーキをかける郁人。
その視界をノーブレーキで切り返したM3のテールが流れる。
「ち! タコ踊りしやがったか!?」
激しく左右に揺さぶられた車体が慣性力に抗えずに、翻弄され路上でスピンする映像が脳裏に閃光のように見えた郁人はアウトからかぶせるのを諦めた。
刹那、深紅のBMWは僅かに車体をロールさせながら、一際高らかに吼えた。
M3はひょおっという皮膚の粟立つような音をさせながら、狭いシケインを華麗な連続ドリフトで抜けたのだった。
「…………」
郁人は悪夢でも見ているような気持ちで遠ざかるBMWを見ていた。
少なくとも四輪にこの峠で敗れたのは初めてのことだ。
どこか放心したように、そのまま病院への小途(こみち)へと入っていった。
郁人が美杉病院の駐車場に着くなり、そこに悪夢の続きを見た気がした。
見間違う筈もないさっきのBMWが、まさに駐車を終えてドアが開いた。
勿論郁人は無視を決め込んだ。
『やぁ、さっきは速かったですねぇ』などと雑談する趣味はない。さっさと駐輪場へとドゥカティを置くことにした。
しかしながらBMWのドライバーは郁人を放って置くつもりはなかったようだ。
つかつかと駐輪場へとやってきた。
郁人は意識的に無視しているのでどんな人間がやってきたのかは分からなかった。
「キミ、なかなか速いじゃない。気に入ったわよ」
掛けられた声は意外に女声であった。
「いや~、負けちゃいましたね」
照れ隠しに笑いながら顔をあげて、郁人は吹き出した。
「汚いわねぇ。それとも何? 全く気づいてなかったの? 鳴川クン?」
そこに立っていたのは眼鏡こそ外していたが、紛うかたなき彼の上司にして天敵、高階玲子その人であった。