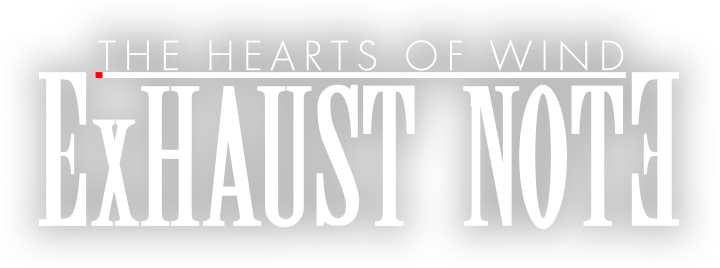novels
白亜の檻
1.
そこに立っていたのはタンクトップにジャケットを羽織りジーンズを穿いた玲子であった。
髪を下ろして眼鏡を外してはいたが間違うはずもない。
よほど間抜けな顔をして玲子を見ていたのだろう。玲子が苦笑しながら「どうしたの?」と訊いた。
「え、あ、いえ……。意外でしたので……」
まろび出た言葉もどこか危うい。普段の玲子を知る郁人にとってこの姿はある意味、クルマに負けた事以上にショッキングなことだったのだろう。
「意外?」
悪戯っぽく玲子が笑うその笑顔の向こうが郁人にはまるで見えなかった。
「は…はい。まさか、このようなところでお会いするとは……」
「あら。私が三木クンのお見舞いにくるのがそんなに意外? 私ってそんなに薄情な女と思われているのかしら?」
郁人は肝を潰す思いであった。
少なくとも郁人は玲子のことをそういう薄情……とまでは言わないもののどこか冷たい女性だという印象をもっていたのは否定できなかった。
玲子はくすりと笑って
「まぁ、いいわ。行くんでしょ? 三木クンのところへ」
「ええ、それはそうなんですが……」
言い淀んでちらりと停められたBMWを見遣る。その視線に気づいて玲子は「ああ、あれ?」と訊いた。
「私だって車の免許くらいは持ってるのよ。休みの日くらいは羽を伸ばしたいしね」
羽を伸ばすとかそういうレベルのドライヴィングではなかったが、それについては何も言わないことにした。
「そうそう」
玲子の髪がふわりと宙を舞うと、柑橘系の香りがした。
人差し指を郁人の口に当てると玲子はまるで少女のようにウインクする。
「私が車に乗っているのは会社では内緒ね。事故を起こして入院してから私は車を降りたことになってるから」
その事実も郁人を吃驚(びっくり)させるには十分なことだ。
「事故?」
意外そうに玲子を見た。
「そ」
玲子はぺろりと舌を出した。
「4年位前かな? 出たばっかりの初期型ボクスターを半年でスクラップにしちゃった」
郁人はもう訳がわからなくなっていた。
会社でキャリアウーマンのオーラをびしばしと発散する姿からは到底想像のつかない玲子がここにいた。
「初期型のボクスターってちょっと非力だったし、ハードに走りこむとブレーキにくるのよね。峠で調子に乗ってインプレッサを突付きまわして遊んでいたらブレーキがフェードを始めて、ペース落とさなくちゃと思いながらそのまま走り続けたらコンクリートウォールにドカン」
両手を小さく広げて『お手上げ』をするようなジェスチュアをする。
「で、そのとき肋骨と腰骨を折って入院3ヶ月。部長にこっぴどく叱られたのよ」
「はぁ……」
人でごった返す待合室を通り抜けながら熱弁を振るう玲子に郁人は気圧されるように相槌を打つ。
正直なところ郁人はこの場を逃げ出したい気持ちでいっぱいであったが、ここで逃げ出しては後で何を言われるか分かったものではないので黙っておいた。
そんな時に掛かった「こんにちは」という第三者の声は郁人にとっては天の助けのようなものだったろう。
玲子と郁人は声のした方を振り向くと、やはりTシャツとスパッツのくだけた格好で小さな、少女といってもいい年頃の女の子が二人の方に深々とお辞儀をしていた。
以前会った時と違うところといえば、長い黒髪を横でまとめて飾りつきのバンドで括っている事くらいだろうか。
「あ」
郁人は少女に気づくと「こんにちは。今日も遇ったね」と微笑んだ。
少女は「はい」と快活に答え、
「単車の音がしたから急いで来たんですよ」
そう言ってとびっきりの笑顔を見せた。
「ねぇねぇ」
二人の様子を伺っていた玲子が郁人の袖を引いた。
「ずいぶん仲が良さそうだけど、この娘(こ)の事は私に紹介してくれるのかな?」
ん~~? と幾分意地が悪そうに玲子は郁人の顔を覗き込む。
「えっと、その……」
郁人はその時初めて返答に窮した。そういえばこの少女の事を郁人はまるで知らないのだ。
その様子を見ていた少女はくすくすと笑いながら
「私は水無瀬雪乃(みなせゆきの)と言います。この近所に住んでる女子高生です」
ぺこりと頭を下げたが、郁人は驚きを隠さなかった。目の前にいる少女はどう見ても女子高生という歳には見えない。
「こ……高校生だったの? キミ……」
口をパクパクさせながら郁人は言ったが少女……雪乃は少しばかり頬を膨らませた。
「あ、それすっごく失礼な反応ですよ? これでも背の低いのは気にしてるんですから」
背が低い……とかそう言ったレベルの幼さではないのだがそれ以上は流石に突っ込めなかった。
「そうよ、鳴川クン。レディに対してそんなことを言ってはいけないわ」
その声の裏側を感じ取った郁人は、先程より更に自分の置かれる状況が悪化していることにようやく気づいた。
針の筵(むしろ)というのは多分こんなのだろう。
「あ、私は鳴川クンの会社の上司で保護者(笑)の高階玲子です。いつもコレがお世話になってるみたいね」
玲子が郁人の頭をぽんぽんと叩きながら雪乃に自己紹介した。手毬のように郁人の頭を叩いているのはどうやら謝罪しろと言うことらしい。
「どうも、鳴川郁人です。先程は大変失礼いたしました」
と、頭を下げた。
「それにしても意外ね。鳴川クンも隅に置けないんだ」
ちらちらと郁人と雪乃を見比べながら玲子が言ったが、その口調は郁人を弄るネタを得た喜びに溢れているようだった。
「いや、あの……」
「最近は歳の差なんてあまり問題にならないし、鳴川クンに春がきて保護者としても嬉しい限りね」
ニコニコしながらそう言う玲子の台詞の陰にある棘に気付いて、郁人は大いに狼狽した。玲子の声の裏側には陰火の如くちろちろと燃えるドス黒い炎が隠れているに違いなかった。ここを何とかしなくては事態は収拾がつかなくなりそうだ。
「あ、ああ、あのあの!」
郁人は不意に大きな声で二人の間に入った。
少女に小さく手を合わせると
「ゴメンね、これから部下の見舞いなんだ。すぐ戻るから単車でも見て待っててくれるかな?」
そう言って玲子の背中を押した。
「さささ、三木の見舞いに行きましょう! 今すぐ! 可及的速やかに!」
「ああ! こら、鳴川クンってば!」
白い病院の廊下に暫く郁人を罵る玲子の声が聞こえたが、それもすぐに聞こえなくなった。
雪乃は一人呆気にとられながらその場でその様子をずっと見ていたのだった。
敬一郎の病室に向かう途中、問い詰められるかと思ったが意外にもそれ以上の追求はなかった。まさか敬一郎の前であからさまにそのネタを振るとは思えなかったが、何が原因で玲子の機嫌が損なわれているかまでは郁人の知る由のないことであった。
敬一郎の病室につくとやはり敬一郎は魂を抜かれた人形の如く、何か物の怪でも見るかのように玲子を見上げていたが、持ち前の人間の軽さで郁人よりは柔軟な態度を示した。
「そうそう、三木クンも聞いてよ。今さっき私、信じられないものを見たのよ」
そう言って郁人を意味ありげな視線で見る玲子。郁人は直感した。
「いや! だから誤解ですって!」
「あら、何が誤解なの? 説明していただけるのかしら?」
「いや、その、だから、あの娘(こ)とはこないだ知り合ったばっかりで……」
動転して自分が地雷を踏んだのにも気付いていないようだ。
「鳴川さん、あの娘って誰っスか?」
「いやいや待て待て。落ち着くんだ二人とも!」
「……あなたが一番取り乱してるわよ」
「そんなことはない! ……と思う…かも」
郁人の額をがまの油のような妙な汗がだらだらと流れていく。
「……性犯罪者……」
したり顔でぼそりと玲子が呟くと郁人が真っ白になって停止した。
「何? 何?? 何なんスか???」
要領の得ない敬一郎が玲子に真顔で訊いた。犯罪者とは穏やかではなさそうだ。
「ロ……」
「わー! わー! わー!」
玲子の一言で郁人が壊れて奇声をあげ始めた。その結果飛んできた年配の看護婦に三人は静かにするようにと叱られた。
看護婦がナースステーションに戻ったあと、玲子は郁人を見て念を押すように言った。
「まぁ、それは冗談としても問題だけは……」
「そんなんじゃないです!」
郁人は勘弁してくださいよといった風に抗弁した。
「たまたま下の駐車所で出会った女の子なんですよ。何でもモンスターが好きらしくてわざわざ見に来たみたいです」
そこまで郁人が言うと、玲子はちょっとばかりつまらなさそうに「ふ~ん」とだけ言った。
信じきった訳ではないが一応そういうことにしておこう、といった返事であった。
「そういえばカノジョ、待ってるんじゃなかった? 鳴川クンってば冷たいんだ?」
「なんですと? 俺のお見舞いじゃなかったっスか? デートっスか!? デートなんスか!!??」
「いやいやいやいや! べっ……べべ……別に俺はそんな…!!」
「吃ってるわよ?」
勿論本気というわけではなく郁人をダシに遊んでいるだけだが、普段の玲子を見慣れている郁人は冗談とはとらなかったようだ。
「ち……小さな女の子なのに単車に興味があるって、ふ…不思議な気がしたからちょっと話を聞いてただけです。勿論そんなやましい事は……」
慌てふためく郁人に玲子が「ぷっ」と吹き出して、噛み殺すように笑い始めた。
その様子を見ていた敬一郎も声をあげて笑ったが、郁人は一人憮然としていた。
「ああ、可笑しい。冗談よ。別に疑ってなんかいないわ」
郁人は何かを言いたげな苦笑を頬に刻んだ。
「でもね、あの娘が待ってるのは事実でしょ? 後は私に任せて行ってあげなさい」
「でも」
と言い淀んだ郁人の背中をぽんと玲子が叩いた。
「ほらほら、行った行った。三木クンの見舞いはもういいでしょ?」
「高階さん、それビミョーな台詞っス」
敬一郎は苦笑しながら突っ込んだ。
郁人は多少ばつが悪そうに笑った。確かにあの少女なら何時間でも単車の前に座り込んで待っていそうだ。
「ごめん。じゃ、ちょっとだけ相手してくるよ」
そう言って郁人は玲子と敬一郎に軽く会釈して、風のように病室を出て行った。
途中の自動販売機でミネラルウォーターとコーヒーを買った郁人は駐輪場に向かった。
果たして、黒髪を横に結った小さな白い少女が郁人の黄色いドゥカティの傍らに座り込んで、飽きもせずにじっと単車を見つめていた。
郁人はTVでよくやるように後ろから近づき、キンキンに冷えたミネラルウォーターを少女の頬に当ててやろうと、あからさまに怪しい足取りで隠れたが、不意に顔を上げた雪乃に気付かれて計画は失敗した。
少女の顔に、ぱっと花開くような笑顔がこぼれた。
郁人はやや決まり悪そうに頭を掻いた。
「ごめん、待たせちゃったね」
そう言って郁人はそのまま雪乃に歩みより、ミネラルウォーターを手渡した。
少女はちょっと意外そうな顔をして、小さく「ありがとう」と言った。 それから少しはにかんだように微笑って、
「ずっとこの子を見てたから、平気です」
雪乃はドゥカティをもう一度見た。
昼下がりの初夏の耀(ひかり)が黄色いタンクの上できらきらと輝いていた。
「本当に好きなんだねぇ。コイツが」
郁人も雪乃の視線に倣った。
「私……」
雪乃がぽつりと言った。
「私、この歳になっても旅行って行った事ないんですよね。だから、単車に乗って何処までも行けるのってすごく憧れちゃうんですよ」
その言葉はもしかしたら独り言だったのかもしれない。何処の誰へという訳でなく、ただ事実を口にしたかっただけなのだろう。この少女にしては珍しく、その言葉は虚ろに響いて消えていった。
だからというのは理由たり得ないかも知れない。
少女が見せた一瞬の空虚に青年は動揺した。もしかすると少女の家族が入院していて旅行どころではないのかも知れない。この娘には何の罪もありはしないのに、旅行すら許されない。
不意に郁人の口をついて出た言葉は、彼の意思では止めることができなかった。
「んじゃ、コイツでどこか行ってみる?」
郁人は努めて軽い冗談の口調を装った。
何せ知り合ってまだ2日目の、まだまだ何処の誰とも知れぬ間柄でそうやすやすと誘いに応じるとは思えなかった。
だからこそ、
「ホントですか!?」
と雪乃が喜色満面に応じた瞬間
「はっはっは、やっぱりねぇ。冗談、冗だ――って、何ですとぉ!?」 と思いっきり滑ってしまった。
その時の雪乃の落ち込み様はなかった。
は――っと大きく息をついて、大いにがっかりした風に
「冗談ですかぁ……。残念です……」
そう言った雪乃の目尻に光るものを見つけてしまって、郁人は引くに引けなくなった。
コレが世に言う女のブキなんだろうか? 良いように篭絡されている気がしないでもないが、これで「また今度ね」などとは言えなくなった。
「わかった! わかったってば! 連れてく! 連れてくから泣くんじゃない」
「やったぁー!」
郁人が折れたと同時に雪乃が飛び上がった。
計画的犯行の模様。
「その前に!」
郁人は小躍りしている雪乃にこほんと咳払いをしてから言った。
「親御さんの了解とっておくこと。分かった!?」
未成年者略取なんて事件が多発している最近、保護者に無断で連れ出したとあっては通報されても文句は言えない。
大体にしてそんな何処の馬の骨とも知れない男にツーリングに連れて行ってもらうなんて、普通の神経をしている親なら許す筈はない。
それが最後の拠り所であったのだが、「それじゃ今からお母さんに断ってくるね」と一目散に病棟へ入る少女の姿をみて、郁人の自信は早くも揺らぐのであった。
2.
次の日の日曜日、郁人はドゥカティを暖気しながら自問した。
「なんでこうなるの?」
昨日、美杉病院の駐車場で雪乃とツーリングに行く約束をした郁人は「保護者の了承を得ること」を条件に提示した。
勿論郁人はこの条件が如何に難題であるかを理解していたはずなのに、不安をぬぐいきれなかった。
そして病棟へと入っていった雪乃は、母親らしい女性と共に降りてきた。何処となく雪乃に雰囲気の似た、優しそうな、だが少しだけどこか疲れたような儚(はかな)い印象の女性だった。
深々と女性がお辞儀をしたので郁人もつられてお辞儀をした。
「この娘の母親の美雪と申します。娘がいつもお世話になってます」
「は、はぁ。こちらこそ」
郁人は頼りなげに応えた。まだ遭って2日目だからそれほどお世話はしていないんだが、その辺を突っ込むと話がややこしくなりそうなのでやめておいた。
「ねえ、いいでしょ? お母さん?」
雪乃がせっつく様に美雪の袖を引っ張った。
ちらりと娘を見た美雪は『しょうのない子ねぇ』と言いたげに苦笑して、
「初めてお会いする方にこんなことをお願いするのは心苦しいんですけど、どうかこの娘を一緒に連れて行ってやってもらえませんか?」
と郁人に再び頭を下げたのだ。
なんだか妙な展開だったが、こうなってしまった以上郁人に選択の余地はなかった。
「分かりました。責任を持ってお嬢さんをお預かりします」
郁人はかしこまった風に返答し、清里高原への日帰りツーリングプランとルートを美雪に伝えたのだった。
郁人は空を見上げた。
空は何処までも抜けるように蒼く、僅かばかりの雲が街並みの向こうに垣間見えた。
雪乃とは美杉病院前のバス停で待ち合わせている。
郁人はアイドリングの安定し始めたM900をそろそろと走らせた。
美杉病院前のバス停に郁人が到着すると、そこには既に雪乃と美雪が待っていた。
雪乃はピンクと白のトレーナーにジーンズ、背中に小さなデイバッグといった出で立ちである。
「おはようございます」
エンジンを止めて郁人が二人に声を掛けた。二人は呆気に取られたように郁人を見ている。
「?」
郁人が訝るように二人を見ると美雪の頬が微笑みを形作ろうと引きつった。
「す……すごい音ですね……」
どうやら2人ともドゥカティのエキゾーストノートを間近に聞いたのは初めてだったらしい。
少なくともこれほど大音声(だいおんじょう)のオートバイなど彼女たちの知識の埒外であったろう。
「こ……こんにちは…」
雪乃も軽く耳に当てていた手を下ろしながら小さくお辞儀した。
ヘルメットは持っていないということなので、郁人はスペアのヘルメットを雪乃に手渡した。
「……ちょっと大きいかも~」
ヘルメットを試着した雪乃は、ぶかぶかの白いジェットヘルをガサゴソと揺らしながら苦笑いする。
「タオルを真知子巻きにしたら?」
美雪が雪乃に提案したが雪乃はそもそも真知子巻きを知らなかったようだ。きょとんと美雪を見返すその瞳の重さに耐えられず、美雪は「あう~っ」と呻いた。
「と、とにかくアゴ紐はしっかりとね」
その様子を苦笑交じりに見ていた郁人は雪乃のヘルメットのアゴ紐を調整する。
美雪は二人を優しい眼差しで見つめるのだった。
「さて、それじゃそろそろ……」
そう言ってシートに跨ろうとして郁人は、視線をふらふらと泳がせて戸惑いの色を見せる雪乃に気付いた。
「あの、ごめんなさい」
困ったようにヘルメットの奥の可憐な瞳が郁人を見上げる。
「私、オートバイって乗った事ないんですよ。何処にどう乗ればいいんですか?」
勿論郁人のモンスターはタンデムするためにシートカバーが取り払われているが、そも雪乃は単車自体に跨った事がない。蓋(けだ)し、乗り方を知っていたところで150cmに満たない身長の雪乃には一人でモンスターのタンデムシートに乗る事は難しそうだった。
郁人はタンデムステップを引き出して、単車が動かないように押さえながら雪乃に手を差し伸べる。
「片足をステップに乗せて飛び乗るように跨って。手を持っててあげるから」
雪乃は美雪と郁人を交互に見比べて暫しの逡巡を見せたが、美雪がにこりと微笑んだのを見てから郁人の手を取ってモンスターのリアシートへと飛び乗った。
僅かばかりモンスターが傾いだが、支えが必要なほどではなかった。
郁人は雪乃を蹴り落とさないように用心深くシートに跨って、
「しっかり俺の腰を持っててくれな。できれば手をこう回して、オレの腹の所で手を組み合わせてくれるとありがたい」
「え? あ……う~~っ」
真っ赤に頬を染めながら雪乃は今にも泣き出しそうな顔で、それでも素直に郁人の言葉に従った。
そんな恥ずかしくも微笑ましい二人を見ながら美雪は
「じゃあ、気をつけて。鳴川さん、娘をどうかよろしくお願いしますね」
そう言って深々と頭を下げるのだった。
「あ、いや、その……。こちらこそよろしく」
あまりにも真剣な美雪のその願いに郁人の答えはまるでちんぷんかんぷんなものになったが、郁人がその真意を知るのはもう少し後の事である。
そして郁人がセルボタンに指を掛けようとしたとき、「そうそう」と言って美雪が懐から一枚の紙片を取り出して郁人に差し出した。
それは名刺であった。
「何か困った事があったら下の携帯まで連絡してください」
随分周到なことだが、確かに何かあった時に連絡がつけば心強い。
「分かりました」
そう言って郁人が名刺を受け取る。
そこには何やら横文字の、ブティックか何かの店長の肩書きと共に水無瀬美雪の名と店の代表電話、携帯の番号が印刷されている。
凝った紙質の、上等な名刺だった。
(もしかしてお金持ちなんだろうか?)
郁人は二人を見たが、別段ブルジョワジーと言う訳でもなくごくごくありふれた家庭のように見えた。
「じゃ、行ってくるね」
そう言って雪乃が小さく母親に手を振った。
郁人は名刺を仕舞い込むとセルボタンに触れた。
軽いクランキングの音と共に続いてボンと鋼の心臓に命が宿る。
乾式クラッチが立てる打音をバックに、チタン製のテルミニョーニマフラーが雄大なデュエットを奏でる。
郁人は軽くアクセルを吹かすとクラッチを繋いだ。904ccのLツインエンジンは乾式クラッチ特有の高音を一瞬立てたあと、二人を乗せてオープンロードへ車体を推し進めた。
雪乃は後方へと過ぎ行く美雪をちらりと見遣り、もう一度小さく手を振った。
美雪も軽く手を振った。
徐々に高まるエキゾーストノートに反するように小さくなってゆくその姿を、美雪は手を振りながらいつまでも見送っていた。
美雪の姿が見えなくなった後、雪乃は声が出そうになるのを必死に堪えていた。
初めて乗ったオートバイはどこか落ち着かない。加えて結構前後に揺れる。加速する度に雪乃の体は大きく後ろにのけぞり、減速する時は郁人の背中にヘルメットがごんごんと接触する。
モンスターの不安定なリアシートが慣れない雪乃の体を固くさせ、幾度もずり落ちそうになった。
単車に乗るときに郁人が「腰に手を回して手を組んで」と指示するのも分かる。
雪乃はぎゅっと目を瞑って郁人にしがみついた。
不意に腰に回された手に力が入って郁人は後ろを見た。雪乃は小さな体をさらに小さくしながら、ただそこにいた。注意すれば雪乃が震えているのも感じられた。
これでは何のために連れ出したのか分からない。
郁人は己の不明を恥じた。
「ごめんね」
信号で停まった際に郁人は雪乃にそう言った。雪乃は意味を理解することが出来ずに郁人を見上げた。
信号が青に変わって、モンスターが走り出す……が、今度は雪乃の体が遅れることはなかった。風景は緩やかに流れ、優しい風が二人の傍らを通り過ぎてゆく。
雪乃は周囲を見た。
道が変わったわけではなさそうだった。雪乃は先ほどの郁人の謝罪の意味を理解した。
ドゥカティのエンジンは元はと言えばレーシングエンジンである。
公道を走るためにエンジン性能を穏やかにして扱いやすく、耐久性を持たせるように躾られてはいるが、国産車のようにストリートバイクとして設計されたものではない。
ラテンの熱い血がそうさせるのか、このイタリアの悍馬(かんば)はゆっくり走ることを拒絶する。
それを穏やかに、後部座席にショックを与えぬように走るのは並々ならぬ神経と技術を要することなのだ。
だがその甲斐あって雪乃はそれ以降、周囲に目を配る余裕すら生まれた。
「うわーーっ」
雪乃が突然背中で大声を上げたものだから郁人はびっくりした。
「な、何? 何?? どうしたの???」
テルミニョーニマフラーの吐き出すエキゾーストノートに負けまいと、大声で雪乃に訊いた。
周囲はどうということのない国道で、森を抜けたあとはパラパラと民家と田園ががあるばかりで特に眺望が良い訳ではない。普通なら退屈な移動区間であるはずの場所で、雪乃はまるで初めて世界に触れたかのように目を輝かせて周りを見ていた。
「す……スゴイです! 風景が飛んでいきます! 風を切ってます! 音も凄いです! 私たちまるで魔法の絨毯(じゅうたん)にでも乗ってるみたいです!!」
マシンガンのように撃ち出される雪乃の感想に郁人はやや気圧されながら
「あ、う……うん。そうだね」
と応じた。
いつしかモンスターは郊外を走っていた。
緩やかなカーヴの連なる山並みを縫うように、整備された路が続いていた。
馥郁とした木々の馨りと、目の覚めるような碧(みどり)が二人を包み込んだ。
それまで大声で感歎の声をあげていた雪乃の声が徐々に小さく少なくなり、ついに黙り込んでしまった。
風景を見るのに飽きたのかと思って郁人がさりげなく後部座席を見てみると、雪乃はまるで今目にしている風景を愛しむように、慈しむように、そして決して忘るるまいと心に刻み込むように見ていた。
その貌(かお)が何だかひどく淋しげに見えて、郁人は見てはならないものを見たような、言いようのない罪悪感に苛まれてすぐに視線を前へと戻した。
モンスターのデスモLツインエンジンが、会話の途切れた二人の間を取り持つように揚々とエキゾーストノートを謳い上げた。
山並みを抜けるとぱっと視界が拡がった。
そこは大きな溪谷のようだった。
両脇の緑が一瞬にして消え去り、彼方に山が見える。
路は途方もなく大きな橋によってまっすぐ何処までも伸びているのだった。
雪乃は息を呑んだ。
雪乃の心を世界が侵食した。
ここにあるのは広い背中とオートバイと自分だけだった。
抜けるように高い蒼穹と遥かに霞んで滲む山並みは何処までも遠く、畏(おそ)れさえ感じるほどに広大であった。
知らず、雪乃の頬を伝うものがあったが、ついに郁人はそれに気づくことはなかった。
郁人の目に映るものは見慣れた、だが極上に心地よい風景。
ドゥカティは二人を乗せて走る。
二人の目に映る風景がまるで違った色を帯びていても、同じ風をまいてひとつの道をひた走る。
例え行き着く先が同じであろうとも、二人の想いは暗夜に浮かぶ星ほどに離れていたのだった。
3.
2人を乗せたドゥカティはいくつかの交差点を折れて広い駐車場に出た。
駐車場にはかなりの台数の車が停まっており、少なからぬ人出が予想できた。
客船が接岸するようにゆっくりと駐車場の隅へと単車を停めた郁人は一つアクセルをあおってキーをオフにした。
エンジンから立ち上る熱気と陽気で少し暑い。
郁人は振り返り、
「お疲れ様。到着だよ」
と微笑んだ。
雪乃はほんの少し痛くなったお尻と頼りない足を気遣うようにして、よろよろとステップの上に立ち上がると単車の横へ飛び降りる。
う~…ん、と大きく伸びをして全身の凝りを解す雪乃を見ながら郁人は苦笑する。
「やっぱり単車に乗り慣れてないとツラかったかな? 休憩入れた方がよかったな」
雪乃は小さくガッツポーズして
「これくらい平気です。それに、すっごく気持ちよかったから気になりません」
その顔は心底ツーリングを愉しんでいる様だったので郁人は安堵した。
「ここはどのあたりなんですか?」
雪乃はくるくると周囲を見回して訊いた。
山や森に囲まれた丘陵地のようだったが、地理に疎い雪乃には皆目見当のつかない場所だった。
「ここかい?」
郁人はヘルメットとグラブを脱いで遥かに遠い峻嶺を見た。
「ここは山梨県の清里高原、清里の森だよ。結構いい所だろう? 自然のほかにも美術館とかオルゴールの博物館とかいろいろあるんだ」
雪乃は郁人の説明に目を輝かせて聞き入っていた。
「……女の子にも人気あるみたいだしどうかなって思ってさ」
雪乃の顔にこぼれるような笑みが咲いた。
郁人は雪乃から顔を意識的にそむけるようにしてヘルメットを受け取ると、単車にかけるチェーンロックに自分のヘルメットを含めた2つのヘルメットを通して鍵をかけた。
照れくさいのである。
施錠を終えた郁人は立ち上がって空を見た。
日は既に中天にあった。
名も知らぬ小鳥が囀(さえず)りながら2人の頭上を飛んでいく。
「確かこの近くにレストランがあったはずだよ。頃合もいいしお昼にしようか?」
郁人の提案はしかし雪乃によって呆気ないほど簡単に却下された。
「あ、私お弁当持ってきたんですヨ。水筒もちゃんと入ってます」
そう言って雪乃はぴょんと後ろを向いた。
背中のデイバッグは小振りではあったが、確かに結構重そうだった。
「そいつはいい。手製の弁当なんて何年ぶりだろ??」
誰も手製だなんて言ってないんだが、郁人は感激のあまり涙が出そうになるのを堪えて感謝を捧げた。、
「でも私はお手伝いしただけで、全部を作ったわけじゃないんですけどね」
雪乃はばつが悪そうにぺろりと舌を出して苦笑した。
郁人は破顔して
「いいさ、いいさ。次に機会があったらお願いするよ」
軽い冗談のつもりで言ったが、雪乃は少しだけ寂しげに微笑んだ。
「そうですね。次は頑張りますね」
その声音(こわね)に郁人は言いようのない響きを聞いたが、うまく言葉にすることは出来なかった。
喩えるなら咽喉に魚の小骨の刺さったようなもどかしさとでもいうのだろうか。
時々この少女は幼い外見にひどく不釣合いな表情を見せる。
郁人は頭(かぶり)を振った。
「さて、と」
そう独りごちて郁人は踵(きびす)を返した。とにかく今はツーリングに来ているのだ。不景気な顔などを雪乃に見せてこの場をしらけさせる道理はない。
「じゃ、広場でその弁当を食べよう。外で食べる弁当は格別だと思うよ」
郁人は笑顔を作って歩き出した。
雪乃は「はいっ!」と輝くような笑顔で小走りに郁人についていった。
少し歩くと広大な草原に出た。
微かに立ち上る草いきれに雪乃はまるで小さな……いや、幼い子供のように駆け出して、胸いっぱいにその空気を吸い込んでいた。
何組かのカップルや家族連れが点々と緑の中に腰を落ち着けている様子を、雪乃は物珍しそうに眺めては、楽しげに笑顔を振り撒いて郁人の周りをくるくると踊るように廻るのだった。
二人は草原の中ほどにシートを広げて腰をおろした。
少し恥ずかしそうに、雪乃はデイバッグから水筒と品のよい包みにくるまった重箱を取り出した。そのサイズは家族連れの運動会もかくやと言うほどで、二人で食べるには些か大きすぎるようだったが、折角の弁当にケチを付けるのも憚られるため郁人は口を噤んだ。
「お口に合うかどうか分かんないんですけど……」
きつく結ばれた口を解くのに少しばかり時間を要したが、雪乃は2段重ねの重箱の蓋を外した。
中は見事な出来栄えであった。
ただひとつ、卵焼きだけがいびつな形をしており、売り物さながらの弁当箱の中で違和感を醸しているのだった。
「この卵焼き……」
何か変だね、と言いかけた郁人は、だがしかし最後まで言葉を口にすることはできなかった。雪乃が慌てふためいて卵焼きを手で覆い隠し、「わわわ、こ……ここ、これわですね?」と、しどろもどろになりながら素っ頓狂な声を挙げた所為だ。
流石の郁人もピンと来た。そう言えばさっき、雪乃は弁当を作るのを手伝ったと言ったのではなかったか。
なんなれば、例え如何な出来であろうとも郁人はこの卵焼きを貶(おとし)めてはならなかった。
郁人は雪乃から割り箸を受け取る前に素手で卵焼きをひとつつまむと、雪乃が止めるより早くそれを口へ運んだ。
がりりという卵焼きに本来あってはならない歯ごたえがあったが、郁人は表情ひとつ変えずに咀嚼する。雪乃はその様子をまるで最後の審判が下される咎人(とがびと)のような面持ちで見守った。
「ふむ」
卵焼きを嚥下して、指をぺろりと舐めた郁人は微笑んだ。
「うん、旨いじゃないか」
それは嘘偽りのない言葉だった。
確かに予定外のカルシウム片は混入していたが、味付けは絶妙といえた。火の通り加減も文句のつけようのないものだ。
雪乃の顔がくしゃっと潰れたように見えた。雪乃は泣きながら笑っていた。その瞬間、全ての罪が赦されたかのような、安堵と感謝と充足感に満ちた表情(かお)であった。
「ありがとうございます。まだまだありますから召し上がってくださいね」
それだけ言うのが、今の雪乃の精一杯だった。
抜けるように蒼い空の下で二人は弁当を食べた。雪乃は殆ど弁当には手をつけず、郁人にあれこれとおかずを勧めてはいちいち感想を聞くのだった。それから雪乃は寸暇を惜しむように質問を投げかけた。
ごくごく些細なことから、中には郁人が喉を詰まらせそうになるような話題まで、雪乃は立て続けに訊いた。数秒と会話が途切れることはなく、次から次へと泉のように言葉が雪乃の口から湧き出てくる。寸暇を惜しむように、片時たりとも無為にしないように、この瞬間が総てであるかのように。
単車に乗り始めたきっかけ、今まで単車に乗っていて良かったこと、辛かったこと、今までに行った場所のこと、出会った人のこと、単車以外の趣味について、休日の過ごし方、そして好きな人のこと……。郁人は丁寧に(あるいは巧くはぐらかしながら)それら雪乃の質問に答えていったが、次第に焦燥感を募らせている自分に気づいた。
それらは特段ツーリングにきて話す内容ではないように思えたのだ。
せっかく清里高原まで来たのだから、ここでしか体験できないことを雪乃に味わってもらいたかった。
弁当を食べ終えた郁人はまだまだ続きそうな質問攻勢に待ったをかけて、郁人は雪乃に周囲の散策を提案した。
この近辺なら「清里の森美術館」、少し単車で移動することになるが「ホールオブホールズ(オルゴールミュージアム)」、ガラス工芸で有名な「北澤美術館」、豊かな自然が満喫できる「美しの森」あたりが女の子にもお勧めできるスポットだろう。
郁人の提案に少しばかり悩む仕草を見せた雪乃は破顔して、「じゃあ、ホールオブホールズに」と言ったのだった。
ホールオブホールズは清里の森から少し南東に下った所にある「萌木の村」にある。アンティークとしても評価の高い自動演奏楽器やオルゴールを集めた博物館で、実際に演奏も聞くことが出来る。
ハンドルを手で回して聞く手回しオルガン「オルガネッタ」や、アナログ盤にピンがついたような「ディスクオルゴール」などの素朴な音色に魅了される人も多い。
雪乃は館内に入るや、はぁっと息をついた。
壮麗豪奢なクラシックオルゴールの精緻な技巧に目を奪われ、奏でられる神韻に心を奪われた。
郁人はそんな雪乃の様子を目を細めながら見ていた。
或いは雪乃のこの表情を郁人が見たかったのかもしれない。連れて来てよかったと自分に納得させるために。
そんな心を気取られないように「知ってる?」と雪乃に訊いた。
「オルゴールってのは何語か知ってるかい?」
雪乃は目をぱちくりさせて、意外な問いに頭を悩ませた。
「え……っと、ポルトガル語……とか??」
もちろんでまかせだったが、郁人は「おっ?」と言う顔をした。南蛮渡来品と言うことを考えれば十分に考えられるからだ。
「惜しいが違う。実はオランダ語由来の日本語なのさ」
郁人はやや自慢げに言った。ネットで拾い集めたトリビアだったが、意外な所で役に立つものだ。
「語源はオランダ語の『オルゲル』から来ているらしいけれど、『オルゴール』って楽器を指す言葉は日本語なんだよ」
余談だが天麩羅(てんぷら)、金平糖(こんぺいとう)もポルトガル語(テンポラ、コンフェイト)を語源とする日本語である。
「因みに英語ではオルゴールをミュージックボックス(※)っていうのさ」
そんな説明にも雪乃は目を輝かせ、オルゴールの音色に聞き入るのだった。
おみやげ物売り場ではあれこれと小さなオルゴールを取り上げてはその音色に耳を傾ける雪乃に、郁人は「欲しいの?」と訊いた。
雪乃は即座に顔を真っ赤にして首を振った。
「いえいえ、今日はお小遣いそんなに持って来てないですから……」
雪乃が持っていたのは小さな匣(はこ)だった。
掌に乗りそうな、シンプルな宝石箱にぶら下がる値札を見て郁人の眉がヒクリと動いたが、ここで引いては無粋と言うものだ。
お土産にするにはちょっとばかり痛い値段だったが、あれだけのお弁当を作ってもらってお礼も何もなしでは人としてどうかと思ったし、何よりこの少女の初めての旅に何かしら形に残るものをあげたかった。
「それがいいんだ?」
郁人の問いかけに雪乃はぎょっとなった。明確に郁人の意図する所を感じた所為だ。
「そ・それはその! すごく良いとは思うんですけど、わ……わわ私こんな……」
何かを言いかけた雪乃だったが、「すごく良い」と言った時点で雪乃の敗北である。
雪乃が泡を食っている間に郁人は宝石箱を取り上げて、「プレゼント包装で」と、さっさと会計を済ませてしまった。
「はうー……もしかして私ものすごく迷惑なのでは……?」
メイプル材で出来た匣が手際よくエアパッキンに包まれて包装紙の中に消えてゆく様を見つめながら雪乃は泣き言にも似たか細い声で言った。
郁人は雪乃の肩を軽く叩きながら
「いいって。今日は一日目一杯楽しんでもらいたいからね」
そう、今日一日だけは雪乃の為にあるのだと、郁人は言ったのだ。
郁人は不思議な気持ちだった。一昨日出逢ったばかりのこの少女を、何故これほどまでに気遣ってしまうのか巧く言葉にすることは出来なかった。
一つだけ言える事は、この小さな少女の持つ空気がまるで玻璃(はり)のように繊細で脆くて儚げで、けれど何処までも美しく透き通っていることに郁人はえもいわれぬ感情を持ちつつあるということだ。
それは憐憫とも焦燥とも悲哀とも少し違う。勿論思慕とも恋愛とも違った。
ありがちな言葉で言うならば、「放っておけない」とでも言うのが一番近かろうか。
少女は歳相応にころころと笑顔を振り撒いているが、危うい硝子の天秤の上で辛うじて平衡を保っているような、どこかにそんな影の匂いがした。
雪乃のデイバッグにオルゴールを詰めて、努めて明るく
「さ、次は何処が良い?」
と、郁人が聞いた。
雪乃はデイバッグを気にしながら、少し考えたようだった。
「お茶にはちょっと早そうですね」
時計をちらちらと見遣って雪乃は呟いた。
「じゃあさ、少し歩こうか? すごくいい眺めの所があるんだ」
郁人の提案に雪乃は手を軽く合わせて夢見がちな少女のように目を見開いた。
「わ。何処なんですか?」
「ちょっとさっきの森の方へ戻るけれど、『美しの森』なんてどうかな? 自然が一杯の中を森林浴すれば気持ち良いと思うよ」
雪乃はいつもの笑顔だった。
それから程なく、ドゥカティで美しの森へ移動した二人はレンゲツツジで紅く萌える丘をゆっくりと登り始めるのだった。
違和感を郁人が覚えたのは15分も歩いた頃であろうか。
雪乃は何でもないところで度々止まっては、座り込んで草花を愛でるように見つめるのだ。無論、その様子が変だったわけではない。だが、意図し得ぬ何かがそこに介在しているかのように思えてならなかった。
「大丈夫? 疲れてない?」
郁人の問いに雪乃は笑顔で応えるのだった。
しかしその笑顔とは裏腹に雪乃の歩みは徐々に速度を緩めてゆき、遂に苦笑とも自嘲ともつかない微笑を頬に刻んで困ったように言った。
「日頃の運動不足が祟ったみたいです。少し休ませていただけませんか?」
郁人に否やはなかったが、もとより紙の色を刷いたような真っ白な少女の肌が、今や青紫色に転じているのを認めて大いにうろたえた。
どう見ても健常な顔色ではなかったのだ。
郁人は即座に雪乃の肩を取って木陰まで連れて行き、適当な所に座らせたが正直どうしてよいものか分かりかねた。
雪乃の呼吸はいつになく荒くなっていた。耳を傾ければ喘鳴が微かに聞き取れる。
雪乃の体調の変化は突然で唐突でそして急激であった。
「やっぱりお昼の薬を抜いたのは失敗だったか~」
悔悟とも取れる独語をうわ言のように言った後、小さく
「すみません。ちょっとだけ休ませて下さい。すぐに快復しますので……」
そう郁人に言うや、ずるずると上体を傾けてそのまま草の上に横になってしまった。
それから雪乃は目を閉じてぴくりとも動かなくなってしまった。