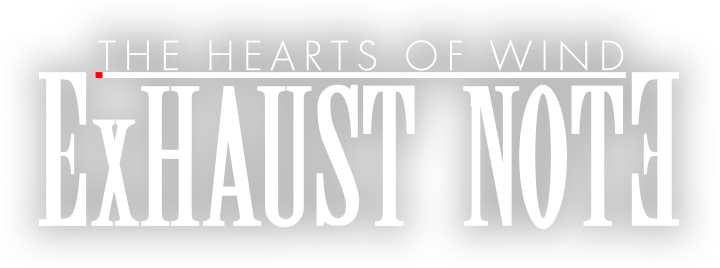novels
白亜の檻
1.
雪乃が眠りに堕ちて30分ほどが経過した。
郁人はその間雪乃の傍らに座り込んで、つぶさにその寝顔を見ていた。
いま、郁人の心は猛烈な葛藤に見舞われている。それはこの少女と出逢った当初から頭にこびり付いて離れぬある思考が、激しい警鐘を郁人の心に打ち鳴らしている所為に他ならなかった。
もしもこの予感めいた直感が正しければ一刻の猶予もならない。だが、こうして安らかな寝息を立てて眠る雪乃の平穏な寝顔を見ていると、そんな思考は馬鹿馬鹿しくなってくるのだった。
郁人は幾度も幾度も携帯を開いてはアンテナの本数を数えて、ポケットの中の名刺の存在を確かめるように指で弄ぶ。
幾許(いくばく)かの時間が流れただろうか。ついに郁人は雪乃の肩を軽くゆすってみることにした。
気持ちよさげに眠っている所を揺り起こすのは気が引けたが、さすがに気になった。しかし返事があろうはずもなく、雪乃は昏々と眠りつづけるのだった。
郁人は事ここに至って決意した。
ポケットから美雪の名刺を取り出して携帯に連絡を入れてみた。三度のコールで美雪が電話に出た。
「はい、もしもし?」
電話に出た声は美雪に間違いなかったが、心持ち声には硬さがあった。恐らくは見知らぬ番号からのコールだったので怪訝に思ったのだろう。
郁人は「お忙しい所すみません。お嬢さんをツーリングに誘った鳴川と申しますが……」と切り出した。鳴川という姓に反応したのではなく、恐らくツーリングに誘ったという言葉に「ああ」という声を上げたのだろう。
「娘が厄介をかけていますね」
美雪はおっとりとした口調で、しかし総てを見透かしたようにそう言った。勿論全面的に肯定するわけにもいかず、郁人は
「いえいえ、ちっとも」
と思わず答えてしまった。
「ただ、ちょっと疲れてしまったのか、今は眠ってます」
そう、ただ眠っているだけ……そう、郁人は言った。
「眠ってからどれくらいになりますか?」
美雪の声にはあらかじめ予測されたもののように抑揚がなく、ただ事実を確認するような事務的な響きがあった。
郁人は携帯を持ち替えて腕時計を確認する。雪乃が寝入ってからちょうど30分が経過していた。
「30分ってところでしょうか」
美雪の声は「そうですか」と消え入りそうなほど小さく、力がなかった。
「車をそちらに迎えにやります。鳴川さんは今どちらに?」
「清里高原、美し森です。森林浴をすると気持ちいいんじゃないかと思って……」
しばらく黙考していた美雪は「それでは」と二の句を継いだ。
「恐れ入りますが、その娘(こ)を最寄の車道まで運んでやっていただけませんか? すぐに迎えの車を手配いたしますので」
郁人はこの状況が芳しくないことに気づき始めていた。それもかなりクリティカルな状態らしい。恐る恐る郁人は
「もしかして雪乃さんの体は……」
そう言いかけた郁人を美雪が止めた。
「ごめんなさい。今は一刻を争います。雪乃のことについては後ほどゆっくりとお話しますので、今は至急雪乃を車道まで運んでやって欲しいのです」
意識的にゆっくりと喋っているのは、恐らく郁人がパニックなどを起こさぬように気遣ってのものだろう。
ともかく美雪の様子から察するに急いだ方がよさそうだった。
「黒いバンをそちらにやります。清里高原の駅であらかじめ待たせてあるので数分でそちらにつくはずです」
まさか車まで待たせてあるとは周到すぎる。どう考えてもこの事態を予測していたとしか思えなかったが、何より今は雪乃を優先すべきである。
「わかりました」
そう答えて郁人は電話を切った。
『落ち着け、落ち着け――』
そのまじないは或いは口に出ていたかも知れない。郁人は自分に何度も言い聞かせながら雪乃をおぶった。雪乃のデイバッグを忘れぬように持って、足を滑らさぬように注意深く、出来うる限りの速度で走り始めた。
郁人が道に出るとすぐに指定された車が路肩に停まっているのを確認した。それはまるで不幸を告げる使者のごとく不気味な威容を曝(さら)け出しているかに見えた。
車内から2人の姿を確認したのだろう。
3人の白衣をつけた男たちが車から降りた。その行動は迅速でいかにも手馴れていたが、医者という感じはしなかった。
2人はバンの後部ドアを開けてストレッチャーを用意し、1人は郁人の元へと駆け寄った。郁人の手からデイバッグを受け取り、「お嬢様をそのままストレッチャーに!」と指示する。
郁人がストレッチャーまで走るや、待ち受けた2人が雪乃を実に手際よくストレッチャーへ寝かしつけて、ストレッチャーとともに後部座席へそのまま吸い込まれた。
「これから美杉病院へ戻ります。よろしければ後ほどおいでください」
デイバッグを持った男が郁人にそう言って一礼し、慌しく運転席へ収まった。バンは赤色灯こそ備えていなかったが、派手なスキール音を立てて緊急車両顔負けの速度で飛び出した。
郁人は暴風雨にでも遭ったかのようにその様子を見ていたが、やがて我に返って愛機を探した。一人乗りなら高速が使える。
郁人は駆け出した。祈るような思いだった。
大急ぎで駐車してあるM900の所へ戻った郁人は、焦る気持ちを抑えてバイクをスタートさせた。
郁人が美杉病院に着く頃には日は既に傾き、世界は緋色に侵食され始めていた。
高速道路で黒いバンに追いついた郁人は、そのまま美杉病院まで黒いバンに付き従うように走った。
玄関口を通り過ぎて救急用の出入り口へと回ったバンが、目的地を得て静かに停車する。
病院のドアとバンの後部ドアが開くのが同時だった。
無駄のないテキパキとした医師達の動きを郁人はただ傍観することしかできなかった。その領域は郁人の立ち入るべき場所ではなかった。
郁人はM900を邪魔にならないところに停め、雪乃の後を追おうと通用口に向かった。と、そこに見知った顔を見つけて足を止めた。
雪乃の母親、美雪が郁人を見つけて一礼した。
郁人は頭を下げたが、何と言ってよいかわからずにただ沈痛な面持ちで眉間に深い皺を作っただけであった。
美雪はゆっくりとした足取りで郁人のもとに歩み寄ると、「ありがとうございました」ともう一度深々と頭を垂れた。
「鳴川さんのおかげで娘も大事に至らなかったようです。このまま安静にしていればすぐに意識も回復するでしょう。本当に助かりました」
「…いえ……」
郁人にとってはまるで見当違いの感謝の言葉は、細やかな砂のように郁人の心に入り込んでぎしぎしと音を立てている。少なくとも雪乃の体調を慮(おもんぱか)ってやれなかった点については申し開きのしようもなかった。
「ぼくがお嬢さんの体調に気づいてあげられなかったばっかりに……」
そう言って項垂(うなだ)れる郁人に美雪は「どうぞこちらへ」と手招きした。
病棟へと無言で入っていった美雪のあとを、やはり郁人は無言でついて行った。
消毒液の臭いがひどく鼻につく気がした。僅かに効いた冷房がやけに肌寒かった。
程なく二人はエレベーターホールに出た。△ボタンを押した美雪は何から話そうかと思案しているように押し黙ったままだったが、郁人は無理に口を挟むことはしなかった。
いや、出来なかったと言った方が正しいかもしれない。
まもなく到着したエレベーターに乗り込み8階をプッシュすると、エレベーターの扉は閉じられ、軽いショックとともに上昇を開始した。
僅か8階までの時間が異様に長かった。無辺の黝(かぐろ)い闇の最下(いやした)へと吸い込まれるように、二人の肩に重力が圧(の)し掛かった。
不意に重力は消え失せ、ごこっと微かな音と共に扉が開いた。
エレベーターホールからまっすぐ伸びる廊下に人気(ひとけ)はなかった。
美雪にとってここは慣れた場所なのだろう。
純白に塗りこめられた廊下を美雪は歩き始め、郁人もそれについていった。二人の立てる足音以外には音は聞こえない。ただ跫然(きょうぜん)と四つの靴音が響いた。
美雪の足が止まった。郁人は振り仰いで部屋のネームプレートを見た。
そこには「水無瀬雪乃様」と彫り込まれていたのだった。
扉を開けると中は個室だった。
部屋の中にはベッドが1基、簡単なテーブルと椅子、TVなども備えられていた。清潔そのものの真っ白な病室には既に先客がいた。
一目見ただけでブランド品と思しきスーツに身を包んだ、品のよさそうな40代くらいの長身痩躯の紳士である。
先程まで窓際から一望できる森を見下ろしていた男性は郁人を瞥見(べっけん)して軽く会釈する。郁人もつられて会釈したが、その身形(みなり)から流石にピンとくるものがあった。
恐らくは雪乃の父親だろう。許可は得ていたとはいえ、少なくとも出先で雪乃が倒れたのに郁人が無関係であるとは思ってもらえまい。
「鳴川さん……ですか?」
僅かに錆を含んだ穏やかな声が、主のいない空虚(うつろ)な病室に響いた。
その声には些かも憤怒の色は見えなかったが、雪乃をツーリングに誘った上に体調の変化にも気づかずこのような事態を招いたのは他ならぬ郁人の責任だった。場合によっては2~3発殴られることも辞さない覚悟で郁人は「はい」と答えた。
雪乃の父親は真っ直ぐ郁人を見据えて、深く頭を下げた。
「有難うございます。娘がご迷惑をおかけした様で」
若いからといって馬鹿にしたところのない、慇懃な態度であった。僅かに戸惑いながら郁人も頭を下げる。
「いえ、もっと早くお嬢さんの体調に気づいてあげられれば或いはこんな……。無理をさせてしまったようでこちらこそ申し訳ありません」
「いえいえ。あれも分かって無理をしていたのです。楽しみにしていましたから」
そう言った雪乃の父親の眸は淋しげであった。
「いい思い出になったと思います。あなたには感謝の言葉もない」
「思い出……ですか?」
郁人は聞き返す。その返答は遂になかった。
「……貴方には一言お礼だけ申し上げたかった。それに今日の事については鳴川さんが気に病む必要はありませんから……」
そう言って雪乃の父親は郁人の元へと歩を進めた。
「そして出来れば、もうここにはいらっしゃらないで頂きたい。私からのお願いです」
郁人の前で一礼して、雪乃の父親は病室から出て行った。
一言も発することが出来ず、郁人は徒(いたずら)にその後姿を見送った。
最早掛けるべき言葉すらなく、たとえ呼び止めたとしてもその背中は生半な言葉を冷然と拒絶するだろう。
『もうここには来ないで欲しい――』
その言葉の意味が理解できぬほど郁人は幼くなかったが、だからといってあっさりと肯んじることも出来ない相談だった。
何故なら郁人は雪乃の見せた深淵を覗き込んでしまったから。
「ごめんなさいね」
それまで押し黙っていた美雪が、その様子を見てか郁人に言った。
「主人はああいう言い方しか出来ない不器用な人ですけれど、貴方と娘のことを思ってのことなんです。怒ったり気分を害したりしている訳ではありませんのでどうかお気を悪くされないで下さい」
「お嬢さん……雪乃さんは……」
郁人は口を開いたが、そこから先を言い継ぐことが出来なかった。これ以上家族の事情に首を突っ込むことが躊躇(ためら)われたのもある。何よりその答えを聞くのが純粋に怖かった。
重い沈黙が二人に圧し掛かった。
紅に染まった世界の只中で、無窮の静寂(しじま)が総ての音を奪い去ったかのようだった。
「……お約束――でしたわね」
「は?」
「電話で申し上げました。『後ほどゆっくりとお話します』と」
「あ……」
そう言われれば確かに携帯で連絡を入れたときにそう言ったやり取りをした記憶がある。だが、郁人はもう無理にその言葉を聞くつもりはなかった。その先を聞いてしまうともう後には引けないかも知れないと漠然と思った。その言葉を聞いてなお雪乃と今まで通り接する自信もなかった。
郁人は唇を噛んだ。
だからといって見て見ぬ振りをすることも、今までの事をなかったことにも出来そうになかった。だからこそ郁人は訊いた。
「雪乃さんは……?」
美雪はその真意を汲み取るように郁人の眸をじっと見て、ゆっくりと、消え入りそうな程に幽(かす)かな声で言った。
「…娘は……脳腫瘍なんです」
2.
「どうしたんスか?」
敬一郎に声を掛けられて郁人は、はっと声の主に目を向けた。
「なんかボ――っとしててらしくないっス。悩みっスか? 夜の悩みだと俺では聞いてあげられないっスけど」
敬一郎の軽口にやっとといった感じで苦笑を浮かべた。
暮れなずむ病室を訪れていた郁人は、だがこのところ心ここにあらず、いつも何かを考えているように沈思していた。
「いや、なんでもないさ」
そう言って郁人はまた深く考え込むのであった。
昨日の美雪の言葉が頭から離れなかった。
「星細胞腫」
それは聞きなれない名前だった。
神経膠腫、髄芽腫、上衣腫……次から次へと挙げられる腫瘍の名前にそもそも脳腫瘍の種類がこれほどあることすら郁人は知らなかった。
5~14歳程度の小児に発生する星細胞腫は特に『幼若性毛髪様星細胞腫』とも呼ばれ、病理上きわめて良性であるとされている。
手術さえ行い、腫瘍の全摘出が可能であれば5年生存率は80%以上ともいわれ、完治すらも夢ではない。
だが、雪乃の両親に医者の告げた言葉は非情な現実であった。
「一部に浸潤が見られます」
脳組織に腫瘍が食い込み、手術での全摘出が非常に困難であること、発生部位が極めて危険な場所で、メスを入れることが躊躇われることなどを説明した。
「放置すれば余命は1年から2年――」
美雪は真っ直ぐな瞳で郁人に言った。
「腫瘍の場所が命に関わる部位の為、手術をしても成功率は10%を切るそうです」
もう、涙は涸れ尽くしていた。
成功率10%の大博打か、緩やかな死か――。その選択はあまりにも無慈悲で冷酷だった。今はまだ薬物治療が奏功して症状は軽微だが、もう半年もすれば運動障害が起こって歩くことすら困難になるだろう。
症状が重くなれば放射線治療も余儀なくされ、副作用でボロボロになりながら花すら咲かせることも出来ずに蕾のような少女はこの白い檻の中でその生を終えるのだろう。
郁人は総てを喪(うしな)ったかのような、美雪の自嘲めいた微笑をただ唇を噛んで見ているしか出来なかった。
「鳴川さんってば」
何度も何度も敬一郎は呼びかけたのだか、郁人はずっと黙ったまま時間の果てるまで思考をループさせるのであった。
面会時間の終了を看護士が告げ、肝心の敬一郎に「それじゃ」とだけ言って郁人は病室を後にした。
敬一郎が大きなため息をついたのも無理のないことだ。
郁人が駐輪場につくと、雪乃はやっぱり駐輪場に降りてきていた。いつものようにたっぷりとしたTシャツに黒い膝丈のスパッツというくだけた格好で、墨を流したような黒髪を横に結わえて。
ドゥカティの前に座り込んでいた雪乃は郁人を見つけると一瞬気まずそうな顔をしたが、すぐに弾かれたように立ち上がっていつもの笑顔で深々とお辞儀をした。
「こんにちは。それと昨日はごめんなさい」
「……もういいのかい?」
郁人は雪乃の元に歩み寄りながら、努めて平静を装って訊いた。
雪乃は小さくガッツポーズをして、「はい!」と答えた。
「ならいいけどさ」
郁人は苦笑した。
「けれど吃驚したよ。突然眠りこけて起きないんだから。単車で寝てる君を連れて帰るわけにいかないから、結局美雪さんに連絡しちゃったよ」
雪乃は小さくあははと笑って、
「ホント、せっかく連れて行ってもらったのに何やってんだろ? 一昨日嬉しくて眠れなかったからかなぁ??」
それから雪乃は再び座り込んだ。そろえた膝にちょこんとあごを乗せて
「ホント、何やってんだろな……」
と、呟いた。
郁人はしばらくその様子を見ていたが、思い至ったように雪乃の隣に腰をおろして、雪乃の頭をぐしゃぐしゃと撫でた。
「わ!?」
驚いたように雪乃が郁人を見ると、郁人はニカッと笑った。
「いいさ。雪乃ちゃんの気持ちよさそうな寝顔も見られたし……」
「え? わ??」
耳まで真っ赤にしてあたふたと何かを言おうとする雪乃に、郁人は嗜虐心の見え隠れする微笑を湛えて、
「こう、涎がついーっとな……」
「わわわっ!」
今さら雪乃は口の周りを拭う仕草をしたが、郁人の笑いを買っただけだった。
「ははは、冗談! 冗談だよ。可愛らしい寝顔だったさ」
「あの、…その……」
それでも顔を紅に染めて、おろおろと目を泳がせている雪乃に郁人はやさしく言った。
「またツーリングに行こう。時間はたっぷりあるさ」
じっと郁人の眸を見た雪乃もいつのまにか観念したようにふっと目元を緩ませた。
「そうですね。また行きたいです」
雪乃はそう言って笑ったが、郁人はその笑顔に胸の痛みを感じて「ああ」とだけ答えた。
雪乃は、ぽんと手を叩いて
「そだ。来週の日曜日はどうですか?? 実は行ってみたいところがありまして」
郁人の苦衷を知ってか知らずか、雪乃は上目遣いで哀願するように言った。
「行ってみたい所?」
「はい!」
雪乃は立ち上がるとくるりとその場で回った。長い射干玉(ぬばたま)の黒髪がふわりと雪乃の周囲を踊った。
「私、海って行った事ないんですよね。ずっとずっと行きたいって思ってたんですよ」
屈託のない笑顔でそう言った雪乃に郁人は「そうだなぁ」と考える仕草を見せた。もしも雪乃の病気のことを知っていなければ悩む事などなかっただろう。
「うん、日曜日のスケジュールを調べておくよ。明日にでも返事をしよう」
「やたっ!」
喜色を満面に浮かべて雪乃は駆け出した。
「じゃあ、お母さんに行っていいか訊いて来ますね?」
郁人が声をかける隙もなく雪乃は病棟に向かって走って、何でもないところで躓(つまづ)いて転んだ。
「……ドジッ娘?」
彼方でアスファルトの上に座り込んで、てへりと舌を出している雪乃を苦笑まじりに見守っていた郁人は勿論真実に気づいている。
腫瘍に運動中枢を冒され始めているのだ。
雪乃の姿が見えなくなってから郁人は「くそっ」と小さく毒づいた。
夜の帳(とばり)が打ち払われようとしていた。
夜闇に包まれた窓外は徐々に色づき、目覚めた雀がひっきりなしに囀り始めていた。
フローリングのシンプルな部屋に置かれた簡素なベッドの上で郁人はまんじりともできずにただ一点の虚空を眺めていた。
雪乃は海を見たいと言った。
雪乃に連れて来られた美雪も賛同した。海開きもしているし、いい季節だからと美雪は愉しそうに言った。そして悪戯っぽく雪乃に耳打ちして『新しい水着でも買って鳴川さんを悩殺して差し上げれば?』とまで焚き付けた。
どう見ても中学生か、下手をすれば小学生にも見える雪乃のカラダで郁人が悩殺されるかどうかはかなり微妙だが、当の雪乃はまんざらでもないらしく真っ赤になりながらも楽しそうに日曜日の事をあれやこれやと話題にするのだった。
そんな雪乃の姿を郁人はやるかたない気持ちで、しかしそんな内心を露ほども顔には出さずに見ていた。
万に一つの可能性を掴む為には手術が不可欠だ――雪乃が倒れたあの日、美雪は二人きりの病室で言った。放射線治療や化学治療には限界があって、可及的速やかに措置が必要だと。だが、それに伴うリスクは小さくはない。手術そのものの成功率が10%以下である上に、例え成功したとしても予後については未知数。
そもそも星細胞腫という腫瘍は悪性度が様々で、悪性度の低いうちに手術で除去できれば予後は良い。病理上『良性』に分類されるのはその為だ。だが、手術で取りきるのが難しく、臨床上は『極めて悪性』とされている。本来一分一秒すら無為にはできない所以であった。
そしておそらく雪乃は気づいている。
このまま放置すればどうなるか――。
それを鑑みて、なお手術を拒んだのだとしたらそれが雪乃の価値観に相違なかっただろうし、例え医者であっても成功率とその結果を秤にかけた時、手術を無理に推す事ができなかったのだろう。
雪乃の両親も恐らくあらゆる事を考え尽くして、雪乃のクオリティ・オブ・ライフ……長きよりも豊かな人生を選択したのだろう。
郁人の辿り着いた解答は、それでも郁人を納得させはしなかった。
そんな真綿で首を締められるような、緩やかに死に転がり落ちる人生など赦せなかった。
そして郁人は原点に立ち戻る。
雪乃の人生は雪乃のものなのだ。彼女の運命は彼女自身が掴み取らねばならないのだ。
郁人がタイムカードを押したとき、既に始業時間から10分が経過していた。
その日の郁人はまるで精彩に欠け、くだらないミスを重ねては玲子に叱責され、遂には見かねたように玲子は郁人を無人の会議室に呼び出した。郁人が入社して3年、それは初めてのことだった。
呼び出された郁人は無論その理由を知っている。
鉄の女とも、夜叉姫とも綽名(あだな)され畏れられるあの高階玲子から呼び出しを食らった郁人は勿論相応の罰を予想しながら会議室に入室した。
室内には玲子が不機嫌そうな面持ちで郁人を待っていた。
「鳴川君?」
郁人はその言葉だけで飛び上がりそうになった。
だが、その後に続いた言葉は意外なものだったのだ。
「一緒にお昼に行きましょう」
玲子は社員食堂ではなく、外へ郁人を連れ出した。玲子が先頭になって入った店はどう見てもかなり高級そうなフレンチレストランで、間違っても彼等の知り合いがお昼に立ち寄りそうな店ではなかった。それでも玲子はよく来るらしく、ギャルソンに手早くワインとメーンの料理を伝えて、不慣れな郁人に席を促した。
「すみません」
席に就いた郁人はやっとの思いで玲子に謝った。いろんな意味をこめての謝罪だった。
玲子はじっと郁人を見て、「何があったのか……話してもらえるかしら?」と訊いた。その口調は社に居る時のそれではなかった。包み込むような慈愛に満ちていた。
食前酒が運ばれ、少し気が落ち着いたのか郁人はその胸に溜め込んでいたものを余さず話した上で、玲子ならばどう対処したものかと意見を仰いだ。
プルミエール(軽いオードブル)、オードブルと続いてアントレ(メーンディッシュ)が供される頃、言葉少なに郁人の言葉に耳を傾けていた玲子は首を振った。
「そこで大事なのは私の意見ではないでしょう。キミがどう感じて、どう思ったか。あの子がその思いをどう受け止めるかが大事なのではないかしら?」
玲子は鮮やかに盛り付けられた薄切りの鴨のローストを優美な仕草で口へ運んだ。
それができれば苦労はしない…と言おうとして玲子に止められた。
「どんな結果が待ってるかなんて誰にもわからない。どんな選択肢を選んで行動したにせよ、キミはその結果を受け入れるしかない……例え最悪の結果が待っていたとしても」
玲子の瞳は明滅する燭台の光を跳ね返してゆらゆらと幻想的に揺らめいていた。幻のように光たゆたうその奥はしかし峻厳にして酷薄ですらあった。
「責任がもてないというのなら、傍観者でいなさい。あの娘はキミの奥さんでも恋人でも何でもない。仮にここでキミが傍観を決め込んだとしても誰もキミを責めたりはしない。ただ……」
玲子がそこまで言った時、郁人は静かにナフキンをテーブルに置いた。その表情は冴え冴えとして、何かつかえが取れたかのような清々しさに満ちていた。
「やはりご相談差し上げてよかった」
郁人はそう言って、深々と頭を下げたのだった。
3.
その日、郁人がタイムカードを押して社屋の外に出ると其処は既に薄暮に包まれていた。森に近いここには都会のようなむっとする熱気はない。日中汗ばむほど暑くとも、日が落ちると心地よい風がさぁっと吹き抜けていくのだった。
本格的な夏はすぐそこだった。
「海かぁ……」
郁人は懐かしむようにそう独りごちた。そういえば最後に海に行ったのは何時だったか。
うっすらと苦笑を頬に貼り付けて、郁人はドゥカティM900を駐輪場から引っ張り出した。そしていつもの日課となりつつある美杉病院へとM900を走らせるのだった。
郁人がまもなく美杉病院に到着し単車を停めようとしていると、ぱたぱたとスニーカーの音がして雪乃がやってきた。どうやら待ちきれずにこの周辺をうろうろとしていたようだ。
いつものようにたっぷりとしたTシャツと黒い膝丈のスパッツで、長い黒髪を横結いにして。
「あ、あの! ど……どうでした? 行けそうですか?」
挨拶も抜きにヘルメットを被ったままの郁人に雪乃は訊いた。まるで子犬のような落ち着きのなさに郁人は苦笑する。
ヘルメットを脱いだ郁人は
「とりあえず今晩は」
と、努めてゆっくりと挨拶する。雪乃は慌てて
「あ、そっ……そうでしたっ! こんばんわです!」
早く返事を聞きたくてそわそわしている雪乃を見ながら郁人は「今日は暑いねぇ」と殊更はぐらかすように言って、自動販売機に向かった。
雪乃は郁人の周りをくるくると廻りながら、郁人の答えを待った。
郁人はアイスコーヒーとミネラルウォーターを買うと、ミネラルウォーターを雪乃に渡した。
そして徐(おもむろ)に
「え~っと、日曜日だったね」
と、ゆっくり口を開いた。
雪乃はどこかのクイズ番組に出てきそうな、ファイナルアンサーを口にした後の解答者のように期待と不安を顕わにした面持ちで郁人の次の言葉を待った。
郁人は缶コーヒーのプルタブを起こして一口つけた。雪乃は受け取ったミネラルウォーターのペットボトルを握り締めながらじっと郁人を見ていた。
「とりあえず、日曜日は空けておくよ。海に行こうか」
郁人がそう言うのと歓声を上げて雪乃が飛び上がるのが同じタイミングだった。
目尻に涙まで浮かべて喜ぶ雪乃を見て郁人は少しだけ胸の痛みを感じたが、それでも郁人は心に決めてきたのだ。
「だけれどそれは今度の日曜日じゃあない。その日曜日が何時になるかはわからない」
雪乃の動きはぱたりと止まった。
「だって雪乃ちゃんはやる事があると思うから」
一瞬何がなんだか訳が分からないといった表情を見せた雪乃だったが、すぐに猛烈に抗弁した。
「そんな! そんなものはないですよ!」
必死の形相で雪乃は食い下がったが郁人は雪乃の目を真正面に見ながら言った。
「俺は君の最期の思い出になんてなりたくない」
それは16歳の少女にとってあまりにも残酷な一言だったに違いない。
雪乃はその場にあらゆる憑物が落ちたかのように立ち尽くした。
「そ…それは……」
雪乃の真っ青な唇からようやくまろび出た言葉は、可哀想なほどに震えていた。
郁人の胸は砕け散りそうなほどに痛んだ。あまりの痛みに目の奥がチカチカして無性に喉が乾く。それでも、血を吐いてでも言いたい言葉があった。
「俺は……」
何時からだったのだろう、と郁人は自問する。
「こんな結末なんか……」
この少女の笑顔を見ていたいと願った。そしてこの少女から笑顔を奪い去る、理不尽で不条理で不公正な運命を呪った。
「欲しくない」
雪乃はペットボトルをぎゅっと両手で握り締めたまま立っていた。その小さな身体は更に小さく見えた。
郁人は今更ながらその言葉のもたらした結果に烈しい自責と後悔を感じた。
雪乃には笑っていて欲しいのに何故こんな言葉を吐いて雪乃を悲しませる必要があろうか。
精神を木っ端微塵に粉砕し、正気すらも保てぬほどの死の恐怖から逃れて魂の安寧を渇望する幼い少女に、尚も死と向き合って闘えと言う事の何と言う残酷さよ。
分かっていた。 否、解っている。
「やっぱり、聞いていたんですね? 私の病気のこと……」
雪乃の声は何処か虚ろで、言葉には存在感がなかった。
郁人は開けてはならないパンドラの函に触れてしまった事に後悔を感じながらゆっくりと首肯した。恐らく雪乃も十分に予想しえたのだろう。澱のように倦み溜まった肺の中の空気を吐き出した。
「分かっていたんです。手術が成功すればもしかしたら治るかも知れないって。でも……」
郁人も理解していた。
成功率10%――。失敗すれば命の保証もない大博打に我が身を晒す勇気の持てる人間など多くはない。郁人は自分のエゴを雪乃に押し付けただけなのかもしれないのだ。
郁人の拳は握られた。関節が白く浮き上がり、指は鬱血して真っ赤になっていた。
『やっぱりもういいよ』
そう言えたらどれほど楽になれるだろう。『今度の日曜に海に行こう』と言えば少なくともこれ以上雪乃の心は苛まれる事はない。上辺で笑えていられるならば今の郁人の心は救われるだろう。
だがそのもたらす結果を思う時、郁人は断固として貫かねばならない意志がある。人は何時か土に還るものだが、今確かにある可能性を放棄する事は郁人にはどうしても赦せなかった。
「……余計なお世話かもしれない。もしこれで上手くいかなかったら俺は人殺しだ」
郁人はゆっくりと、ゆっくりと言葉を確かめるように言った。
「それでも俺は、諦めないで欲しいと思っている。可能性に目を瞑(つむ)った事を後悔して欲しくないし、……俺も…その……後悔したくない」
郁人はふいっと眼を逸らして続けた。
「取り返しのつかないところまできて『あの時、引きずってでも手術を受けさせておけばよかった』……なんて思いたくない」
思いを紡ぐかのように、祈るように、囁くように、郁人は小さく言った。
「あーあ……」
雪乃は鼻声で嘆息した。
「やっぱり私ってダメだなあ……」
雪乃が空を仰いで呟いた言葉は、森から吹き付けた風に運ばれて霧消した。
「分かってたんですよ? これでも。このままじゃダメだって」
悪戯っぽく笑って小さく頭をこつんと叩いた仕草がいじらしかった。
「ホントにダメだなぁ……」
そう言って落ち込む雪乃に郁人は掛ける言葉も見つけられずに、ただ黙って見つめるよりなかった。
「この切り立った谷の向こうには楽園が見えているというのに、谷を飛び越える勇気はないんです。そしてこちら側の陸地はどんどん沈下して、最後には海に沈んでしまうのも分かっているんです。どうせ人はいつか死ぬのだから……そう自分に言い聞かせて、人より短い人生を駆け足で生きていけばいい……。人の一生の良し悪しは、生きた時間の長さとは関係ないと無理やり自分を納得させて――」
ああ、この少女は一体幾つの眠れぬ闇黒(あんこく)の夜を過ごしたのだろうか。
如何なる精神力が、刻一刻と迫る死の恐怖に抗い続けたというのだろう。
郁人は唇を噛んだ。
『人は生まれながらにして皆平等である』
そんな世迷言(よまいごと)を唱えるような輩(やから)がもし今ここにいたならば、郁人は問答無用でそいつをブッ飛ばしている事だろう。もしそうならばこの少女が一体何をしたというのだろうか。この地獄のような罰を受けねばならぬ罪を犯したとでも言うのだろうか。
不条理だった。不公平だった。理不尽だった。
この世に神がいるならば、なんと気まぐれで無慈悲なことか。
なのに少女はそれさえも泰然と受け入れて、不平ひとつもらさずに笑顔を見せていた。
「……でも、もうダメなんですよね」
雪乃は寂しげに薄く笑った。その微笑みは郁人の心を寒くさせた。黒い影が張り付いたような輝きのない、決定的に何かを失った笑顔。
――違う――
郁人は奥歯をぎりりと鳴らした。
雪乃にこんな顔をさせるために自分はこんな思いをしたのではない。
「俺は……」
「――どうしてくれるんですか?」
郁人の言葉が自らを失って彷徨うように流れると、それを断ち切るように雪乃の声が重なった。それはまるで断罪するように、叱責するように、あるいは駄々をこねる幼い少女の怨嗟のようにも聞こえた。
郁人は、はっと顔を上げて雪乃を見た。
少女は一寸困ったような哀しい微笑を浮かべていた。
「私はもう外の世界を知ってしまった。何年も何年も閉じ込められていた真っ白な檻の中からただ想像するだけだった外の世界へ、鳴川さんは私を連れ出してしまった。消毒液の匂いしかしない病室では想像する事もできなかった風の匂いを、鳴川さんは私に教えてしまった。……ううん、正確にはあの時……病室でただ天井を見ていることしかできなかったあの時に聞こえたあの音が、私を自由の天地に導いてしまった――。そう、いつかこのがらんどうの病室から私を連れ出してくれるような……そんな気がしたんです」
雪乃の言葉が郁人には痛かった。第三者が冷静に聞けば、それは利己的な責任転嫁の言葉に聞こえるかもしれない。
それでも雪乃の言葉は鋭利な刃物と化して郁人の胸を抉(えぐ)り、切り刻むのだ。
「あの時まで私はもう何時死んでもよかった。この世に未練なんてなかった。友達もいない、やりたい事もない、何年も何年も体が弱くてただ病室でぼんやり過ごすしかできない私に生きてる価値なんてなかった。なのに!」
雪乃の言葉は次第に激情を孕んで、何時しか大粒の涙が雪乃の目尻に光る珠を形作った。
荒れ狂う暴風のような感情の波が突然消失した。
「……もうダメなんですよ。だって、私はもう知ってしまったから。世界はこんなに綺麗で素敵で私はまだまだ何にも知らなくて、やりたい事がどんどん溢れてきて……」
血のように紅かった夕陽は森の向こうに姿を消し、青紫色の薄闇が天蓋を支配しつつある中で雪乃は立ち尽くしていた。まるで世界にただ一人取り残されたかのように。
雪乃の頬を一条の涙が滑り落ちた。
「……私は……まだ死にたくない――」
どうしようもない絶望の中で慟哭する魂が搾り出す、嗚咽にも似た希望(ねがい)の言葉が、総ての感情の消え失せた雪乃の口から零れ落ちた。
「このまま放っておくと冬には歩行に障害が出るようになるそうです」
脳の運動を司る部分にできた腫瘍は雪乃を蝕み、来春から来夏にかけて寝たきりになるだろう。そして――。
「私、行ってみたいところがいっぱいあるんですよ。春のお花畑とか、夏の海とか、紅葉狩りにも行ってみたい――。まだまだ見たいものや、やってみたい事が沢山あるんです。今、私のなかでその気持ちがすごく大きくなってて、行って見るまで死にたくないとまで思ってる……」
雪乃は地面を見ながら、独白のように吐露した。その横顔は郁人が初めて見るものだった。
不安げに揺れるその表情は最後の逡巡だろうか。
郁人ができる事は?
僅かに考えたが、郁人ができることなど最初から決まりきっていた。そう、雪乃の背をそっと押してやる事だけなのだ。
「俺も見せたいな。6月頃に見られる北海道のラベンダーなんて最高だぜ」
郁人は目を閉じた。
かつて一度行った北海道の情景は目を閉じればいつでも脳裏に浮かんだ。その地平の彼方まで続く平原を、陽光に煌めく深く澄んだ湖と馥郁(ふくいく)と茂る森を、夏でも頂(いただき)に雪を冠する峻険な山々を、うねる野に聳(そび)えるポプラの木々を、そして見渡す限り目も絢(あや)な薄紫色に染まったラベンダーの丘を雪乃に見せてやりたかった。
「私も……見られるなら見てみたい……ううん、私は見たい! でないときっと私は後悔する。自分を騙して、やりたい事や見たいものから目を逸らして、それで心から満足できるなんてもう思えない。私は…、わたしは……」
涙に頬を濡らしながら、雪乃の表情はむしろ晴れやかですらあった。
「わたしは、生きたい――」
それはほんのささやかな願い。
雪乃にとってそれは彼方まで続く無明(むみょう)の闇の中にある、儚(はかな)くも朧(おぼろ)な実体を持たない夢のような希望。
それでも雪乃はその夢に輝きを見た。その夢に輝きを与えたのは他ならぬ郁人とドゥカティだった。
郁人は今、一人の人間の人生を変えたことを知った。吉と出るか凶と出るかは神ならざる身には窺い知れぬ事だったが、廻り始めた運命の輪を最早押とどめる事はできなかった。
郁人にできることは、決断を下した雪乃に光あれと祈ること、そして自らの選択の結果の総てを受け入れることだけなのだった。
「待っている――」
郁人は言った。
「いつの日か、君を乗せてツーリングに行ける日がくるのを、君と一緒に海に行ける日がくるのを俺は待っている」
郁人はようやく微笑んだのだった。