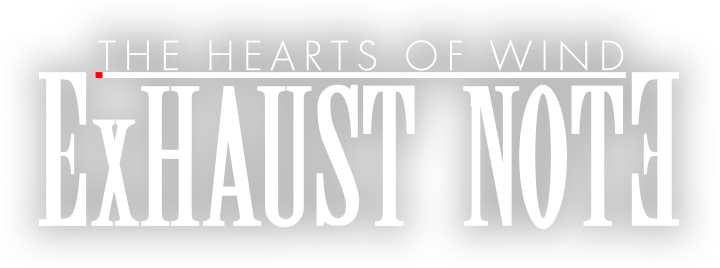novels
遺産相続
桜も散り終えた暖かな春の昼下がりは、吹き抜ける風すらも優しかった。
春の風は命を運んでいるからこそ暖かく、そして優しいのかも知れなかった。
春は命の季節。
生けるものと、そして死せるものの季節。
なれば去りゆくものを送る言葉も、新たな出逢いの為に欠かさざるものなのかも知れなかった。
閑静な住宅街のひときわ大きな屋敷には、このあたりでも有数の郷士、匂坂源一郎(さきさかげんいちろう)が静かに一人余生を過ごしていた。
メイドを何人か住まわせていたが、血縁のものは住んでいない。
バブル時代には何かと派手な噂も聞こえたが、今となっては立ち寄るものとてない。もとよりこの老人にはどこか人を寄せつけぬようなところがあって、ここ数年老人は屋敷から外へ出ることもなくなった。
近隣の住人は源一郎が元気にしているのかさえ伺い知ることはなかったし、また偏屈で頑固な老人という風評もあって気にしようとする者も多くはなかった。
だから今、源一郎翁が死病の床に就いているとも、だれ一人見舞うものもなく、また縁者がやってくるようなこともなかった。
源一郎は自らの運命を悟っていたのだろうか。
豪奢なベッドに点滴を受けながら横になっていた源一郎は、桜の花が舞う様子を窓外に眺めながら付添の三人のメイドのうちの一人に封書の束を渡した。
部屋にいたメイド全員の顔色がさっと変わっても源一郎は最早動じず、ゆっくりとメイド達へと視線を移した。
「今までよく尽くしてくれたな……礼を言う」
労るように告げたその声はか細く、ひゅうひゅうと息苦しそうな呼吸に紛れていたが、その場にいたメイドは全身 全霊を傾けて聞いていた。一言半句とて聞き漏らさぬように。
「永い人生じゃったが、それも終わりに近づいた様じゃ」
源一郎は事実を淡々と口にしたが、メイド達は最後の務めとこぼれ落ちそうになる涙を一様にこらえていた。
源一郎の瞳は既に白濁しており、何も見えぬようだったが「そんな顔をするんじゃあない」と小さく笑った。
「その封筒がお前達最後の仕事になろう……。我が数少ない縁者である娘夫婦への遺言じゃ。すまんがよろしく頼む……」
そう言って源一郎はひと呼吸した。
「あれほどいたメイド達も今や三人……。じゃがお前達のおかげで儂は何不自由なく過ごせた。その封筒のうちの一部はお前達への感謝の気持ちじゃ」
とうとうメイド達の瞳から涙がこぼれ落ちたが、源一郎は気付かないようだった。源一郎は疲れたように目を閉じていた。
息をふうっと吐き出すと、
「いろいろあったが、……今となっては総てが懐かしい……。よき人生であったと…思うておる」
満足そうな笑みを浮かべながら源一郎は、そう独語すると
「下がってくれてよいぞ……。儂もそろそろ休むでな」
そう言うや源一郎は深い深呼吸を一つして、ねむりに就いた。
永い、永い瞑りに。
葬儀は屋敷の大きさから考えれば地味といえる規模であった。
地元でも有数の郷士ということで一通り地元紙の記者達の姿も見えた。
しかし、源一郎の縁者、親族の姿はほとんど見えず、わずかに彼の娘夫婦が喪主で参加しただけであった。
源一郎はもともと没落した旧商家の生まれで、およそ裕福とは言いがたい幼少時代を過ごしてきた。その生活たるや悲壮を極め、当時戦時下の貧しい日本にあってもその生活レベルは苦しいと言わざるを得なかった。
ただ、この窮乏が全く不運であったかというと分からなかった。
彼の父親は栄養失調ゆえに徴兵されることはなく、母親も、源一郎自身も強制労働に狩り出されることがなかったからである。
しかし草をはみ、泥をすする生活には夢も希望も見出せず、彼はいつしか成功者となって、両親を助けたいと切に願うようになっていた。
満足に学校へ行くこともかなわぬ源一郎は血を吐く思いで学を修め、遂に働きながら大学を卒業し源一郎は大手電気会社への就職を果たす。
既に病気がちであった両親もたいそう喜んだものだった。
その頃日本は特需を迎え、総ての未来が輝いていた。無論、源一郎もその輝きを信じて疑いはしなかった。
その未来が木端微塵に砕け散ろうとも知らずに。
源一郎が就職した翌年母が結核で他界すると、父もそれを追うように過労で倒れ帰らぬ人となった。
源一郎は身の上の不幸を呪い、無情を儚んだが時代は彼に立ち止まることを許しはしなかった。
彼は猛烈に働いた。
働いている間だけ、彼の脳裏から忌まわしい記憶が放逐された。
天涯孤独の身となった源一郎には、仕事だけが寄辺となっていった。
源一郎が35歳の時、職場の女性と結婚したが彼は立ち止まらなかった。一女をもうけても源一郎は走り続けた。
いつしか彼は地元で有数の郷士となっていた。
それは夢にまで見た境遇であったが、源一郎は満たされはしなかったのである。
叶ってしまった夢など、最早夢とは言えないのだ。その事に気がついたとき、一人娘は嫁いで行き、源一郎の妻は既に亡かった。
源一郎は人生で2度目の喪失感に打ちひしがれ、金銭以外に何も信じられなくなっていた。
そうしてますます血縁者からも疎んじられるようになっていったのだった。
納骨が終わったのは既に陽がかなり西に傾いた頃、夕闇が東の空から忍び寄りはじめる、そんな時間だった。
「ようやく一息入れられるわね」
今回の葬儀の喪主を務めた源一郎の娘、篠原由希子は匂坂の屋敷の前でメイド達に辞去したあと、暮れなずむ空を見上げて呟いた。
「やれやれ、だな」
夫の善秀が由希子の肩を労るようにポンと叩いた。
「ところでさぁ」
今年から大学に通い始めた一人息子の健一郎が気怠げに口をはさんだ。
「じいちゃんって、ウチ以外に親戚がいないってホントかよ?」
由希子は困ったように微笑んだ。
「親戚はいるわよ。直系はウチしかいないんだけど」
健一郎の目は輝いた。
「じゃあさ、じいさんの遺産はウチのものなんだ? 確かおかんが1/2で残り1/2をおとんと俺とで山分けできるんだよな?」
善秀と由希子が顔を見合わせた。
その顔は喜色満面とはほど遠く、健一郎は両親の顔を交互に見くらべた。
「どうしたんだよ? 何か俺変なこと言ったか?」
しばらく、どうしたものかという表情で沈黙していた善秀が少しばかり困ったような、複雑な皺を眉間に寄せて口を開いた。
「その事でお前に言っておかなきゃならんことがある」
「はぁ?」
健一郎は要領を得ないような返事をした。
「まず結論から言おう。現金というかたちでの遺産はもう存在しない」
「はぁ!?」
今度の返事は明らかに不満と憤りが混じっていた。
「どーゆーことだよ? じいさんの遺産っていったら結構な額になるんだろ? 存在しないってどういうことだよ!?」
噛み付かんばかりに抗議する健一郎をいなした善秀は「まぁ、待て」と無言でジェスチュアする。
「まず、バブル時代にじいさんは結構な土地を買っているんだな。地価の下落でじいさん大損出してるんだ」
「地下のゲラク?」
「もう少し勉強しなさい、あんたは」
由希子が健一郎の後頭部をチョップした。お嬢様だったにしてはなかなかナイスなタイミングの突っ込みである。
「要するに土地の値段が下がってしまって、じいさんが高い値段出して買った土地が、今や二束三文って訳だ」
苦笑交じりに善秀が続ける。
「……そりゃ、大損じゃねぇか?」
「大損って言ったじゃない」
呆れたように由希子が肩をすくませる。
「さらに相続税率は70%で、残念ながら残された現金で払えるものじゃぁない」
「相続に税金がかかるのか?」
「しかも70%が税金だ」
健一郎は地面を思いっきり蹴り飛ばして悪態をついた。
「なんじゃ、そりゃぁ!」
「正直な話、相続権を放棄しようかと思ったんだが、弁護士の計算によると物納を併せるとまだいくらかは残るんだそうな」
「マジ?」
途端に健一郎の機嫌が治るのだから阿呆らしい。
「俺は? 俺はいくらもらえんの??」
鼻息を荒げる健一郎をどうどう、と抑えた善秀はしかし涼しい顔で
「だから、現金は残っておらんよ」
「現金はあのメイドさん達がお給料として持って行っちゃったからね」
「マジ?」
信じられないと言った面持ちで健一郎が両手をあげた。
「親族を差し置いて?」
「そう遺書に書かれていたからね」
由希子の口の端はその時、かすかに歪んだがすぐに元に戻った。
実質メイド達だけで源一郎の身の回りは賄われていたのだ。盆と正月には匂坂の屋敷に顔を見せていたとはいえ、由希子自身正直なところ家族を顧みなかった父親にはあまり好い感情は持っておらず、それどころか心のどこかで母を死の淵に追いやった父を恨み疎んじていたのかもしれなかった。
だから、娘よりもメイドを優先させた父の遺書に初めて目を通したときも、ある種の落胆と諦観ゆえの苦笑を頬に刻んだものだった。
「遺書?」
健一郎はなおも食い下がった。
遺書と聞いて胸が高鳴るのは明らかにTVの見過ぎだが、当の健一郎には一切自覚はない。
善秀は肩をすくめた。
「そこには遺産の分配についても詳しく書かれていた。お義父さん、結構まめな方だから何が残るかまできちっと計算されてたよ」
「で? で?」
ふうっとため息をついた善秀は懐からコピーを取りだした。
目録として記されたものは箪笥やベッド、テーブルといった類である。
勿論源一郎の眼鏡に適ったものだけあってどれもかなりの価値はあるのだが、健一郎にとっては些かつまらない品々であったようだ。
そんな中で健一郎の目に留った文字があった。
「なぁ、この車両って、なんだ?」
目録を指さして健一郎が聞いた。
「ん? ああ、それか」
善秀はやや口ごもるように返事をした。
「お義父さんの車だよ。生前に乗っていらした……」
「すげぇ!」
健一郎が間髪入れずにパチンと指を鳴らした。
「いいもん残ってるじゃんよ? なぁ! その車、俺にくれよ! こないだ免許も取ったし、いいだろ!?」
善秀は狂喜して小躍りをはじめる健一郎を見遣って溜め息をつく。
「やめておいたほうがいいぞ?」
その口調は明らかに事情がありそうだったが、今の健一郎には詮索できる心の余裕はない。
「いいって、いいって!」
なおも踊りながら健一郎は両手を振った。
既に健一郎の頭の中は大学へ車で通うクールな自分自身や、車でナンパしたカノジョとのウハウハな妄想でいっぱいであった。
その様子を呆れながら見ていた由希子と善秀は、今さらながら我が子の軽薄さに頭を痛めるのであった。
「なぁなぁ、じいちゃんの車ってさ、やっぱ、ベンツ? ビーエム(BMW)?」
健一郎の頭の中で高級車といえばこのクラスなのだ。間違ってもロールスロイスやベントレイが出てこないあたり、彼の金銭感覚は庶民のそれと大きく懸け離れているとはいえまい。
「残念ながら……」
由希子は苦笑しながら答えた。
その苦笑はしかし、健一郎の価値観を嗤(わら)ってのものではなかった。
「まさかフェラーリとか言うんじゃないだろな? 俺、AT免許しか持ってないぞ?」
確かに今や日本国内を走る車の殆どがオートマチック・トランスミッション(AT)車なのだから、AT免許=車の免許と言えなくはない。
だが、
「ま、確かにあれに乗ろうって言うならMT免許がいるな」
善秀はしれっと言った。
腕を組んで考えていた健一郎はしばしの熟考のすえ、手を打った。
「しかたねぇ。AT免許持ってるからMT免許はすぐに取れるだろ? フェラーリのためだ。取ってやるよ」
「いや、ダレもフェラーリだとは言っておらんが……」
さすがに善秀が裏手パンチで突っ込んだ。
「んじゃ、ポルシェ?」
「……当たらずとも遠からず……って気がしないでもないが、やっぱり違うな。……ビートルだよ」
今度こそ健一郎の目が点になった。
「は?」
「だから、ビートル。VWビートル」
「……マジっすか?」
「しかも1953年式だ。かなりの老骨だから大変だぞ?」
今年19歳の健一郎にとって50年前というのは既に歴史の教科書の中の話であり、50年前の車など老骨というよりはポンコツに等しかった。
「って、じいさんそんなのに乗ってたのか?」
健一郎が信じられないと言った面持ちで聞き返す。およそ大富豪の車とは思えなかったのだ。
「病気で寝たきりになるまではご自身で運転されていたそうだ」
「初めて聞いたぜ……」
健一郎は呆れながら呟いた。
「で、どうするんだ? それでも乗るのか??」
善秀の声に少しばかり意地悪な響きが混じった。苦笑するように。
健一郎は顎に手をやって少し考えるような仕草を見せると、あっさりと首肯した。
「よし! もらったぜ!」
「……分かった。だけど、本当に大変だぞ? あっという間に降りるのがオチだと思うが……」
健一郎の飽きっぽくてズボラな性格を熟知する父親はこの時、実にすばやい決断を下した息子になおも疑わしい視線を投げ掛けた。
「車は車に違いねぇし、何より今、旧いのって流行ってるじゃん? '53年式なんて誰も乗ってないよ? かなり渋くない?」
「渋いのは渋いだろうな。ちゃんと維持して乗りこなせれば」
そう言った善秀の目は彼方の空を見ていた。
「?」
突然遠い目をした父親を怪訝に思いながら、健一郎は
「じゃ、じゃぁ、俺はすぐにでもMT免許とるよ。おとんは車の手配頼むな」
とだけ言った。
「ん? ああ、わかった」
どうも心ここにあらずといった風に応える善秀であったが、今の健一郎には父の胸に去来する想いを伺い知ることはできなかった。
それから三人は言葉少なに帰宅したのであった。