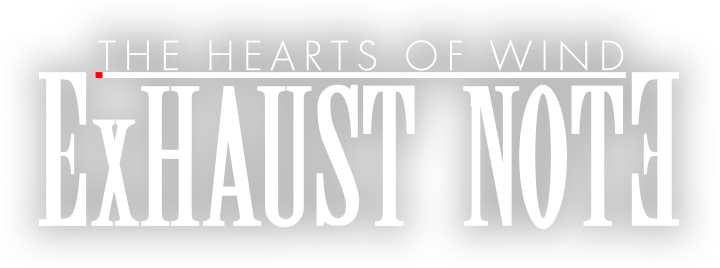novels
遺産相続
大学生というのは暇なものだ。
もちろんその時間は社会人になるための準備期間に過ぎない。資格を取得したりする時間というのは案外この時期くらいしかないものだ。
健一郎は葬儀の翌週、大学の休講を見計らって自動車学校に赴くとMT免許を取得するメニューへ申込みを済ませた。
最近はインターネットで申込みできるようだが、健一郎はパソコンがイマイチ苦手で、ネットサーフィンくらいならまだしも金がからむとさすがに怖い。自動車学校が家から自転車で10分ほどのところにあるので、手間でもなかった。
教習自体は技術教習がメーンとなり、すぐに済みそうだ。
ビートルの方は源一郎が病床に臥せってより旧知の自動車工場に保管されているとのこと。
「自宅のガレージに置いておくと腐る」と源一郎が言うので定期的にエンジンをかけたり、工場敷地内を走ったりしているので状態は悪くないらしい。ただ、既に車検は切れているのでナンバーはついていない。
こちらの方もすぐに路上へ復帰できそうだ。
ビートルの方は自動車工場におまかせするとして、健一郎は免許の書き換えに専念することにする。
教習所で初めて乗ったMT車は確かに難しかった。クラッチに神経を集中すると、ついつい周囲への注意が散漫になりがちになる。
何と言っても難しいのが坂道発進で、何度もエンジンをストールさせる羽目になった。
「やっぱMTは難しいな」
教習を終えて帰宅すると、健一郎はキッチンに立つ母の由希子にぼやいた。
「な~に言ってんの? まだ1回目じゃないの」
夕食の準備をしながら苦笑交じりに由希子が応えた。
あれほどの富豪の一人娘にしては随分とつましい姿である。
家族も顧みずに仕事に打ち込んだ父親から半ば逃げ出すように家を出たのだから、当然と言えば当然かもしれない。
いま、商社勤めの善秀と三人で築いた家庭は不景気な今の世にあっては十分裕福と言えた。
家は普通の建て売り住宅だし、ガーデニングができるほど広い庭があるわけでもない。車を2台置こうとするとその小さな庭さえほとんど消えてなくなってしまう。
それでも由希子は結婚したことに後悔していない。いや、よかったとさえ思っている。それは源一郎が亡くなってしまった今も変わらない。
家族が一緒にいられること、それは少女の頃から由希子が夢にまで思い描いていた「幸せの形」だから。
もちろん由希子の物心がつくころには匂坂家は十分に裕福で、由希子は立派な「お嬢様」だったから善秀の苦労は想像に難くないが……。
フローリングのリビングに据えられたソファにどっかりと腰を下ろすとテレビのリモコンを探しながら、健一郎はテーブルの上にあったリーフパイを一つつまんで
「ま、俺の才能をもってすれば、その難しいMTもちょちょいのちょいな訳よ」
と軽口をきく。
「ちょちょいのちょい、ねぇ」
一体この軽い性格は誰に似たのだろう?
由希子はヤレヤレと肩をすくめる。
「まぁ、見てなって! あ~、ビートルかぁ! 楽しみだなぁ!」
もう既に健一郎は永遠の世界に旅立ってしまったようだ。こうなるとしばらくは現実の世界に帰ってこないから、由希子は夕食の準備を続ける。
呼び鈴の音が聞こえたのはそんな時だ。
「お父さん帰ってきたから、玄関開けてきてちょうだい」
由希子がビデオフォンに目をやって健一郎に言ったが、当の健一郎はビートルを颯爽と駆って峠の覇者になっている(夢想中)ので、聞こえはしない。
健一郎ワールド内では非力なビートルで、並み居る走り屋の強豪達を鮮やかなドライヴィングテクニックでバックミラーの彼方へとおしやる(あくまで夢想中)未来の自分がいた。
獰猛な速度で流れ去るガードレールぎりぎり一杯まで車体をアウトに寄せ、迫りくるストレートエンドを見据えながらスロットルペダルを一杯まで踏み続けていた右足は、不意にブレーキペダルへ移動して素早く、しかし繊細に踏み抜く。
荷重が前輪に乗る。ハンドルの手応えが変わる瞬間、必要最小限だけステアリングホイールを切る。否、斬ると言うほうがよいかもしれない。切れ味鋭い刃物のように車体がイン側に吸い込まれる。クラッチ操作もそこそこにギアを落としてやると重いはずの後輪が悲鳴を上げながらスライドを始めた。(ひたすら夢想中)
ビートルのノーズは一直線にクリッピングポイントを目指し、ステアリングはわずかに外へ。
減速Gが次第に横Gへ変化する。スライドを始めたときから右足はスロットルの上でコーナーの出口が見えるのを待ち構えながら……
と、その時激しい衝撃が健一郎を襲う。
刹那、健一郎は何が起きたのか理解できなかったように周囲を見渡す。
「くぉら! いつまでやってんの!? さっさと玄関の鍵、開けてきてちょうだい!」
後頭部に鈍痛を感じる健一郎の足下におたまが転がっていた。
そう言えばさっきから呼び鈴の音がする。
健一郎はコブのできた後頭部をさすりながら玄関へと腰を上げた。
帰宅した善秀はスーツを脱ぎながら「ビートルができたそうだ」と健一郎に伝えた。
「マジ?」
目を輝かせるが早いか、健一郎は小躍りをはじめる。
いつものことなので善秀は全く気にしない風に続ける。
「免許を書き換えたらここへ行け。アポを取るのを忘れない様にな」
そう言って一枚のFAXを健一郎に手渡す。
FAXには手書きで「仲里オート」と書かれており、連絡先と簡単な地図がやはり殴り書きのように添えられている。
「うわ、きたねぇ字」
自分のことは棚に上げて健一郎が眉を顰(ひそ)やす。
「そうそう、言い忘れていたが……」
気付いたように善秀が振り返った。
「車両はもちろんタダだが、検査までは入ってないからな。車検にかかった費用はお前が払えよ?」
健一郎の踊りがピタッと止まった。
「何ですと?」
車に自賠責のほかガソリンやタイヤ以外の出費があろうとは、彼にとっては全く予想外だったようだ。
「……車検にかかった費用って自賠責のこと?」
恐る恐る訊いた健一郎に用意された善秀の返答はもちろんNoである。
「もちろん自賠責も含まれているが、車検通すためには整備してもらうわないと。その整備費用、代行手数料、自動車重量税もろもろひっくるめて十五万円」
「Σ( ̄□ ̄;)!!」
言葉にならない叫びを発して健一郎が凍りついた。
しばらく氷点下の時間が二人の間に流れたが、やがて
「おとん……」
「金なら貸さんぞ」
にべもなく即答する父親に「うぐぅ」と健一郎が恨みがましい声をあげた。
「……だって今度ボード買うのにあの金要るんだぜ?」
「知るか、そんなこと」
善秀は何事もない様子で部屋着に着替えて
「んじゃ、そういうことで宜しく。今更キャンセルは利かんからそのつもりで」
ポンポンと健一郎の肩を叩いて善秀がでていく。
後に残ったのはFAX用紙を握り締めてたたずむ男一人……。
健一郎の免許更新が済むのに幾日か掛かったが、新たな免許証(といっても裏面に条件変更のハンコが捺されただけだが……)を携え、更には血を吐く思い(←大袈裟)でスノーボードを諦めて掻き集めた金を手にFAXにある仲里オートを訪れることになった。
アポを取るのに電話をかけると、嗄れたやや甲高い男声が応対にでた。
「すみません、篠原健一郎といいますが?」
「はァ?」
つっけんどんな返事に健一郎は内心げんなりしたが、
「いや、えっと、ウチの死んだじいさんのビートルがそっちにあるって聞いて、取りに行きたいんだけど……」
「もうできてるよ! いつでも来てくんな!」
「あ、はい。じゃ、今からあの……」
言うが早いか電話は切れてしまった。
ツー、ツー、と寂しい発信音を立てる受話器を憮然と睨(ね)め付けた健一郎はあからさまにげんなりした。
「う~、感じワル~」
とは言っても致し方ない。健一郎は肚を括って家を出た。
FAXによれば店は健一郎の家からさほど遠くはない。
電車で十五分も揺られたら、あとは徒歩で十分ほど。
健一郎は駅を降りて、歩きながら周囲を見渡した。
小高い山々が甍(いらか)の向こうにいくつか見える、街中というほどでもなく、さりとて郊外というには開けた場所。
クルマ屋さんなどに求められる比較的広い土地と、ある程度の人通りが必要という難しい立地条件に適(かな)っている。
程なく健一郎は「仲里オート」の小さな看板を発見した。
見れば木造モルタルの、周囲の家々から完全に時を切り離された小さな店。
旧車が数台並んでいなければ、クルマ屋さんとは誰も気付かぬだろう、質素この上ない構えであった。
「仲里オート 自動車販売・修理」
筆書きで書かれた旧い看板とFAXを交互に見比べながら健一郎は嘆息した。
「ホントにじいさんって、金持ちだったのか?」
眉根に皺を寄せながら小さく独語めいて、入口へと歩み寄る。
磨りガラスに「仲里オート」とやはり筆書きされた木枠の引き戸。
一瞬健一郎は今が二十一世紀であることを忘れそうになる。
がたがたと引き戸を開けて健一郎は店に入った。
木の匂いが健一郎の鼻孔をくすぐる。入口側面に掛けられた柱時計がカ、コ、カ、コ……とゆったりした時を刻んでいる。
部屋の中は薄暗く、人の姿は見えない。
「あの~、すみませ~ん」
蚊の鳴くような声で人を呼んでみた。
返事はなく、柱時計だけがやはり正確なリズムで静寂(しじま)を破り続けていた。
「誰もいないのかな?」
そっと部屋の中に入った健一郎は中を見渡した。
机や戸棚はしっかりした木製で、使い込まれた調度独特の艶がある。
来客用のソファとテーブルも窓際に置かれていた。
壁に目をやると本棚には古い自動車雑誌がぎっしりと並んでいるが、背表紙を見るかぎり1980年代以前のものがほとんどのようだ。
古いが掃除はきちんとなされており、健一郎にはここがアンティークショップか何かのように思えるのだった。
しぃんと静まり返った事務所を見回していると、裏手で微かに音がしているのに気付いた。
どうもエンジンを回しているような音だ。もしかすると裏手が工場になっているのかもしれない。
健一郎は事務所を出てぐるりと店の回りを歩いた。
裏に廻ると小さく見えた店は意外に広いことが分かった。
クルマはもう十台ほど停められている。その他ジャンクと思しい資材も積み上げられていた。
工場はちょっとしっかり作られたプレハブと言った風情で、鋼板やアングルがむき出しの粗野なもの。
その中に見える黒っぽい車は間違いなくビートルであった。
健一郎は「お?」と声をあげて工場へと急いだ。
工場の中に誰かがいるようだ。
「あの、すみません!」
健一郎が声を掛けると整備士は手を止め、健一郎を見た。
整備士はブルーの帽子と、洗いざらしの白いツナギをまとった、おそらく六十近い老人である。
痩せぎすの体躯で帽子の奥の瞳は鋭く、どちらかといえば神経質そうなその印象は、健一郎が電話で受けた印象と懸け離れたものではない。
「え、と。さっき電話した篠原ですけど」
じっと見続けられて気まずくなった健一郎は、頭を掻きながら言った。
「ああ」
ぶっきらぼうに答えた整備士の声は電話で聞いたものに相違なかった。
「……あの、そ、それがその……じいさんの?」
「ああ」
あくまで老人はぶっきらぼうだった。
健一郎は気まずさのあまりげっそりした。今時こんなアナクロな爺さんがいたものだ。
老整備士はツナギのポケットをまさぐると、何かをぽーんと健一郎に投げた。
慌てて受け取ると、それはくたびれた革製の収納式キーホルダー。
キーホルダーのスナップを開けるとメッキが剥げ、打痕で痩せ細ったオリジナルキーがひとつと真新しいコピーキーがひとつ、二本のキーが納められていた。
「シートに座れ。動かし方を教えてやる」
「? 免許は持ってますよ?」
「いいから座れ」
語気に凄みを感じて健一郎は渋々ビートルに近づいた。
間近に見るビートルはさすがに年代相応にやれているが錆一つ浮いてはいない。
車体色は黒に近いが少しグレーっぽい。
と、ここまで近づいて初めて気付いた。
「これ、左ハンドル?」
老整備士は助手席に腰を下ろしながら面倒くさそうに答える。
「見れば分かるだろう」
健一郎はさっきまでの根拠のない自信が木端微塵に砕け散ったことに気付いた。
「でも、俺左ハンドルなんて……」
そこまで言ったとき、バン! と言う大きな音がして健一郎は吃驚(びっくり)した。
整備士がビートルのドアを閉めた音だった。
「乗るのか? 乗らんのか?」
「……乗ります」
――何で客の俺がこんな目に……――
等とぶつくさ言いながら健一郎がシートに腰を下ろす。
聞こえているはずだが、老整備士は何も言わない。
シートベルトを掛けてミラーを合わせるが、ドアミラーはともかくルームミラーからはほとんど何も見えない。
怪訝に思って振り返ってみると、リアウインドウは半円状の窓が向かい合った小さなものしかない。
「スプリットウインドウ」
整備士が呟くように言う。
「は?」
健一郎が聞き返すと整備士は口を開いた。
「こいつは一九五三年式で『スプリットウインドウ』最後のモデルだ。見ての通りリアウインドウのど真ん中にピラー(柱)があって後方視界は最悪だ。ビートルはこのモデル以降のリアウインドウからピラーを廃して『オーバルウインドウ』モデルに移行する」
この男クルマのこととなると打って変わって饒舌になるらしい。
「はぁ……」
健一郎は面食らいっぱなしである。
メーターダッシュに目をやった健一郎はここでも軽いカルチャーショックに見舞われることになる。
ハンドルポストに付いている筈の、キーを差し込むところもなければワイパースイッチも何もついていない。付いているのは左側にウインカーレバーがついているだけだ。
メーターは目の前にスピードメーターが鎮座するだけ。
インジケーターの類一切無しのシンプルこの上ない、健一郎からしてみれば不安になるほど頼りない眺望がそこにあったのだ。
「あの、どこにキー差し込んだら……?」
「ここだ」
整備士が指さすところ……助手席に近い、グローブボックスの左下に確かにキーが刺さりそうな穴が開いている。
とりあえずニュートラルとサイドブレーキを確かめてキーを回す。
「……艦長! 動きません!」
健一郎は再放送で昔見たSFアニメの某航海長の様にうめいたが、整備士にとってはさして驚くに値しないことだったようだ。
「スターターボタンはそれだ」
そう言ってメーター左上にあるボタンを指さす。
プッシュボタン式のスターター?
健一郎が混乱しながらも指を伸ばすと
「待て」
と整備士が制した。
「この頃のビートルは電装が6V(ボルト)だ。火花が弱くて失火しやすく、カブらせると立ち直るのが難しい。始動は常に一発でしなくてはならん」
健一郎は老整備士の顔をまじまじと見た。
ネタなんだろうか?
中途半端に頬を引きつらせたまま、健一郎は
「ど、どうすれば?」
と訊いた。
「エンジンの油温と外気温、それまでのエンジン使用状態に気を配れ。温度が低いとガソリンは気化しにくく、高いと気化しやすい。気化しにくいようならチョークを加減しながら引く。気温が高かったり、それまでエンジンをかけていて再始動するような場合なら逆にチョークは不要。但し、温度が高すぎるとガソリンは勝手に気化するのでエンジンから不必要なガスを抜く必要がある。アクセルを全開にして2~3回クランキングしてから、一発必中の気合いでスターターピニオンをぶち込め」
一気呵成に説明されたが、健一郎には遠い外国の言葉のようだった。
「あの、具体的には……?」
流れる冷や汗をそのままに健一郎は聞いたが、遂に彼の満足できる答えは得られなかった。
「車に訊け」
整備士の言葉はこれだけであった。
とにかくこの気まずい空気を何とかしなくてはならない。
健一郎はボタンを押した。
するとクックックというやや間延びした音がして空冷水平対向4気筒エンジンが目を醒した。
バサバサとボクサーエンジン特有のアイドリングを奏でる。
「掛かりました」
整備士は頷くと
「あと変わっているのは方向指示器だ」
「ええと、左ハンドルだからこれがウインカーですよね?」
「ウインカーではない。方向指示器」
「?」
わざわざ言い直す意味を不審に思いながら、「えっと、何か変わってるんですか?」と訊く。
「まずは動かしてみろ」
健一郎はレバーを作動させて周囲を見渡したが何も起こっている様子はない。
整備士はちょいちょいと車体の外を指さす。
健一郎がその指先を視線でたどっていくとCピラーの所に何やらオレンジ色の物体が突き出ていた。
「は?」
「『セマフォー』と言うやつだ。昔の指示器はこんなもんだ」
「……(汗)」
こんな指示器で誰が気付いてくれるというのだろう?
まだ手信号の方が通じるような気がする。
「あとはヒーターとデフロスターの使い方だな」
「う~、もしやとは思っていたけど、エアコンは無しか……」
当たり前である。
「まだまだ覚えてもらわにゃならんことはある。ちゃんと覚えるまで引き渡さんからそのつもりでな」
「げ……っ」
健一郎は今更ビートルを譲り受けたことを後悔したが、本当の後悔がこの後に待っていようとはまだ知る術がないのであった。