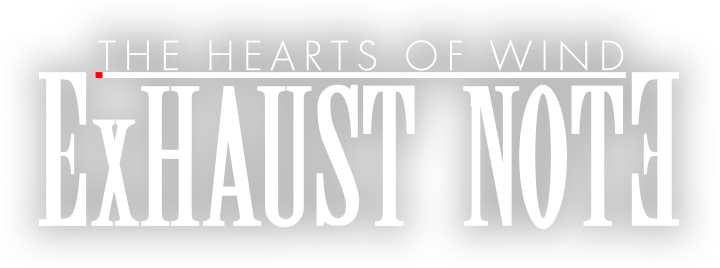novels
遺産相続
一通りビートルの操作を教わったころには陽は既に傾きかけていた。
シートの調整や、ドアロック、ローラー式のアクセルなど今の車と構造が随分違うのには慣れるしかあるまい。
操作はパワーアシストの付いた今の車に較べて若干重い。
重いハンドルやクラッチについつい操作が遅れがちになって、工場の構内を走るだけで危なっかしいが、整備士……仲里は無言で隣に乗るだけであった。
「よし、いいだろう」
車については驚くほど饒舌な仲里だが、健一郎の拙い技術については何も触れず、その言葉だけが健一郎にかけられた。普通ならば危なっかしくて見てもいられないような走りだったにも関わらず。
ビートルを降りる際、「やはり血は争えんな」という呟きを健一郎が聞いたか否か。
仲里は工場へ戻るとビニールケースに入った書類を持ってやってきた。
「これが車検証と自賠責の領収書だ。車に積んでおけ。それから親父さんから預かっているハンコ。これで晴れてこのビートルはお前さんのだ」
そう言って渡された車検証には「篠原健一郎」の名が印字されている。
こうしてみるとなかなか感慨深い。ふつふつとこの車が自分のものになったという実感が湧いてくる。
「料金は十四万八千円だ」
健一郎がすっかりひたり込んでいたため放りっぱなしにされていた仲里が、ぼそりと呟くように言った。
不意に現実に引き戻された健一郎が思いだしたように料金を支払うと、仲里は踵を返した。
「じゃ早く帰れ。じきに夜になる」
手をヒラヒラさせるジェスチュアが人を追っ払っているようで健一郎はむっとしたが、何も言わないことにした。
もうここに来ることはない、と言うのは健一郎の早計というものだが、少なくとも長居は無用のようだ。
健一郎はビートルを走らせて一路自宅へと向かった。
この周辺は善秀の運転する車で何度か通ったことがある。
何となく覚えている道順で帰ることにするが、通りへ出ようとしていきなりエンスト。
その後も幾度となくエンストに見舞われたのは、おそらく重いクラッチ(といってもビートルが特段重いわけではない。健一郎が単に慣れていないだけだ)にそろそろ左足が疲労してきているためだろうが、現在必死の健一郎に自覚はない。
走り始めると健一郎は思ったよりもビートルが非力であることに気付く。
アクセル全開で車の流れをリードできるかどうか微妙。
回転計(タコメーター)はないが、かなり回転を上げているはずなのに、周囲を流れる風景はのどかに過ぎ行く。
おまけに交差点などでブレーキを踏んでも、ちっとも止まる様子がない。まるで氷の上でも走るようにツーッとアスファルトの上を流れていく。
力いっぱいブレーキペダルを踏み込んでようやくといった感じだが、危うく最初の信号で追突するところだった。
無論教習車のブレーキブースターに慣れきった健一郎がそう思っただけで整備不良でも何でもないのだが、この時点で健一郎の中で「峠の覇者(キング)」シナリオが、音を立てて崩れていったのは間違いない。
かと言ってナンパカーとしてもビートルはハッタリが利きにくい。
どこにでもある車なのだ。少なくとも見た目には。
健一郎は交差点を右折しようとウインカーを出すが、けたたましいクラクションの洗礼を受けるたびに思う。
「『見た目』はどこにでもある車なんだよね」
しかし、五十年生きてきた車というのは日本の路上には数えるほどしか残ってはいないのだった。
ローラー式のアクセルにも手を焼かされた。
普通のクラッチ操作も怪しいというのに、不慣れなローラー式アクセルのおかげでエンスト率は1.5倍。(当社比)
何でもないところでよく止まる。
坂道発進など惨憺たるもので、停止するごとにエンストと言うのも珍しくはない。酷い時には同じ場所で二回三回とストールさせて、路上のパイロンと化す。
たった二十分か三十分のドライブだったが健一郎が家に帰りつけたのは僥倖と言うか、既に奇跡であった。
やっとの思いで帰り着いた時には辺りは暗くなりはじめていたが、6Vの貧弱な電装しか持たないビートルのヘッドライトは行灯(あんどん)のように暗くて、まるで使い物にならない。
仲里が「早く帰れ」と言うのも頷ける話だ。
四苦八苦しながら自宅の駐車場にビートルをパークさせたときには、健一郎の腕はパンパン膝はガクガクという有り様。
「あら、遅かったわねぇ……って、あんた何て顔してるのよ?」
鍵を開けた由希子が玄関で健一郎を迎え入れて率直な感想を述べた。
「え? どうかした?」
健一郎は精神的な疲労で、ぐったりと応えた。
「目が落ちくぼんでるわよ。どうしたのよ? あんなに楽しみにしてたじゃない?」
由希子は玄関のドアを閉めて施錠しながら訊いた。
「いやぁ、なんでもないよ……」
へらへらと力なく笑った健一郎は、そのまま自室におぼつかない足取りで戻っていった。
「?」
由希子はその様子を怪訝な面持ちで見送る。
自室へ戻った健一郎は照明もつけずにベッドに前のめりに倒れ込んだ。
車に乗ってこんなに疲れたのは久しぶりだ。少なくとも初めて車に乗った時か、それ以上の疲労感を感じる。
「……冗談じゃないぜ」
一人ごちた健一郎はそのまま微睡(まどろ)みの中に身を沈めていった。
それからどれくらい時間が経ったのだろうか。
階下から由希子が食事を告げる声で目が覚めた。
まだ少し頭の芯が痺れているような感じだが、身体の方は膝が震えることもないし、腕が張るようなこともない。
再び由希子の声がする。
「ご飯冷めちゃうわよ! さっさと降りてらっしゃい!」
幾分強められた語気に「ふぁい」とだけ返事して、健一郎がずるずるとベッドから起き上がる。
寝ぼけ眼(まなこ)で階段を降りていくと既にダイニングには夕餉の用意が整っており、善秀が席について夕刊を拡げていた。
「あら? あんた寝てたの?」
と最後の一皿をテーブルにサーブしながら由希子が聞いた。
「ん、もう起きた」
ぼりぼりと頭を掻きながら、欠伸(あくび)をひとつして席につく。
「お疲れさん。とりあえず事故には遭わなかったようだな」
善秀が新聞から目を離さず訊いた。揶揄(やゆ)するような響きを声に乗せて。
少なくとも善秀はあのビートルがどんな車かを知悉している様子だった。
「なぁ、おとん」
頬杖をつきながら健一郎が聞いた。
「あの車、買わねぇ?」
「いらん」
なお視線を新聞から外さず善秀が即答した。その間0.5秒の即決であった。
「なんだ、もうギブアップしたのか?」
そう言うと善秀が意地の悪そうな微笑みを浮かべて健一郎を見た。
「いや、そんな訳じゃないけどよ……」
やや歯切れ悪そうに健一郎が下を向いた。
しばらく無言だった善秀は徐(おもむろ)に口を開く。
「昔、あのビートルを一度だけ借りたことがあってな」
その口調は遠い昔語りをするようだった。健一郎にとって初めて聞く話だが、無論ビートルの存在を知ったのが祖父源一郎の死後なのだから当然と言えた。
「ま、あの時は車がなくて仕方なく乗ったんだが……、あまりのロートルぶりに辟易したな。揚げ句の果てに指示器を見落とした後続車にオカマを掘られてむち打ちさ」
「……」
今の健一郎には笑えない話だ。
ヘッドレストもないシートでは、軽く接触されただけで搭乗者の首は激しく揺さぶられるだろう。
「幸い大したスピードでなかったから車もバンパーが少しヘコんだ程度で済んだし、俺も後遺症に悩まされるようなことはなかったんだが、今の交通事情を考えるとさすがにな」
腕を組んで考える二人をよそに、由希子が席についた。
「何よ、二人して……。冷めちゃうわよ、さっさと食べましょ」
二人は心ここにあらずといった感じで箸をつけた。
「もう、あんたたちねぇ……」
由希子が呆れて口を開いた。
「そんなに気に入らない車だったらさっさと中古車屋にでも売り飛ばしちゃいなさいよ」
実父の形見だというのに由希子にとってビートルは、微塵も未練を残さぬようだ。
「いや、そうは言ってもな……」
義父が大事にしてきたビートルを何処の誰とも知れぬ人間に乗り回されるのは、善秀にとっては正直気持ちのいいものではなかった。
「だったら博物館とかは? 珍しいから引き取ってくれるんじゃない?」
これも正論だったが善秀は首を縦には振らなかった。
「確かに五十三年式ってのは今の世の中珍しいが、ビートルそのものは珍しいわけでもない。……難しいんじゃないかな?」
どうにもやはり善秀はビートルを手放したくはないらしい。これでは誰がオーナーかわからない。
由希子が苦笑する。
「そんなにあの車がいいんだったら、あなたが乗ればいいのに」
善秀は慌てて
「イヤ、オーナーはホラ、健一郎だからさ」
と逃げに入って、健一郎の方をバンバンと叩く。
「というわけだから、頑張って乗りこなしてくれたまえ。大丈夫、お前ならきっと乗りこなせるさ」
健一郎がむせんでせき込んだのはいうまでもない。
次の日、健一郎は大学へビートルで出掛けた。
普通に電車で通えば30分ほどの距離にある大学が、いやに遠かった。
結局一時間以上も掛けて何とか無事に大学の駐車場に辿り着いた。
「なんだ、お前車買ったの?」
駐車場で出会った友人の野崎信治に声を掛けられる。
「しかもワーゲンじゃねーの。イイ趣味してるな」
じろじろと鉄(くろがね)の車体を見回して信治は言ったが、健一郎には気休めにならなかったようだ。
「じゃ、お前乗るか?」
「?」
講堂へ向かう途中、如何に手のかかる乗り物であるかを滾々(こんこん)と信治に語った健一郎は、最後にあーあと嘆息した。
「絶対失敗したよなぁ。車がタダで手に入る、しかも爺ちゃんの車だからてっきり高級外車だって思ったから貰ったのに……。欲しいって言ったのは俺だけど、こんなに手がかかるなんて思ってもみなかったよ」
「ふーん」
信治は何かを発見したような、語尾の少し上がった調子で唸った。
「なんだよ?」
「いや、文句ばっか言っている割にはいやに嬉しそうじゃないかって思って……」
「はぁ?」
健一郎は素っ頓狂な声をあげた。
「嬉しそう? 俺が??」
「だってそうだろ? 手がかかるとか苦労するとか散々言ってる割に全然嫌そうには見えねーんだから」
むしろ意外そうに信治は健一郎を見た。
健一郎は混乱した。
そりゃ確かに車を手に入れて舞い上がっているところはあるが、嫌そうに見えないってのはどういうことだろう?
「お前ねぇ。どこの世界に普通に乗って命の危険さえ感じるような車を嬉しがるバカがいるの? 上り坂なんて原チャ(原動機付き自転車:原チャリ)にアオられるんだぜ? ブレーキは効かねーしさ、ウインカー出しても誰も気付いてくれないしさ」
「そうそう、その顔」
「?」
信治の言葉に健一郎はますます訳が分からなくなっていた。
「そんな手のかかる旧車に乗ってる自分に酔ってるってカンジのその顔が嬉しそうっていうのさ」
「だから~……」
「乗ってみろってか? 俺は遠慮するけどね」
「だったら……」
「そんな車に乗って学校に来るお前はどこか嬉しがってるんだよ」
「いや、それはだな。今日は夕方から天気が悪そうだから……」
しどろもどろに返事をする健一郎の目はどこか忙しなげに揺れ動く。
「それなら電車で来りゃいーじゃねーの。あ、そうだ。だったら今日はお前に送ってもらおうかな?」
「い…イヤ、免許とってまだ日が浅いし、ホラ、免許とって1年間は確かヒト乗せちゃいけなかったんじゃ……」
それは2輪だろ? と言うツッコミを用意した信治だったが、講堂に着いた二人はそれ以上会話を続けることはなかった。
既に講義は始まっていて、教授がじろりと二人を睨んだからだ。
二人はばつが悪そうに後ろの席に腰を下ろした。
珍しく天気予報があたりそうだった。
講義の最中も健一郎は窓の外をちらちらと見遣った。
朝は薄曇りであった空はいつしか厚い雲に覆われていた。
時間とともに湿度が上昇していくのが分かる。
お昼を過ぎると、とうとう低く垂れこめた雲からぽつぽつと滴が落ちはじめ、健一郎の講義が終わるころには蕭々と雨がアスファルトを叩いていた。
言うまでもなくビートルでの雨天走行は健一郎にとって初めての体験である。教習中一度だけ雨に降られたことがあるが、正直あまり気乗りはしない。
小走りで駐車場まで降りた健一郎は、手早く車に乗り込んだ。
いつもの調子でキーを回してスタートボタンを押すと、いつもより火が入りにくい。
十数回のクランキングでやっと空冷ボクサー4気筒が目覚める。ミラーにやや黒っぽい排気ガスが見えたが健一郎は気にしなかった。
短い暖気を済ませてそろそろとビートルは走り出した。
雨はかなりの勢いだった。
道には大きな水たまりがいくつもできており、ざばざばという音がホイールハウスから聞こえてくる。
「雨漏りしねーだろうな? このオンボロめ」
健一郎は毒づきながらドライブする。
シグナルスタートの出足でエンジン回転が落ち込んで、危うくストールしそうになりながら、危うい雨中のドライブが続いた。
いくつめの信号だったろうか。
健一郎がおっかなびっくり、何とか右折レーンに入って停止線に辿り着いたところでビートルのエンジンがまるで息絶えるようにひっそりと止まった。
「んが?」
健一郎が大きな声とともにハンドルを手のひらで叩く。全くこの老骨はいちいち健一郎を楽しませてくれる。
大きな舌打ちをして健一郎はスターターボタンを押す。
暫くクランキングしてみたが、ビートルのエンジンは息を吹き返さなかった。
そうしているうちに信号は青に変わり、健一郎はあせった。
「やべっ!」
ククク、クククとあざ笑うようなセルモーターの音は次第にゆっくりになっていく。
たっぷりと冷や汗をかく健一郎にとうとう後続車のけたたましいクラクションの嵐が襲いかかる。
「えーい! 畜生!」
健一郎は一言吠えると雨の中へ飛び出して、ビートルを押し始める。とにかくコイツをどけなくてはこの非難のクラクションから逃れる術はない。仮に動かなかったとしても、後続車へのアピールとしては効果があるだろう。
ハンドルを肩に担ぐようにしてビートルを押してみると、意外にビートルは動き始めた。
もちろん重いがまるでお手上げというわけではなさそうだ。
雨でジャケットは重く濡れ、運動不足のふくらはぎが悲鳴を上げるが今はとにかく交差点を抜けるのが先だ。
誰か手伝ってくれるかと思ったが、この雨ではさすがに誰も手助けしてくれない。
「畜生!」
健一郎はもう一度吐き捨てた。
息も絶え絶えになりながらビートルを押して右折させた健一郎は、交差点を過ぎたところへビートルを停めてシートに戻った。
膝がかくかくと笑っていた。
全身ずぶ濡れで酷い身なりをしていたが、健一郎は息を整えるのが精一杯で気にもならなかった。
「ふーっ」
息をついた健一郎は、猛烈な怒りに駆られた。
「あんのオヤジめ! いい加減な整備しやがって!」
そう言えばグローブボックスに車検証と自賠責の領収書が入っていたはずだ。
そこにはにっくき仲里オートの電話番号が載っている。呼びつけてクレーム修理させてやる!
健一郎はグローブボックスから書類を掻き出すと携帯をとりだした。
「仲里オートです」
携帯に出た仲里の声はいつもと同じようにぶっきらぼうで、どこか不機嫌そうだった。
健一郎は気圧されそうになったが
「昨日ビートルを受け取った篠原だけど?」
努めて声を強めながら健一郎が名乗ると、電話の向こうは僅かに笑ったようだった。
「やっぱりカブらせたな?」
まるで予知していたふうに仲里が言った。
「かぶ?」
「エンジンが止まったんだろ?」
それが仲里の思い描いていたストーリーであったかのように、すらすらと状況を言い当てられて健一郎はやっと声に怒気を篭めることができた。
「どういうことだよ? 整備不良じゃないのか?」
整備不良と言われて仲里の矜持はやや傷つけられたようだ。
「それはないな。カブって止まったのならドライバーの責任だ」
健一郎のことを非難しているように聞こえて、健一郎は更にむっとした。
「それは後でいーからさっさと引き上げちゃってよ。場所言うからさ」
「すまんが今ちょっと立て込んでいてな」
あの店が立て込むなんて事があるものかと内心思ったが、ふと仲里の顔を思いだして口ごもった。
「今から直し方を説明する。言われた通りにやれ」
「なんだよ? 取りにも来てくれないのかよ?」
「だから手が放せんといっている。何、簡単なことだ」
「マジかよ?」
信じられないといった様子で天を仰いだ健一郎だったが、仲里は続けた。
「納車のときにも説明したと思うが、そのビートルは電装が6Vだ。どうしたってプラグの火は小さくて、ノロノロ走っているとくすぶりやすい。オマケに今日は雨でワイパーは動くし、夕方となればライトも点ける。バッテリーには過酷な状況で、プラグの火は一層小さくなる」
仲里の言葉はどちらかというと説明口調で、なかなか手順の所まで話が進まない。
「雨で湿度が上がってガスが濃くなると、ガソリンでプラグが湿ってそのうち火が飛ばなくなる。これがプラグの「カブリ」と云う今の状況だ」
そこで一旦言葉を切った仲里は、グローブボックスの奥を見ろと言った。
健一郎が見てみると掌に乗るくらいの小さな金属製のケースが入っている。
「どうせカブらせるだろうと思ってスペアを積んでおいた。交換しろ」
金属製のケースの中には新しい点火プラグが4本、綺麗に並べられて入っていたのだった。
電話でレクチャーを受けながら健一郎はボンネットを開けてスペアタイヤの中にセットされた工具を取り出し、リアフードを開けてプラグを交換し始めた。
右奥のプラグを交換するためにはエアクリーナーを外す必要があったが、それでも現代車に比べれば格段に楽だ。
苦心の末プラグを抜いてみれば、確かにカーボンで黒く煤け、碍子(がいし)の色も判別できない状態である。
健一郎は新しいプラグをねじ込む。
雨脚は弱まることなく健一郎の体を濡らしつづけていたが、もう健一郎は気にしなかった。
「それでは運転席にまわってエンジンを掛けろ。チョーク全閉、アクセル全開」
プラグ交換が済むと、仲里がそう指示する。
スターターを祈るような気持ちで押すと、4~5回のクランキングの後に盛大な黒煙をぶちまいてビートルが息を吹き返した。
「……やった……」
呆然としながら健一郎が呟く。
「ご苦労。ちょっと回し気味に走ってカブらせないように気をつけろ。スペアプラグはもうないからな」
それだけ言って仲里の電話は切れた。
健一郎はアクセルを吹かした。
ボボボ…という湿った音は次第に乾いた音に変わっていった。
初めて健一郎はビートルが言うことを聞いてくれたような気がした。落ちこぼれの生徒を導く教師ってのはもしかするとこんな心境なのかもしれない。
「世話焼かすんじゃねーよ、このバカたれが……」
健一郎はそういって苦笑した。
だがしかし、その笑顔はどこか優しげだった。
EPILOGUE
きっかけは小さなことだったかもしれない。
それを運命とまで言い切れるか否かは人それぞれだろう。
健一郎が自分でも意外だと言っているが、ビートルはその後も健一郎の足として走り続けていた。
平坦なクルマ人生だとは口が裂けてもいえない。
今まで当たり前だと思っていたものが、当たり前でないことに気付かされる。
キーを捻ればエンジンがすぐに掛かる、何時如何なる場所でも無表情に走りつづける現代の国産車とは違う乗り物なのだ。
天気や走る場所によってさえビートルはその表情を変える。クルマの声が聞こえない人間には到底扱うことの出来ない側面を知ったとき、健一郎に初めてこのビートルとの対話を楽しむ余裕が生まれた。
「お前なら解ると思ったさ。爺さんそっくりの目をしてやがるぜ」
仲里は健一郎にそう言った。
実は健一郎がビートルに乗り始めて1年ほど経った頃、ビートルを買いたいというマニアが健一郎の前に現れた。
健一郎のびっくりするような値段を提示されたが、結局健一郎は首を縦には振らなかったという。
「あれほど嫌がってたのに、何なんだろうねぇ?」
由希子が苦笑する。
健一郎も笑った。
健一郎は理解したのだ。この思いを受け止めると言うことは祖父の愛した世界を受け継ぐことでもあることを。
それは何物にも替える事の出来ない遺産相続であった。
完