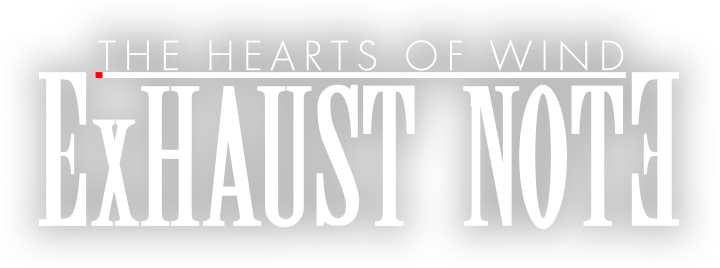novels
カゼノユクエ
1.
昼過ぎから始まった会議がようやく終わった。
会議室のブラインドが巻き上げられると、太陽は足早に西へと急いでいるかのように色づき始めていた。
林立するオフィスビルの壁面を赤みを帯びた陽光が照らし、飾り気のない無味乾燥な会議室をオレンジ色に染め上げる中、スーツ姿の影は一人、また一人と資料をまとめて言葉少なに退出していく。
早くも人影がまばらになった会議室で、ややトーンの高い声が私の名を呼んだ。
「あー、木之元くん。ちょっと」
議長を務めていた笹川専務に声をかけられて私は振り向いた。
「はい。なんでしょう?」
私は資料を小脇に抱えてまさに会議室から出て行こうとする足を止め、忙しくノートパソコンのキーボードを叩く笹川専務の席へと方向転換した。
専務はノートパソコンの画面から目を離して私を見た。今年48歳になる笹川専務は、某大手銀行から引き抜かれたと噂されるエリートで、触れれば斬れそうな鋭い空気を纏っている。オールバックにした髪から額に垂れる一筋の髪と細い銀縁の眼鏡が特徴的な、痩せぎすの男だ。
彼と向かい合うと誰でも自然と自分の姿勢が正しくなっていくのだろう。
直立不動で私は彼の言葉を待った。
笹川専務はやや神経質そうな表情をふと緩めて
「いや、なに。今晩、飯でもどうかと思ってね」
と何でもないような口調で言った。
ざわり、と自分の中で何かが動くような感触がした。もしかしたら顔色が少し変わったかもしれない。
けれど私は努めて平静を装って即答した。
「はい。よろこんで」
専務は頷いて「では7時にロビーで待ち合わせよう。構わないかね?」
「わかりました」
私はざわざわと波立つ胸中を悟られぬよう、ひとつ会釈して足早に退室した。
廊下を歩きながら考える。
さて、これはどう見るべきだろうか。
勤続十二年で課長というのはこの会社ではとりたててエリートコースというわけでもないが、まずまず順風といったところだろう。
大学を卒業してからはひたすら仕事に打ち込んだ。
中学から大学まで続けていた剣道は就職と同時に綺麗スッパリやめてしまった。今の会社に剣道部がなかったこともあるが、今となっては竹刀の柄よりゴルフクラブのグリップを握っているほうが性に合っているような気がする。
趣味といえば昔から釣りが好きだったのと、一時期オートバイにはまったこともあったが、これも乗る時間がなくて今ではまったく乗っていない。
第一この年齢になったらオートバイになんて乗れっこないのだ。
事故を起こして怪我で入院でもした日にはどうなるか分かったものではない。責任云々ではなく、何週間も休まなくてはならないとなったら戦力外通告必至だ。
私はそうやってこの十二年を走り抜けてきたし、それなりに自分はできている……と自分では思っている。社にとっての私という存在がある程度認められてていいんじゃないか、とも思っている。
とはいえ、会社という大きなシステムの中で自分という個人がいったいどれほどの存在価値があるものなのかは、私には推し量ることができなかった。
査定は一定の目安にこそなれ、どうしても私にはそれが社内における純然たる労働力の評価程度にしか思えてならないのだ。
一個の人間たる、木之元隆にしかできない仕事もたくさんあったのだと、果たして会社は見てくれるのだろうか。
だとすれば34歳という年齢を鑑みるに、もしかしたら部長……という事はまずないとは思うが、部長補か、副部長あたりなら強(あなが)ちあり得ないとも言い切れまい。
あまり期待してくだらない用件だったら失望も大きいので、私はあらぬ夢想はそのあたりでやめにした。
逆のことも考えたが、特に大きなポカをやらかした記憶はないから(小さなものは多少あるにせよ)、譴責(けんせき)……はないと思う。
「鬼が出るか、蛇が出るか……」
そう一人ごちて私は我が城、営業ニ課室へと入った。
私は自分の席に戻って先程の会議資料をゆっくり読み返す。
一時期ひどく落ち込んでいた業績は、大リストラの結果何とか採算ベースを持ち直し、今は緩やかに上昇中。
その時のリストラで経営陣がほぼ刷新され、確かに経営基盤は頑強になった。だが昔からあったのびのびとした社風は失われ、いつも気を張り詰めていないといけないような、どこか息苦しい会社になってしまったのも事実だった。利益集団としては至極正しい姿なのだが、昔の社風を知る最後の世代である私などから見ると、つい「昔は…」などと言ってしまうのだった。
そう、昔はこういう会議から帰って来ると女の子がお茶などを淹れてくれたものだが、今やお茶もセルフサービスときたもんだ。
味気ないもんだな…などと思いながら給湯室でお茶を淹れようと思ったら、ポットのお湯がすっからかんだった。
小さく舌打ちをしながら、ポットにミネラルウォーターを注ぐ営業課長。
激しく鬱だった。
それから約束の時間まではやけに長く感じた。
事あるごとに腕時計をちらちらと見ながら、進まぬ針に少しばかりの焦燥を覚えた。
そして6時45分を時計の針が示す頃。
『笹川専務との会食後直帰』
ホワイトボードにそれだけを書いて課員が戻りつつある営業二課室をあとにした。
ここから待ち受けているのは栄耀栄華を約束する天国への階段か、それとも冷たく黝(かぐろ)い闇黒(あんこく)の地獄へ連なる洞穴(ほらあな)か。
私はまさに最後の審判を受ける科人(とがびと)のような心持で、1Fロビーへ向かった。
ロビーに着いたとき、時計の針は6時55分を指していた。帰りを急ぐ社員や、外回りから帰社してきた社員が2、3人ほど散見されるだけで、ロビーはがらんとしていた。
受付席の女の子たちが受付席を閉める準備を始めていた。
ロビー奥の控え室から鍵を持ったガードマンが出てきて、正面玄関横で直立不動の姿勢のまま7時の時報を待っている。7時になると同時に正面玄関を施錠しシャッターを下ろすためだ。
ロビーの大時計が6時57分を指す頃、笹川専務がエレベーターから姿を現した。引き上げる準備をしていた受付の女の子二人が姿勢を正して深く腰を折った。
もちろん私もそれに倣うようにお辞儀をした。
笹川専務は軽く手を上げて、
「待たせたようだ。早速出かけよう」
そう言って直立不動のガードマンたちの前を通り過ぎて玄関を出た。遅れぬように私もその後を追った。
笹川専務は表通りに出ると停まって客待ちをしているタクシーに軽く手を挙げた。
するすると音もなくやってきてドアを開けたタクシーに乗り込む専務に続いて、私もタクシーの後部座席に潜り込んだ。
「何か苦手なものはあるかね?」
タクシーのドアが閉まると、笹川専務はちらりとこちらを見遣って訊いた。
「いえ、特には……」
とっさに答えた。
専務は、ふむ…と一瞬だけ考え、「築地の『橘(たちばな)』へやってくれたまえ」とドライバーに告げた。
ちょっと待て。『橘』といったら政治家・官僚御用達の店で芸妓が呼べる程の超高級料亭ではないか? 営業職について12年、接待の席は数限りなく設け、また受けてきたものだが、流石に『橘』ほどの店を利用したことはない。そもそも経費が認められるような店ではない筈だ。
僅かばかりの加速Gにシートへ押し付けられて思考が現実に戻った。
陽は既に落ち、星の見えない暗黒の空を背景に、幾重にも重なったビルの光が銀河のように車窓を彩って流れていた。
私は気づかれぬように専務の横顔を見ていた。
いつものように超然と、まっすぐ前を向いていたが、不意にこちらを向いた。反射的に一瞬目を逸らそうと首の筋肉がピクリと動いたが、私は専務の視線を受け止めることに成功した。
「なに、ただの会食だよ。会席料理なら気兼ねすることもあるまい。勿論支払いについては心配しなくていい」
専務は頬を緩めたが、細い銀縁メガネの奥の瞳の色は、暗い車内の中で杳(よう)として知れなかった。
ひたすら気まずい時間が車内を覆っていたが専務は特に気にする風でもなく、今は窓外を見るとはなしに見遣っている。この雰囲気は何とかしたかったが、普段専務とは仕事以外に話をすることもなく、飲み会というイベントで専務と腹を割って話すような事もついぞなかったので、何と切り出してよいのか思い悩むうちにとうとう話をする機会は失われた。
二人を乗せたタクシーが目的地に到着したのだ。
僅かな減速Gがかかってドアが開いた。
私と専務は静かな路地に降り立ち、タクシーは紅いテールライトを闇に曳きながら走り去っていった。
純日本風の門構えに小さく「橘」の看板が見える。
まさか自分がこんなところに来ることになろうとは夢にも思わなかった。
どこか別次元の世界のような、浮世離れした空気が私の足を重くする。
「さぁ、行こうか」
笹川専務はそういって門をくぐる。
私は恐らく社会人一年生のような面持ちで専務について行ったに違いあるまい。
おのぼりさんに見られてはかなわないので、できるだけ周囲を見ないように歩いたが、果たしてどこまで巧くいっただろうか。
玄関をくぐると女将だろうか。日本髪を結い上げた和装の女性が楚々とやって来て「ようこそおいで下さいました」と三つ指を立てて伏した。
気後れしそうになるのを堪えながら私は専務の一挙手一投足を真似て蹴上を跨いだ。
女将に先導されて縁側を歩くと控えめにライトアップされた日本庭園が見える。階段を上がり2階に通された専務と私は、座敷へと案内された。
いかにも上等そうな水墨画の描かれた掛軸、杜若(かきつばた)らしい活けられた花も気品を感じる作品だが、あいにく私にはその価値は知るべもない。
「まあ、座りたまえ」
そう笹川専務に勧められた席は上座であったので流石に丁重にお断りした。
二人が腰を下ろすと、計ったように仲居が入ってきて音もなく配膳を済ませる。
専務が仲居にいくつか指示を与えると、ビアグラスになみなみと注がれたビールが給された。
「まずは乾杯といこうじゃないか」
専務はそう言ってグラスを掲げる。
私も倣ってビアグラスを持ったが、まるで手に吸い付くような冷たさであった。
涼しい音を立てて二つのグラスが重なり、私はビールを喉に流し込んだ。ちょうどいい具合に冷えたビールだったが、これほど味を感じないビールは初めてだった。
専務はふと笑った。
「なんだ、まだ緊張が取れないかね? こういうところを一度経験しておくのも悪くないだろう?」
「は」
私は引きつるような笑みを浮かべてそれだけ声に出すのが精一杯だった。
終業までの短い時間にいろいろと会食の会話をシミュレーションしておいたのだが、この雰囲気に完全に呑まれて何一つ頭の中から言葉は出て来なかった。
「まだまだ硬いな。なに、ただの会食だよ」
専務相手にどっしり落ち着いて構えてなどいられるはずもない。
専務のグラスが半分ほどになっているのを見つけて慌ててお酌をしたが、専務は「まぁ、君もやりたまえ」と勧めてきた。
もう私は半ばやけっぱちになってグラスを空け、頂戴したのだった。
しばらくすると先附が給された。
梅肉を添えた白魚とすくい豆腐、見事な包丁細工の野菜が少々。
専務は箸を取ると白魚に舌鼓を打った。
私は箸を取らずに「それで、専務?」と訊いてみた。流石に裏も取らずに料理に手をつける気にはならなかった。
「まぁ、食いながら話そう」
専務はそうはぐらかした。どうやら拒否権は無いらしい。
私も白魚に手をつけたが、勿論味など分かりはしない。家に帰って温かいご飯に縮緬雑魚(ちりめんじゃこ)でもかけて食べたほうがよっぽど気が休まって美味しいだろう。
吸い物が出てきた。
小さな鶏肉が3切れほど入った、ふうわりと柚子の香りのする吸い物だった。
やはり無言で吸い物をすする二人の間に、一種異様な緊張感が横たわった気がした。
「専務は……」
「ん?」
私は沈黙の重さに押しつぶされそうになりながら訊いていた。
「専務はよくこの店を利用されるのですか?」
当たり障りのなさそうな話題としては妥当なところだろう。専務は頬に笑みを刻んだが、私にはそれが苦笑に見えて頭から離れなくなった。
「そうだな。たまに利用するな。とは言え通いつめられるほどのサラリーはないがね」
謙遜に違いあるまい。さて私は勝ち組だろうか、負け組だろうか?
向付として刺身が出たところで専務が「ではそろそろ本題に入ろうか」と私を見た。
専務は周囲を見回し、人の気配のないことを確認してから声を落として「これは内々の話なんだが……」と切り出した。
「指宿(いぶすき)細密電子……と言うメーカーを知っているかね?」
私は頭(かぶり)を振った。指宿……人名か、そうでないなら地名らしいが私には記憶になかった。
専務は特に気落ちした様子も、馬鹿にした様子もなく応えた。
「ま、今は九州の小さな工場だから知らないのも無理はないが……。これまでは半導体やICチップの製造を主な業務にしていたんだが、アジアの低価格競争に巻き込まれて業績は苦しかったらしい。その指宿細密電子の株式70%をわが社が買い付けることが先日決まった」
「持ち株子会社に……ですか?」
「そうだ。この件に関しては先方の役員会議で了承を取り付けてある。いわゆる友好的TOBと言うヤツだな」
「M&Aの目的は何なんですか?」
業績の芳しくない会社を買おうと言うのだ。当然裏があるだろう。
「指宿細密はそれまでの技術をナノテクノロジーへ移行することで業態を変更することになった。今までも基礎研究を重ねていてそれなりの収益が上げられる目処がついた、と言うことだろう。社名も変更し、全く新しい会社に生まれ変わるだろう。本社としてはナノテク関連への足がかりが欲しかったと言うわけだ」
そこまで喋ると専務は鯛の刺身に山葵をのせてたまり醤油につけ、口に運んだ。
「ふむ。流石に築地だけあって旨い。君も食えよ」
私も専務に倣って烏賊の刺身に手をつけた。専務十八番のはぐらかしだが、私は辛抱強く次の句を待った。
「そこでだ」
専務の声とともに、ざわりと私の中で何かが蠢いた。さあ、来た。ここが本丸だ。
「指宿細密は従来の業務を即座に停止する気はないらしい。少ないながらにクライアントはあったようだからな。彼らのサポートはメーカーの責務と言って聞かないので本社も規模を縮小しながら存続を決定した」
私の背中を冷たい汗が転がり落ちた。
「で、本社から誰か出向できるものを探していたんだが、君に白羽の矢が立ったという訳なんだよ」
2.
春というにはまだ寒さの残るこの時期、暖房は微かに効いているだけだったが、その瞬間私の体からどっと汗が噴き出した。
「私が……ですか?」
やっとの思いで絞り出したその声から動揺は隠しおおせなかった。
笹川専務は中指で眼鏡をついと押し上げた。
「君には少々気の毒だとは思っている」
感情の見えない専務の声が聞こえる。
「指宿細密はサポートについていつまでと言う期限を設けていない。それはつまり指宿側の条件と言うわけだ。もしかしたら君にはかなりの期間向うにいてもらうことになるかも知れん」
「……理由をお伺いしても?」
「君が選ばれた理由……かね?」
私はゆっくりと首肯した。
この出向を受ければ私は出世街道から遠ざかるのは確実だ。いつ中央に帰って来る事が叶うことか。帰ってきたとしてもこの九州への出向がプラスになるとはとうてい思えない。しかし理由もなしに断れば上層部から睨まれるのは必至。
ここで一発逆転を狙うなら正当な理由をもって粉砕するしかないのだ。
専務は頬に苦い笑みを浮かべた。
「いや、人材の不足だよ。こういう責務を果たすことができる人間というのは残念ながら社には多くない。君ならできると私がふんだんだがね。それに君は独身だし、寮住まいだ。確か独身寮は35歳までだったし、君も新しい住居を探さねばなるまい? あちらには社宅があるし、双方にとってもいろいろ好都合だと思ったんだが」
視界が真っ暗になって目がチカチカした。
確かに課長クラスになると独身者は私一人。単身赴任に適任と考えられても無理はない。しかも選抜したのは笹川専務本人なのだ。きわめて合理的なこの意思を覆すことは専務に弓を引くのと同義といっても過言ではない。
「君には本社マーケティングディレクターとして部長付きシニアアドバイザーの席を用意した。指宿細密には現在の部長がそのまま現地スタッフの最高責任者として残る予定だが、彼をリードしてやってくれないか?」
また微妙な役職名が出てきた。部長補でも副部長でもなくアドバイザーか。リードねぇ。
本社としては子会社には本社からの出向者を上に立てておきたいが、指宿何たらは本社にそこまで実権を握られたくはない……と言うところか。
お飾りのアドバイザーなんていう実質的に発言力のないポストを用意した……と言うのは穿(うが)ち過ぎか?
一瞬血流が頭に集中したがすぐに霧消し、変わりに恐ろしいほど冷静怜悧に頭脳が回転する。
笹川専務がふと笑った。
「まぁ、急な話で申し訳ないね。辞令が下りるのは春だし、君にも色々と時間が必要だろう。有給などは優先的に取られるよう配慮するから」
「は……」
私はそれだけ言うのが精一杯だった。
有給休暇をとって速やかに準備を始めなさい、と言うことだな。意外だがそれなりに気配りに長けた人のようだ。この会席の意味もわかった。なるほど、最後の晩餐と言うヤツか。専務は専務で多少なり罪の意識を感じている……というアピールな訳だ。
はは……
私は表情を崩さぬように自嘲した。
十二年間、すべてを犠牲にして働いた結果がこれとは。
私は大きく息を吸った。
気分を落ち着けるように、胸に去来する様々な思いを胎(はら)の底へと押し込めるように。
「分かりました。確乎不抜(かっこふばつ)の志で事に当たらせていただきます」
私はそういって深々と頭を下げた。
それからどれくらいの時間が経ったのだろう。
夜は更け月は既に沈んでいたが、暗夜に不夜城・東京の光が地上に星を燦々と輝かせていた。
会席でその後何が出てきたのか、実はあまりよく憶えていない。
専務の話だって半分くらいしか頭に入ってはいなかった。
支払いの時にぎょっとするような枚数の紙幣が見えたが、勿論口には出さなかった。ただひとこと、「本日はご馳走様でした」と頭を下げた。
おそらくこれは会社ではなく、専務本人の心づくしなのだろう。ドライな切れ者と言うイメージが先行しがちだが、今日の口調からはそう感じ取れた。
専務は黙ってうなずいた。
そうとも。何もこれで人生が終わった訳ではない。些細な、本当に些細なことで遠回りするだけだ……と、自分に言い聞かせるほかない。
そして、音もなくやってきたハイヤーが二人の前に停まった。
「東京駅まででよければ送ろう。どうかね?」
開いたドアを一瞬見遣って専務は訊いた。私は頭(かぶり)を振った。
「ありがとうございます。ただ、一人で少々考えたいこともございまして……」
専務は私をじっと見つめ、小さく首肯した。
専務を乗せたハイヤーが静かにドアを閉め、微かなエキゾーストノートと共に走り去った。私はそのテールライトの光が見えなくなるまで深く礼をした。
私はひとつ溜息をついて、ゆっくりと夜の東京に向かって歩き始めた。
雀の声に私はふと我に返った。
昨日あれから結局寮まで歩いて帰ってきてしまった。帰り着いたら夜中の2時を回っていた。
部屋に戻った私はコップ一杯の水を飲んで、カウチに腰掛けてそのままぼんやりと過ごした。少し微睡(まどろ)んでいたのかもしれないが、休んだという実感も記憶もまるでない。頭の芯の痺れる様な強烈な倦怠感と違和感が私の体を鉛のように重くする。
視線を巡らせて掛け時計を見ると6時を回ったところだった。
頬をぴしゃりと打って、私は体を起こした。いつもより早い時間だったが、熱いシャワーでも浴びないことには体が目を醒ましそうになかった。
熱めのシャワーを浴びてから朝食を摂った。と言っても食欲なんてこれっぽっちもなかったから菓子パンをひとつ、ホットコーヒーで流し込むように食べたきりだったが。
時計を見遣ると結構いい時間になっていたので手早く用意と身だしなみを整えて部屋を出た。今から日常が始まるのだ。気分を切り替えなくては。
そうして出社した私は社内の空気が昨日に比べて異質なことに気が付いた。
最初私は自分があのような話を聞いた所為だと思ったのだが、どうやら違うらしい。特に私一人に向けられたものではなく、その違和感はどうも全社的に漣(さざなみ)のように広がっていたのだ。
どこか浮き足立っているような、困惑しているような、何かを懼(おそ)れているような、そんな微かな空気が流れていた。
私はその空気を気にかけながらも我が城、営業二課室に入って「おはよう」と挨拶をした。
「おはようございます、木之元課長」
出入り口近くでコーヒーを持った工藤係長が紙コップをひとつ私に差し出した。
「あ、ああ。ありがとう」
そう言ってコーヒーを受け取った。
「なかなか大変なことになりましたね」
工藤君は自分のコーヒーをすすりながら近くにあったデスクトップPCの液晶モニタをこちらへ向けた。
メールで回ってきている社内報が表示されていたが、ヘッドラインとして一部経営陣の謹慎が告知されていたのだ。
「?」
私はマウスを持つとスクロールホイールをゆっくり回していった。
読み進めていくうちに私はまなじりがひくひくと痙攣していくのを自覚した。
「笹川専務取締役に特別背任の疑い?」
「ええ」
工藤君はそう言って画面の一部を指差した
「何でも一部の幹部と結託して某社の株式を大量に購入した疑いがもたれているようです。会長以下首脳陣は内々で処分を検討しているようですね」
「なん……だって?」
私の頭は真っ白になりそうだった。胃が痙攣して裏返りそうな錯覚を憶えると共に、冷たい汗が首から上だけどおっと噴出した。
私はひょっとするととんでもない泥舟に乗せられたのかもしれない。
私は急いで自席に座ってPCを立ち上げた。
パスワードを打ち込むのももどかしく、デスクトップが現れるのを待った。
メーラーを立ち上げると私宛にいくつかメールが届いていたが、「緊急」と件名が付いているメールが一件見つかった。
メール件名は最優先事項と続き、内容は簡潔極まりなかった。
「木之元隆殿 出社次第至急社長室へ出頭せよ」
送信者は海老名社長である。
私はじとりと口の中一杯に拡がる酸味を嚥下しながら、PCの電源を落として社長室に向かった。
予想通り社長のテンションは最悪に近かった。
とは言え、私は何一つ知らされておらず、昨日初めてそういう話を聞いたという点は理解してもらわねばならない。
社長によると指宿細密は笹川専務が銀行に勤めていた頃からの顧客なのだそうで、笹川専務は今までもいろいろと便宜を図っていたらしい。
私は笹川専務から指宿細密についての話を昨日初めて聞いたことを強調し、利益関係のなかったことを伝えたが、ついに社長の表情はすぐれぬままであった。
「君の勤務態度は聞いているよ」
海老名社長はそう切り出した。
「実によく頑張ってくれている。私としても君にはここでもっともっと頑張って欲しいと考えている。……がだ……」
海老名社長の頬に苦い笑みが僅かに広がって……そして床の一点へと視線を落とした。
「こういった醜聞というのを手薬煉(てぐすね)引いて待っている人間が社の内外にいる。彼らを暗黙のうちに納得させるためにもおそらく君にも何らかの処分(ペナルティー)が科せられるだろう。どの程度まで譲ってくれるかどうかはまだ判らんが、何とか軽微に済むように働きかけよう」
海老名社長はそういって私の肩をぽんと叩いた。
「すまん」
そうして私は社長室から解放された。
私はそれから終業までの間、何か腑抜けたように仕事を続けたのだった。
翌日、社内回覧が回ってきた。
そこには笹川専務の懲戒免職と連座した幹部たちの解任と減俸、そして私の指宿細密への転籍が記されていたのだった。
3.
何日かが慌しく過ぎ、綺麗さっぱり片付いた席の前で私は一枚の紙切れを眺めていた。
『辞令』と書かれたその紙切れにはそっけなく、「木之元隆殿 右の者、指宿細密電子株式会社へ部長付きシニアアドバイザーとして転籍を命ず」とだけ書かれていた。
私は辞令を蛍光灯に透かして見た。
何とも薄っぺらな紙切れだ。
こんな紙切れ一枚で私の人生は大きく変わってしまうのかと思うと情けなくもなる。
結局指宿細密はM&Aにより完全子会社化し、笹川専務以下首謀者たちはクビになり、私はとばっちりで指宿細密に片道切符で飛ばされることになった訳だ。
笹川元専務の独断とは言え社としての契約は有効とみなされた格好といえるだろう。
元専務は職を失したが、それなりの見返りはあったのではないだろうか?
結構なことだが、事情も何も知らされずにいきなり島流しに遭う私は一体誰が救ってくれるのか?
不条理な話だった。
「今回の件は全面的に君は被害者だと思っている」
海老名社長はそう言った。
「給与面ではできるだけ考慮したつもりだし、中央への復帰も力を尽くそう」
それがリップサービスであろう事は勘と経験が裏付けていた。
明日から私だけの2週間の有給休暇が始まる。
休暇といいながらこの転居は社命であるから何のことはない。
この2週間で身の回りの整理をつけて鹿児島へ発たねばならない。
独り身の寮住まいが、向こうでは社宅に変わるだけで特に気遣う必要がないのは有難かった。
とりあえずは部屋の荷物を業者に依頼して社宅に送ってもらう手続きをとるのが最優先事項だろう。
あとは転居届けも出さねばならないし、役所回りも結構時間がかかりそうだった。
寮のお隣さんくらいには挨拶にも行かねばならないだろうし、作業をメモに書き出したらメモのスペースが足りなくなったほどだ。
私は微かな溜息をついた。
不意に営業二課のドアをノックする音がして、私はそちらへと視線をめぐらせた。
私と同期で入社した葛西であった。
営業一課の課長補を務める彼は、私の同じ大学の出身ということもあってたまに呑みに行く間柄だった。
私を見つけた葛西はにやりと笑って顎を軽くしゃくった。
どうやらついて来いという事らしい。
どうせもう今日が済んでしまえば出立の日までこの部屋に来ることはないのだ。私は首肯して葛西についていった。
葛西は社員食堂に隣接する喫茶室に案内した。
この時間人気はなく、喫茶室に居るのは我々二人だけだった。
葛西はサーバーからホットコーヒーを二つ買うと、ひとつを私に手渡した。
「餞別。俺からの」
そういってウインクした。
私は苦笑混じりに受け取った。
葛西は棚から灰皿を一つ掴んで適当なテーブルの席に付くと、懐から煙草を取り出した。
学生時代から両切りのHOPEなんてキツいのを愛飲しているヘヴィスモーカーには、今や社内に居場所がここにしかないのだった。
「まずは栄転おめでと~」
葛西はオチャらけてそう言ったが、その目は苦渋に満ちている。
私から知らず発散されているであろう、重苦しい空気をなんとかしようとしているその態度を私は責める事が出来なかった。変に同情されても辛いところではあったので、いくばくか気持ちが軽くなったのも事実である。
「こりゃどうも。菅原道真の気分だけどね」
葛西はこれまた学生時代からずっと使い続けているZippoで煙草に火をつける。
紫煙が細く長く吹き出され、霧散した。
「……まったくだ」
葛西は吐き捨てるように呟いた。
今回の処分におそらく最も納得していないのは葛西かもしれない、と私は思う。
学生時代から曲がったことが嫌いで筋の通らないことには頑として首を縦に振らない性格だった。その性格が災いしてか、能力的には私よりむしろ上であるにも拘らず、課長補に甘んじている。
彼も独身だったはずだが、彼に声がかからなかったのはその扱いにくさ故だろう。
「俺も今回は自分の脇の甘さを認識したよ」
私は自嘲気味にそう言った。
葛西は私の肩をぽんぽんと叩き、
「ま、いまさら嘆いても仕方ないさ。それに今生の別れっつー訳でもないから実はあまり心配はしてないけどな」
にやりと笑ってそう言った。
その気になれば何時だって連絡は付くし、ちょっと休みがあれば会いに行くのも難しい話ではない。そういう意味で言ったのは理解っていたが、私には少々堪える言葉だった。
「そうだな」
私はそれだけ応じて熱くて苦いコーヒーを飲み込んだ。
葛西も私の余裕のなさに気づいているのか、殊更話を変えるようにいった。
「そういえば入社したときに同期の連中で倉庫を借りただろ? 荷物が多すぎて独身寮に入らないものをみんな押し込むために……」
「……ああ」
言われてみればそうだった。
毎年、年度初めに倉庫代を徴収されていたのを思い出す。継続して借りるならそろそろ払わねばならないが……来年からは私の分は要らない筈だった。
「そうだな。倉庫の中身を処分して、来年から私の契約を解除してもらわないとな」
葛西は頭をぼりぼりと掻いた。
「それもあるが、中の荷物どうする? ある意味お前さんの荷物が一番かさばるんだが……まさか何倉庫に入れたかくらいは覚えてるだろうな?」
そういえば仕事が忙しくなって荷物を持ち込んだ日以来足を運んでいない。たしか……
「大学時代にお前が乗ってた単車だよ」
葛西は煙草の灰を灰皿に弾き落とした。
「あ……」
私はすっかり忘れていた。
単車に乗っていたという記憶はあるのに、その記憶の重要度が日に日に下がってしまっている自分に気づいた……というべきだろうか。
あれほどの熱意が、徐々に冷え固まって澱(おり)となって記憶の海に沈んでしまったかのようだった。
それまで400ccの国産アメリカンに乗っていた私は大学4年の時に一念発起し、バイトで貯めた金をはたいてハーレーダビッドソン 883スポーツスター「ハガー」を個人売買でようやく手に入れたのだ。
そして東京の交通事情を目の当たりにした私は入社の日、いつか乗れる日を夢見て883を倉庫に仕舞ったのを、もう何年も忘れてしまっていたのだ。
痛恨だった。
ほんとうに、この十二年は、いったいなんだったのだろう?
「そうだったな……」
私は天を仰ぐように首をそらした。
「分かった。明日にでも片付けに行くよ。危うく忘れるところだった」
「そうしろ」
葛西はコーヒーを飲み干すと私の肩を叩いた。
「何か困った事があったら携帯に連絡しろよ。身体にだけ気をつけてナ」
葛西はそれから紙コップをダストシュートへ放り込み、喫茶室を出て行った。
最後の言葉は激励の言葉でも慰めの言葉でもなかったが、今の私にはそれが一番ありがたかった。
次の日、私は倉庫に向かった。
倉庫の鍵は共同で借りた人数分だけ用意されていたので私も持っているはずなのだが、もうどこに仕舞ったのか分からず、部屋を探し回る羽目になった。
出てきた鍵も果たしてこれで合ってるのか不安である。
倉庫は独身寮からそう遠くない、歩いて10分ほどの距離にある。
だが、私は倉庫に行った記憶がほとんどなかった。
無事倉庫に辿り着けるか不安でさえあったが、やや古ぼけた倉庫は私の記憶どおりに下町に溶け込んでいた。
私は倉庫のシャッターに鍵を差し込んで回した。
少し引っかかったが、カチャリという音と共に扉は訪問者を受け入れた。
私が忘れていても鍵は忘れない、ということか。
シャッターを開いた。
途中で渋いところが何箇所かあったが、派手な音を立てて薄昏い闇が口を開けた。
シャッターのボタン近くにある灯りのスイッチを入れると、暫くちらちらと明滅した蛍光灯が寒々しい光を放った。
倉庫特有の黴臭いにおいが微かに鼻についたが、私は気にせず最奥を目指した。
確か当初5人で借りたはずだが、今はもう3人だ。
私の記憶の中ではもっとごちゃごちゃと荷物が詰まれている映像がフラッシュバックしたが、今眼前には少なくとも棚にきれいに収まるだけの荷物しかなかった。
そんな中でもっとも大きな荷物が、倉庫の一番奥にあるサイクルカバーをまとった物体だった。
その近辺だけが異様に散らかっており、永らく訪問者がないことを雄弁に物語っていた。
私は棚にかけられたジャケットとヘルメットを見遣った。
革製と思しい黒いジャケットは既に埃で真っ白で、一体元がどんなデザインだったのかさえ判然としない。
油分をすっかり失くした表面はひび割れこそなかったが、既にカチカチに固まっており、まるで革の鎧のようだった。
ヘルメットもよく似た状態だった。
クリアーシールドはもう色も変わっていて、埃を払ったくらいでは使えそうにない。
何より内装が既にやせてしまっていた。
私はヘルメットを元に戻し、一歩、また一歩とサイクルカバーをまとった物体に近づく。
カバーを止めているバックルを外そうとすると、経年劣化した樹脂製のバックルはあっさりと半分に割れた。
私はバックルの破片を捨て、銀色のカバーを持ち上げ……取り去った。
埃を被って真っ白ではあったが、とりあえず単車の形はしている。
だが、よくよく見るとフロントフォークのインナーチューブは錆に覆われ、ドライブチェーンも錆で真っ赤だった。
タイヤは見事にぺしゃんこにパンクしており、無数のひび割れが生じている。
アルミ製のP型V2エヴォリューションエンジンは、埃ではなく腐食で真っ白だ。
そのほかステーやハンドルなど鉄製の部品に転々と錆が浮き、12年と云う時間が如何に残酷かをまざまざと曝け出す。
オイル漏れとは無縁なはずのエヴォリューション4カムエンジンでさえも、その永い時間に抗えなかったのか車体の下に巨大なオイル染みを作っていた。
バッテリーは取り外されていたが、既にバッテリー内にバッテリー液はなく、完全に干上がっている。
私は目を閉じて、この883と共に走った短い時間を思い浮かべようとしたが、うまくいかなかった。
思い出せる事といえば、乗ってる時間より修理している時間のほうが長かったということくらいだろうか。
もとより個人売買で安く手に入れただけに、そのあとはひどく苦労させられたのだ。
当時私は「ハーレーはそんなもの」と言い聞かせていたものだが、疎遠になってしまったのはその当たりにも原因があるのかもしれない。
一瞬、この一見屑鉄にも見える883を処分してしまうことも考えたが、これからの新しい門出には何かしらの契機が欲しかった。
もう肩肘を張って生きる必要もないかもしれない。誰かを蹴落としたり、せかせかとする必要もないかもしれない。
だとしたらこういった単車で走ってみるのも良いのかも知れない。
すべてを犠牲にして突き進んだ、空白の12年を取り戻すために。
今私は再び自由の翼を手に入れたのだ。