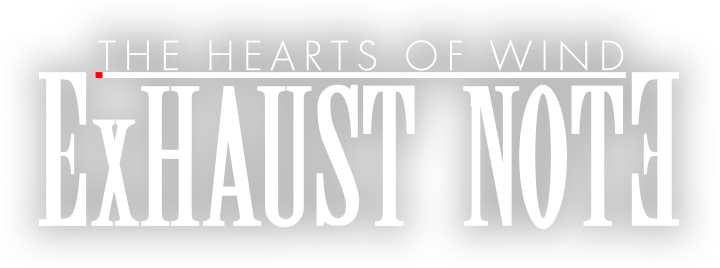novels
いつか白樺の湖畔で
プロローグ
それは、二学期の始業式の日のことでした。
式が終わって、部活も今日はお休みで午後から何をして遊ぼうかと考えていると、圭ちゃんが急に「話がある」って。あ、圭ちゃんって私のカレシのことね。
またどこかにアソビに連れてってくれるのかなって、ちょっと期待してついていったのね。 着いた所は自転車置き場。
思えば一学期、ここで圭ちゃんに告られたんだなぁ。
「なぁ、梓……」
そんな夢見心地の私を圭ちゃんが呼んだ。
「あ、何?」
私はいつもの癖で髪をくるくるさわりながら答えた。そしたら突然、
「俺達、このへんで終わりにしないか」って。
私思わず「へっ」なんて聞き返しちゃったわ。
何? 一体どういうこと?
パニクる私の頭の中をよそに圭ちゃんは、さっさとヘルメットを被っオートバイを引き出していた。
「ちょ、ちょっと待ってよ」
そんな、理由も聞かずに納得できるもんですか。
「俺の忍耐力だって限りがあるんだよ」
圭ちゃんはグラブをはめると突っ撥ねるようにそう言って、愛車スズキ・バンディットVに跨った。
「ちょ……」
一歩前に出た私と圭ちゃんの間にセルモーターの無機質な音が割って入り、400cc4気筒の乾いたエキゾーストノートが私の前に壁になって立ちふさがった。
「じゃ、な」
それだけ言うと圭ちゃんはヘルメットのバイザーを下ろして走り去っていってしまった。
「そんな……、そんなのないよ……」
私はあまりの突然の事に涙を浮かべることもできず、ただ茫然と圭ちゃんの消えた路上を見つめていた。
第一章
1
あの日から三日が過ぎた。
部活で圭ちゃんと顔を合わせても冷たくされるばかり。今までけんかしたことも少しはあったけど、これ程冷たく当たられた事はなかったのに……。
はあ……。
この切なくて哀しい気持ちが一緒に出ていってくれるような気がして、幾度も幾度もついた溜息。
授業を進める先生の声も虚ろに響いて、心は何処かに出張中。
開いた教科書とノートはあさっての場所。
圭ちゃんの顔が目に浮かぶ度に心が帰って来て掻きむしられていく。
(こんなに好きなのに……)
幾度も幾度も繰り返したこの言葉。
涙で潤んだ目を誰にも見られないように、私は窓の外へと視線を移した。
私の名は四条梓。
一月十四日生まれの山羊座。血液型はB型の十五歳。
この春に市立高校に入学したばかりの一年生。カラオケとプリクラが大好きで、トモダチとケータイが命の次に大事なふつーの女子高生。
中学のときから吹奏楽部だったから、高校でも別に何も考える事なく吹奏楽部を選んだ。
高校での部活初日どきどきしながら部室に入ったのだけれど、結構かっこいい先輩もいたりして超らっきー。
中学卒業間際にフラれちゃったけど、そんなコトどーでもいーもん。
私は高校で新しい恋を掴むんだもん、て思ったりもするんだけれどね。あーあ、あの先輩、こっちに向いてくれないかな、なんて。
「おい!」
「は、はい!」
急に先生に呼ばれてびっくりした。
「自己紹介、君の番」だって、そんなに偉そうに言わなくたっていいじゃん。
この顧問の先生とは折り合い悪そう、などという感想はとりあえず胸の内にしまっておいて、
「あ、あの……二組の四条梓です。出身中学は港第一中学校で、えと、趣味は手芸とお料理です。それから、あの……性格はよくおとなしいって言われます」
周囲を見回して、
「その、宜しくお願いします」
って頭を下げたら、「それで?」と、例の顧問が困惑したように言った。
「君一体何の楽器奏りたいの?」だって。
部室の中に小さな苦笑がさざめいた。私ってば、ぼぉっとして全然話を聞いてなかったみたい。
見ればあの先輩も笑ってる……。
「あの、フルートです」
私は赤面しながらそう言っていた。この顧問、人に恥かかせる天才だよ、全く。
あ~あ、なんかやなカンジ。ヤメちゃおかな。でも、3日くらいは続けないと三日坊主にもなれないもんね。
で、この日は親睦を深めるってゆーか、新入部員歓迎ってカンジで楽器が割り当てられた以外は練習もなくお開き。
帰り自宅をしなくっちゃってせっせと片付けてるんだけど私って人一倍ドジでのろまなのね。結局最後になっちゃった。
部室に鍵を掛けて職員室に届けて、さぁ帰ろって思ったら
「四条!」って呼ぶ声がしたの。
振り向くと何とあのかっこいー先輩が!
でもホントに私を呼んでるのかな? って回りをきょろきょろ見回してみたけれど、人気のない廊下に私達二人だけ……。
私何だか急に胸がどきどきして頬がのぼせてくるのが分かったけれど、どうしようもないよね。
「あ、は、長谷川先輩!」
やや怪しい口調だったけど何とか言葉になったみたい。
先輩はちょっとびっくりしながら、
「へぇ、もう覚えてくれたんだ。俺の名前」
もちろんですとも、長谷川圭一先輩。先輩の自己紹介だけは私一言半句たりとも聞き逃したりはしていませんから。
「戸締まり御苦労さん。送っていくよ」
だって。これって夢よね。きっと私夢見てんだ。とびっきりいい夢だからお願い! もうしばらく醒めないで!
「? 何してんだ? 来ないのか?」
「あ、はい、行きます! 今行きます!」
ああ、私ってば一体今までどんな顔してたんだろ。頬をつねってこれが夢でないことを確かめた私は俄かに顔面に血が昇るのを感じた。
私は上気する頬を殊更隠すように両手で覆うと、歩き始めた長谷川先輩の背中を小走りで追った。
先輩の足は通常の校門には向いていなかった。
私は黙ってついていったけれど、内心不安が全くない訳ではなかった。
先輩は自転車置き場で足を止めた。
「ちょっと待っててくれよ」
そう言うと先輩は自転車とバイクの列の中に割って入っていった。
先輩はその中の一台のバイクにキィを差し込んで表へ引き出して来た。
私、びっくりしちゃった。だってバイク通学可なんて聞いてなかったもの。
先輩のバイクは赤くて大きなバイク。私にはよくわかんないけど、タンクには「SUZUKI」って書いてある。何かすっごくかっこいー!
「ほれ、ヘルメット」
先輩は自分のヘルメットを私に手渡した。
「あ、で、でも、私、スカート……」
制服姿の私は当然スカートなんです。
「横に座りなよ。その長さじゃチェーンに絡むことはないと思うけど、一応マフラーの方に足を揃えて、ね」
私は手渡されたヘルメットと向かい合って、む~っと考え込んだ。先輩のヘルメットを取り上げちゃって大丈夫かな?
けれど先輩には何か別のことを考えていると取られたみたい。
「なぁ、四条……」
考え込んでる私の顔を覗きこむように先輩が呼んだ。
「お前、付き合ってるオトコとか……いるの?」
ちょっと言いにくそうに先輩の言ったその一言で私、心臓が一瞬止まりそうになったよ。
だって、それってもしかして、もしかして……。
「あ、いや、もしタンデムなんてしてるの見られてまずいオトコがいるんだったらって、ね」 大慌てで釈明する先輩に私は思わずヘルメットを取り落としかけた。
「い、いいえ! いません! カレシなんてとてもとても!」
何故か私まで大慌てで首を振っていた。
深呼吸を一つして、咄嗟に苦笑を浮かべる。やっぱりね……。
「じゃあさ、俺と付き合ってくれないか」
今度こそ私の心臓は一瞬止まっちゃった。フェイントの後の強烈なストレートパンチがクリーンヒットして、私は大事なヘルメットを落っことしちゃった。
その後どうなったのか、どこをどう帰ったのか、先輩の背中はどうだったのか、実は全然覚えてない。
確かにその日その時うんと頷いたはずだし、家にもたどり着いているからバイクの後ろに乗せてもらったことも確かなのだけれど、どういう会話を交わしたのか、どれくらいの時間だったのかまるで憶えてない。
こんな性格だから多分のぼせ上がって舞い上がってまるで上の空だったんだろうけれど、自分が何して何言ったのかわかんなくてチョット(いやダイブ)こわい。
気が付くと布団の中でじんじんする体と、息苦しさを感じるほどの動悸に身悶えしていた。
「神サマ、これって嘘じゃないよね。夢じゃないよね」
布団を被って闇の中で呟いた。そうすると頬が緩んでどうしようもなくだらしのない笑みがこぼれてしまうのだった。
次の日から私と長谷川先輩の恋が始まった。いや正確には出会ったその時から始まっていたと言うべき?
そして私は学校が大好きになった。もちろん放課後の部活が楽しみなんだけどね。
あ、ここで先輩のこと紹介しとくね。
先輩の名前は長谷川圭一。七月六日生まれの蟹座で、血液型はAB型。すっごく優しくてその上冗談が超おもしろいの。責任感も強くてとっても紳士なカンジ。
実際よく単車の後ろに乗せてもらうんだけど、運転がホント優しいの。ホラ、よくいるじゃない? ハンドル握ると性格の変わる人って。ハンドル握ると化けの皮が剥がれるみたいでちょっとヤじゃない?
そーゆーのって。
その点先輩は常に歩行者を気遣ったり、いつでも穏やかってカンジで私もちょっと鼻がタカいよね。私の目に狂いはなかったのね! なぁんて。
それに長谷川先輩はけっこー行動力があって頼もしいんだぁ。
免許取るのに掛かった費用とかバイク関係の出費なんかは、全部自分で働いたお金で払ってるんだって。バイクも親に買って貰ったんじゃなくて、自分で貯めたお金で買ったんだって。偉いよねー。私、尊敬しちゃうよ。私だったらゼッタイ親にねだってるモン。
だから私はますます長谷川先輩が好きになってた。
そんな幸せな時間が一月、二月と続いた。
夢を見るように短い時間は夏休みの終わりまで続いた。
短いその間に変わったこともあった。
バイクのリアシートが私の指定席になったコト
「長谷川先輩」が「圭ちゃん」に、「四条」から「梓」に呼び名が変わったコト
念願のロストバージンを果たしてからは、週に二日はえっちするようになったコトなどなど……。
その間圭ちゃんは不満一つ漏らさなかったし、そんな素振り一つ見せなかった。いつだって私の前では微笑んでいてくれた。
なのにあの日突然「別れよう」だなんて……。だから私、最初はたちの悪い冗談だと思ってた。本気であんな事言うはずがないことを知っているから。次の日にも「やぁ、びっくりしたかい?」なんて笑って抱き締めてくれると思ってた。
けれど
この三日間、私達がともに過ごした五ヵ月足らずの間まるで何もなかったかのように振舞う圭ちゃん。
私は溜め息をついた。
あれから何度この溜め息をついただろう。
私は目を伏せるようにして滲む涙を拭った。
もうあの日々は帰ってこないの?
もうあの優しいぬくもりに触れる事はできないの?
もうあの心地好い風と背中を感じることは出来ないの?
いつの間にか私は泣きじゃくっていた。
当然のように教室は私のすすり泣きにざわめきが広がって、授業は強制中断。
それでもあとからあとから流れる涙を、私は止めようとはしなかった。涙が心を洗い流してくれるような気がした。
懸命になだめてくれる友達がいてくれた事がちょっとだけ、私の心を救ってくれた。
2
部活が終わっても私の目は、真っ赤に泣き腫れていた。
ちらりと圭ちゃんを見てもまるで気にする様子がない。この目が一体誰を想って泣き腫れたのかも判ってもらえないのかと思うと、また悲しくなってきた。
圭ちゃんはそんな人じゃなかったのに……。
帰り仕度を済ませて自転車置き場に帰ろうとする圭ちゃんを、私は意を決して追った。
居ても立ってもいられなかった。どうにかして圭ちゃんの口から納得のいく理由を聞き出したかった。
自転車置き場は幸い人の姿がなかった。
「圭ちゃん」
私は恐る恐る呼び止めた。
取りつく島もない答えが返ってきたらどうしよう……。そんな思考が声を震わせていた。
「梓、か」
圭ちゃんは予想していたよりも穏やかに答えた。
もしかしたら許してくれるのかも、という儚い期待はけれどすぐに砂のように崩れ落ちた。
「もう終わりにしよう、て言わなかったか?」
「だからって……」
私はつかえた胸の内をどうすれば晴らすことができるのか少し考えて、
「だからって、そんなのあり? 今までそんな事なかったじゃん? それとも何? 圭ちゃんは私のカラダだけが欲しかったの?」
思わず口走ったその瞬間の圭ちゃんの目は今まで見たこともないほどコワかった。私は最後の一言が明らかに言い過ぎであったことを理解した。
私は息を飲んだ。けれど「ごめんなさい」の一言は遂に言えなかった。
圭ちゃんは大きく息をついた。
言いたい言葉をお腹の底へ沈めているようだった。
「梓」
しばらく時間をおいて圭ちゃんが呼んだ。
「悪いけど俺、もうお前について行けないよ」
今日一日泣き続けて涙も枯れ果てたはずの目から、再び大粒の涙が滲み出てきた。
「お願いだよ……。私を一人にしないで……。私を棄てないで!」
最後の言葉は絶叫に近かった。圭ちゃんは困ったような表情をちらりと見せたけど、そのまま何も言わずにバイクを引き出して跨った。
私は答えを求めて圭ちゃんをじっと見つめてた。
圭ちゃんは黙ってヘルメットを被りエンジンをスタートさせると、とうとう一言もなく走り去ってしまった。
次の日から私は圭ちゃんの言葉の意味を考えるようになった。そこに何かの理由が隠されている気がした。
圭ちゃんの口調ではやっぱり私に原因があるみたい……。何か圭ちゃんの気に障るような事を言ったのかもしれないし、やったのかもしれない。理由もなく怒るような人じゃないから。
でも、そうだとしたら一体私、何をしたの? 突然そんなに怒るようなことなの?
夏休みの最後から私は圭ちゃんとどんな時間を過ごしたかを思い起こしたけれど、やっぱり思い当たることなんてなかった。
圭ちゃんはいつも微笑みを浮かべて、私を見つめていてくれた。
もしかして圭ちゃんは私に飽きちゃったけど特に別れる理由もないもんで、カッコつけてあんな態度取ってるだけかも……。
何日も何日も考えて、考えるほどにこのイヤな考えが頭にまとわりついて離れなくなっていく。
そしてある日、私はこの心は拒否して信じようとはしない結論を頭で理解することにした。 長谷川先輩は私を棄てたんだ。
そうとなれば私はあんな人をいつまでも想ってうじうじしててもしかたないよね。気持ちを切り替えて今度こそいい人を見つけるんだ。未だ十五歳だもん!
これからじゃん!
私はこれから前向きに生きていくんだ。
そう決意したのは2学期が始まって半月後のことだった。
私は吹奏学部に退部届を出した。
以前ほど学校は楽しいところではなくなっていたけど、級友にも恵まれたしそれなりに居心地はいい。お昼休みなんかで長谷川さんにばったり出会う事もあるけれど、学校にいて気まずい時間はそんな時くらいのもの。早くカレシを見つけて見返してやんなくちゃ。
あなたが愛してくれなくても、私のこともっともっと愛してくれる男はいるんだもんって。
ところが、それから何人かのカレシができたりしたけれど、どーゆー訳かぜんっぜん長続きしないの。ひどいのになると3日で別れたオトコもいた。こーなってくると私もちょっと落ち込んできちゃう。私って、どうしてこーオトコに運がないのかしら?
みんな口を揃えていうの。「お前と付き合ってると疲れる」って。それって私の責任?
確かにおもしろくないのは分かるよ。だって今でもやっぱり長谷川先輩のこと忘れられずに、無意識のうちに先輩と比べてしまうから。
でも先輩と比べたら、みーんなガサツで勝手なんだもん。しょーがないじゃん。
私がドジでのろまなのは分かってんだから、それなりに待ってくれるなり気遣ってくれるのがフツーじゃない? 長谷川先輩は少なくともそうだったのに。
どうしてこうなっちゃうんだろ?
これでも早く先輩のコトは忘れなくちゃって思ってるんだよ。新しいカレシに失礼だとは思うしぃ……。
でもしみついたクセはなかなか抜けないよね。
新しいカレシの中に先輩の面影を求めちゃったり、バイクの音が聞こえると無意識に振り返ったり……。
そんな時ってすんごいブルー入っちゃうよね。自分が惨めになっちゃう。いつもそんなだからきっと私キラワレちゃうのかな。
私、どうすればいいんだろ。
どうすればこのドツボにはまったこの状態から抜け出せるんだろ。誰かこの迷える子羊ちゃんを救ってプリーズ!
それから私はとうとう三カ月で11人のカレシと別れるとゆー大記録(?)を樹立してしまっていた。私ってレンアイの才能ないのかな……?
一体私のどこがどう悪いんだろ。これだったら先輩の方が全然いーじゃん。
私は溜め息をついた。
あれから四カ月……。
先輩、まだ怒ってるのかな。
私、もう十分に反省したよ。やっぱり先輩でないと私ダメみたい。
今からじゃ、もう手遅れ? やり直すことはできないの?
クリスマスも近いのにたった一人でシングルベルなんてイヤすぎるよ。
今までずぅっと考えてきたけど、付き合ったカレシからは「ウザい」とか「疲れる」とかワケわかんないものから「前の彼氏をすぐ引き合いにだす」とか「超ワガママ」とか流石に耳のイタイものまでいろんな理由を突き付けられた。
そんな理由で先輩怒っちゃったの? もしそうだったら今度こそちゃんと謝るからヨリを戻して欲しいよ。
そうだ!
やり直せるものならやり直そう!
これで駄目だったら
もしこれでも「ついて行けない」なんて言われたら……。
今度こそ私、先輩のことは金輪際忘れてしまおう! こんな事で人生の貴重な時間を無駄に過ごすコトないもんね!
私はある日の放課後、もう一度だけ先輩に逢うことにした。
私は自転車置き場で先輩が部活から帰ってくるのを待つことにした。
思えばここで全ては始まり、ここで何かがおかしくなったんだ。
先輩のバイクはいつものように、いつもの場所に停められている。
あの頃と何も変わってはいなかった。ただ一つ違う点は、今の私はこのシートに座ることが出来ないという点だけ。
初めて寂しいと思った。
あの頃はこんな事になるなんてこれっぽっちも思わなかった。幸せってそんなものなのかも知れない。
人通りのない自転車置き場で一人、私は待った。
バイクを見ていると、懐かしい記憶が瞼の裏を駆け抜ける。
車がなければ到底行けないような変なところにあるチョーかわいー喫茶店や、夏には海にもこのバイクでつれてってもらったなぁ。それから街が一望できる先輩の「秘密の展望台」とか、白樺のきれいな湖とかホントいろいろな所に行ったよね。
そんなふーに楽しかったあの頃を思い起こしていると
「四条か?」
って私を呼ぶ聞き慣れた、でももう永らく耳にすることのなかった懐かしい声が聞こえた。 私はどきりとして、はじかれたように振り返った。
そこにはやっぱり何一つ変わらないように見える長谷川先輩が立っていた。
「……先輩……」
懐かしさが胸を少し締め付けた。
私も表面的には何一つ変わっていないはずだけど、四ヶ月という時間は私たちの心に確実な変化をもたらしていた。
「久し振り、って言うのも変だけど……。元気してるか?」
「う、うん」
先輩の口調はすごく優しかった。出逢ったときのように……。そしてその分よそよそしかった。
「新しい彼氏とつきあってんだって? どうだい、うまくいってるのかい?」
私は無言で小さく首を振った。僅かに自嘲ぎみに、
「んーん、だめ。つい先週ケンカ別れしちゃった。先輩と別れてもうこれで十二連敗」
「ふーん……」
先輩は複雑な表情であごに手をやった。
やっぱりねっていう嘲笑と、流石にかわいそうという同情がないまぜになったようなそんな複雑な表情。
「やっぱり私ダメだよ。すぐ先輩と比べちゃう。でも先輩よりイイ人なんていなかった。私の一番は今でも先輩なんだよ」
私は俯いた。
「ごめんなさい……」
私は顔を上げずにそのまま謝った。
その「ごめんなさい」の意味は先輩には分からない。私にも何でここで謝んなきゃいけないのか分かってないくらいだから。
「だからお願い。あの日私たちの恋は終わったけれど、今日からまたやり直して欲しいの。新しい関係を一から作りたいの。私、先輩が好きなんです。……どうしようもなく好きなんです……。先輩の好みの女になるから……だからお願いです。先輩のそばに……そばにいさせてください」
ほとんど一気に言った私の言葉を、先輩は黙って聞いていた。
そして大きな溜め息をついた。
「おまえ、わかってねーよ」
ぼそりと呟いた一言は私の心を貫いた。
「おまえ、あれこれ考えてばっかで何一つ変わっちゃいない」
先輩は髪をかきあげた。
そんなの分かるワケないじゃん、って言いかけた私はでかかった言葉を飲み込んだ。
「じゃあ、私はどうしたらいいの? 私はどう変われば先輩に許してもらえるの?」
先輩はじっと私を見据えた。
「そいつがわかったらさっきの話、考えてもいいさ」
それがわかんないから聞いてんじゃん! もう、私トロいんだもん!
「ひとつだけ言えるとしたら『いいかげん大人になれよ』って事かな」
先輩の言葉をしばらく噛み締めた私は呟いた。
「……わかんないよ。そんなの」
私はもうサジを投げることにした。ムツカシイ話はもうたくさん!
「それがわかんなきゃ、この先きっとお前の記録は延び続けるよ」
私は何も言い返せなかった。
ちょっとムカツク言い方だけれど、十二連敗中の身としては何も言えない。
私ってコドモなのかな。それが今までフラレてきた原因なのかな。私ってやっぱダメな娘なのかな。こんなんじゃ、永久に独りぼっちなのかな。
先輩の一言に、私の頭の中はぐるぐると回り始めた。
「私は……」
無意識に言葉が出た。
「私はどうすればオトナになれるの? オトナって一体何?」
本格的に私混乱してきたみたい。だって今までそんなの考えたコトないモン。
「それを自分で考えてみなってことさ」
先輩はやっぱり何処か突き放したような口調でそう言った。
3
私は家に帰ると部屋着に着替えて机の前に座った。
大人、オトナ、おとな……
先輩と別れてからもずっとこのことを考えていた。
私はそれまでオトナとコドモの境界線ってゆーか、そんなモノがどこかにあるような気がしていた。
例えばそれは「十八禁」解禁の十八歳かも知れないし、成人式のある二十歳かも知れない。それとももっと早くてアレがあったらもう大人? えっちした日からオトナになれるとか……?
でも、アレもえっちも経験しても「オトナじゃない」ってコトは、二十歳になるまでオトナになれないってこと? それって変じゃない?
二十歳になったら私はサナギが蝶になるようにオトナになるの?
私の何が変わればオトナになるんだろう。
普段「大人」って言うときは何か落ち着いてるヒトを指すよね。と言うことは二十歳になると私にも落ち着きが出るのかな?
けど、それって二十歳って決まってるワケないよね。同じクラスの聡美ちゃんなんておない年なのにすっごく落ち着いてて、いつも冷静で「大人」な娘だもんね。
それに、私に「大人になれ」ってゆーんだから歳なんかカンケーあるわけないよね。
だったら、聡美ちゃんはどーして「オトナ」っぽく見えるのかな?
普段あんましゃべんないから? しゃべり過ぎってコドモっぽく見えるのかなぁ?
そんなとき、
「ごはんよー」
というお母さんの声が聞こえてきた。
「はーい!」
と答えて、「そだ! お母さんなら分かるかも」と瞬間思って首を振った。
先輩は「自分で考えろ」って言ったんだ。ここでお母さんに聞いたらフェアじゃないよね。 私はぺろりと舌を出して立ち上がった。
次の日も、そのまた次の日も私は「オトナ」の意味を考えた。
でも分からなかった。
「やっぱり私は頭悪いんだ。そんな事も分からないんだ」
私は休み時間の教室で机に腰掛けて、いつものように溜め息をついた。
私って溜め息ばっかりついててどーしよーもないよね。
そんな時、
「梓ちゃん」
と、私の背後から声がかかった。
振り返ると聡美ちゃんが立っていた。
「どうしたの? また大きな溜め息なんてついて。また恋の悩み?」
普段あまり自分からしゃべることのない聡美ちゃんが珍しく声を掛けてくれたのだった。
「聡美ちゃん」
どっちかって言うと鳩が豆鉄砲を喰ったような顔して、私は答えてたんだと思う。
「もしかして、お邪魔だった? だったら……」
「ううん。ううん! 全然! そんなコトないよ!」
「そう? 何か眉を曇らせてたから……」
私は恥ずかしくてちょっと俯いた。私ってどうしてこう思ったことをすぐに表情に出してしまうんだろ!
「ううん、そうじゃないよ。ただちょっと、聡美ちゃんが羨ましかっただけ……」
聡美ちゃんはきょとんとしていた。そりゃそーよね。いきなりそんなコト言われても、戸惑うよね。
「いいな。聡美ちゃんは。どうしてそんなにクールでいられるんだろ」
「クール? 私が?」
聞き返した聡美ちゃんは、少しして鈴をふるように笑った。私何かそんな可笑しいこと言ったの?
「それってツメタイ女って意味?」
なおも笑いながら聡美ちゃんは聞いた。
私は両手を振った。
「そんな! そんな意味じゃないよ! 私は、その、聡美ちゃんて落ち着いてて、知性的ですごく大人びてていいなって……」
私は真っ赤になって言い訳してたけれど、実際聡美ちゃんはキレイだもの。何て言うか、美人っていう表現がぴったりくる。
やや切れ長の目、すらりとした鼻、形の良い口、そして何より抜けるように白い肌……。
私と歳は同じはずなのに、並んで立ったらまるっきり月とすっぽんだもん。
「そんな事……。梓ちゃんだってとってもかわいいよ」
いつの間にか笑みは熄(や)んで聡美ちゃんは、少し頬を薔薇色に染めながら軽く俯いた。その仕草の艶っぽいことと言ったら!
私はちょっとばかり胸に嫉妬のもやもやと、ある種「やっぱりね」という落胆を感じた。
私は「かわいい」なんだ。「きれい」ではなくて……。
「……どうしたの? 梓ちゃん」
沈んだ顔をしていた私を怪訝に思って、聡美ちゃんが訊いた。でも、聡美ちゃんにはこんな私の気持ち分かんないよね、きっと。
「ううん」
私はかぶりを振って殊更明るく、
「ね、教えてよ。どうしたらそんなふーになれるの?」
と、聞いてみた
人に教えてもらうってのはどうしても少し抵抗あったけれど、この際仕方無いかな。ホラよくゆーじゃない。聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥……だったっけ?
「どうって……」
聡美ちゃんは困ってしまったようだ。
「私は小さい時からこんな感じの娘だったから……。どうしてこうなったのか分からないよ」
聡美ちゃんは考え込むような仕種で答えてくれた。
それから私をまじまじと見つめて、
「こんなのだから小学生の頃とか、よくかわいくないっていじめられたんだ。澄ましてるとか、お高くとまってるとかよく言われたもの。だから私は今正直に言うと、梓ちゃんがすっごく羨ましい。明るくて、かわいくて、女の子らしいそんな梓ちゃんが心底羨ましいよ」
私はびっくりして聡美ちゃんを見た。
聡美ちゃんが人を羨むなんて……しかも私みたいなダメな娘を羨んでたなんて思いもしなかったんだもん。
確かに聡美ちゃんがカレシに甘えているような場面にはでくわしたことがないし、想像もつかない。
美人の聡美ちゃんにカレシがいると聞いたこともない。
けれどそれ以外聡美ちゃんは何一つ不自由はなかった。
すべての面で少なくとも私よりは恵まれていた。成績も、運動も、美貌も、感性もすべて私なんか比べものにならない。逆に言えば、何でカレシの一人も出来ないのか不思議なくらい。
二人揃って大きな溜め息をついた。
「結局これってないものねだりなのね。自分に無いものを人が持ってると羨ましく感じちゃう。梓ちゃんは私の持ってないものをちゃんと持ってる。だからそんな事気にしなくてもいいと思うな」
聡美ちゃんは私を慰めてくれた。でも私がホントに聞きたかったのは慰めの言葉ではなくて、その大人びた振舞いはどこからきているのかってことなんだけど。
「そうね。ありがと」
お礼を言った私は少しばかりがっかりしながらも、同時にちょっとだけほっとした。
だって「これこれこうこうしたら大人っぽくなるよ」なんて教えてもらったらさすがにアンフェアじゃない? お化粧の仕方だったら別に問題ナイけど。
休み時間の終わりまで聡美ちゃんとたあいのない話をしながら、私はふとそんな事を考えていた。
その日の放課後。
私は一人下校しながらやっぱり考えていた。
オトナって何だろう?
オトナになるってどういうことだろう?
立ち止まった。
「あ~! やっぱわかんないよォ!」
オトナはオトナになるからオトナになるに決ってんじゃん!
思った。
これって変?
オトナはオトナになるからオトナになる、って考えてみたらそうじゃない? オトナはガッコ卒業して働き始めたらオトナになるって間違ってる?
じゃ、働き始めたらオトナ?
でも私だってバイトくらいしたことあるよ?
ちょっと待ってよ。
何かこのヘンに引っ掛かるものがあるよね。
そうだ、ちょっと視点を変えてみよう!
オトナって周りからオトナって見られて初めてオトナになるんじゃない? オトナになるってゆーのは自分で言うんじゃなくて人にオトナと言ってもらうことなんじゃないかな?
何かが私のなかできらりと閃いた。
答えの片鱗を微かに見たような気がした。
……でもどうやって?
再び現れた疑問が、嬉しくて有頂天になりかけた私の頭にざばーっと冷や水をかけた。
そうなの。
私はオトナとは何かを発見した訳でも、理解した訳でもないのよね。
でもキーワードは見つけた……よーな気がする。
私はオトナ社会に出ればいいんだ! オトナ達に囲まれて、オトナって何なのかを見て、そしてオトナ達に私をオトナと認めさせればいいんだ。……きっと……。
聡美ちゃんだって周りからオトナっぽく見られてるからオトナっぽいんだ、たぶん。
そうと分かれば! ……どうすればいいの?
私は情けなくなってきた。
ここへ来てまた振出し?
私を完全にオトナとして扱ってくれるような社会なんてどこにあるの?
私は気落ちしながら、またとぼとぼと歩き始めた。
そんな時だった。
私の傍らの車道を、一台のバイクが矢のように走り去った。
もう一度、私は立ち止まった。
既に遠い過去の記憶と化し始めている、あの音……。
もはや思い出の中にしか存在しない、広い背中と吹き抜けていく風……。
瞬く間に心を揺さぶる、幸せだった日々……。
私はそのまま視界の淵に消えるまで、そのバイクの後ろ姿を見送っていた。
あの頃の記憶が走馬灯のように(と言っても私、走馬灯って見たことないんだけど)フラッシュバックする。
「あった……」
私はぽつりと呟いていた。
私を完全に一人のオトナと見なす世界が今、目の前にあった。
私はとうとう見つけた。
「そうだよ」
よく先輩も言ってたっけ。
道路の上じゃ、年齢も性別も乗ってる車さえも関係ないんだって。原付きだろうが高い外車だろうが、背負った責任は皆一緒なんだって!
だったら私だって道路に出れば一人前に扱ってくれるはずよね!
「決めた! 私、免許取る!」
だれもいない路上で私は自分自身に宣言した。
十六歳の誕生日まであと一ヶ月。
お父さんもお母さんもきっと反対するね。ウチの娘が不良になったとか言ったりして。
でも私はそのとき、初めて自分の為すべきことを見つけた嬉しさに心と足は異様に軽かった。