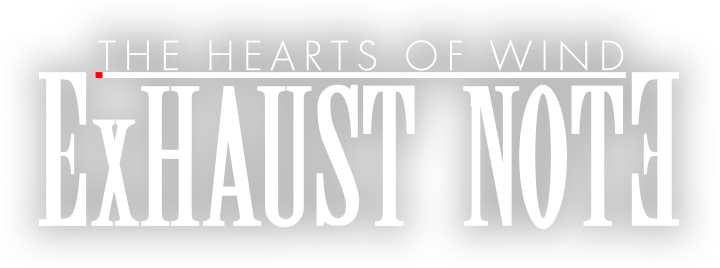novels
残響
第1章
闇は深く澄んでいた。
長い陽が落ちると、うだるような暑さがまるで嘘のように引いて、肌寒ささえ感じられる。
どこからともなく生暖かい風が、ひょうひょうと未練を唄うように吹き抜けていった。
それはそんな夏の終わりの夜の出来事だった。
都会とも、郊外ともつかぬ小さな街はすでに眠りに就いていた。
出歩く人影はまばらで、車だけが煌々とヘッドライトを灯して走り去ってゆく。
時間にすれば午前2時をまわった頃。
星も見えない街を一人の小柄な少年が歩いていた。
背の丈から察するに小学生の高学年から中学生と言ったところだろう。
少年はまるで光を忌み嫌うように路地へ路地へと足を向けた。
重く、引きずるようにゆっくりした足取りでフラフラと陰から陰へと歩くその様は、まるで意志を感じさせない夢遊病者のようでさえあった。
もしも彼を警官が見つけていたなら、間違いなく保護していただろう。
少年は一人黙然と歩き続ける。
時折、街の明かりが少年を照らしたが、光は陰を強調するにすぎなかった。
あどけなさを残すその貌は無残なまでに腫れ上がり、ブランド品と思しい服も泥にまみれていたのである。
その目は生気をまるで感じさせなかったが、そこには異様な光が垣間見える。
憎悪という名の赤黒い炎がちろちろと陰火のごとく燃えていた。
それは決して燃え上がることなく、少年をさらに深い闇へと誘う灯火となって少年をつき動かしているに相違なかった。
やがて街の灯が遠くなり、住宅街へと足を踏み入れる。
少年は一軒の家の前で足を止めた。
「八木」という表札の掛かった、豪邸とは言わないまでも庭のついた三階建ての家は、高級住宅街である周囲のどの家と比べても決して見劣りしない壮麗さを兼ね備えていた。
白亜の壁と車庫のシャッターがあらゆる不法侵入者を寄せつけぬ様に立ちふさがっていたが、総ての窓は昏く主の不在を訴えていた。
少年は気にする風でもなく門を開けると鍵をとりだして玄関のドアを開ける。
中は静寂に包まれていた。
耳を澄ませばキッチンから冷蔵庫のモーターの唸り声が聞こえてきそうだった。
少年はいつものようにダイニングへと、ふらふらとした足取りで向かった。
暗い部屋や廊下に灯をひとつひとつ点しながら、誰もいないダイニングにやっとという感じで辿り着いた。
広いダイニングは中央に四人掛けのテーブルがあり、豪奢なサイドボードなどの調度品がそろえられている。
少年はテーブルに目をやると、いつものように置かれた手紙と五千円札を取り上げた。
「昭平君へ。今日は家に帰れそうにありません。時間がないので晩ご飯作ってあげられませんでした。お金を置いておきますので好きなものを食べておいて下さい。出掛ける時や寝る前には戸締まりを確認して下さい。いつもごめんね。母より」
少年……八木昭平は手紙をくしゃくしゃと丸めると屑篭へ投げ入れた。
昭平は天井を見上げて、目を閉じた。
もう彼は我慢できなかった。
否、耐えられなかった。
少年の硝子のように繊細な精神は今彼の置かれる苛烈な環境に耐えることが出来なかった。
上を向いて堅く瞑った目から涙がこぼれ落ちた。
もう流すまいと遠い日に誓った涙であった。
少年は決意した。
もう彼にはその途しか見えなかった。
昭平はゆっくりとダイニングをあとにすると階段を上がった。
体中が軋るように痛んで昭平の表情が曇る。
3階の自室がこんなとき恨めしかった。
昭平はやっとの思いで自分の部屋のドアを開けた。
大量の模型やラジコン、ゲーム機器が主の帰りを待っていた。
ここだけが彼の居場所。
この空間だけが彼を癒してくれた。
それもこれで終わる。
昭平は玩具に目もくれずデスクの引出しを開けた。
一通の封筒が文房具などのトレーの下に隠すように置かれていた。
昭平は無言で封筒を取り上げ、中を認(したた)めると封筒をもって部屋を出た。
外へと出た昭平は施錠を終え、わが家を一瞥した。
「さよなら……。ごめんね、母さん」
一人ごちた昭平はしばらくした後、再び夜の闇へと吸い込まれるように歩き始めた。
その手に握られたロープを認める者はどこにもいなかった。
昭平の足は街と反対方向に向いていた。
人通りの絶えた深夜の街は彼の孤独に相応しかった。
やがて道は勾配が強くなってきた。
そして、アスファルトの道はそこで終わった。
昭平は気にせず壁の間に身を潜り込ませると、杣道をやはりゆっくりと登っていった。
ここは昭平が小さなときからよく一人で遊びに来た場所。
小さな裏山とも言うべき場所だった。
街の自慢のスポットの一つであり、山林や池、キャンプ場などもあるちょっとした自然公園として街の人々に親しまれている。
昔はここに玩具やお菓子を持ち込んではひとりで日が暮れるまで遊んだものだった。
山桃や枇杷の木があってよく食べていたっけ。
その奥にはひときわ大きな木があって木登りしたこともあったな。
ふとそんな記憶が昭平の脳裏をかすめた。
あの頃がどれだけ懐かしくて、どれほどよい時代であっても、もう帰ることは出来なかった。
時間とは無情で残酷なのだ。
今、昭平の足はその大きな木に向かっていた。
昔日を懐かしむためではなく、そこに人生の終焉を見るために。
十四年の歳月は彼にとってすでに充分永く、それ以上にこれからの人生を生きる気力は最早昭平にはなかった。
彼に与えられた時間はただ徒(いたずら)に永く、すでに安寧はそこにしか見いだせなかった。
ただひとつ、心残りなのは「やつら」が裁きを受ける様を見られないことだろうか。
昭平が手にする封書には「やつら」の名前が記されている。
これによって「やつら」に幾許かの社会的制裁が加えられれば、昭平はそれで満足であった。
これが昭平に出来る精いっぱいの復讐だったのだ。
その様を思い起こすとき、ようやく昭平の口元が歪むように笑みを形作るのであった。
「いまにみてろよ……」
昭平は小さな呟きは、そぞろ鳴く虫の声にかき消された。
昭平は立ち止まった。
幼少の頃から昭平だけの秘密の場所。
大きな、名もしれぬ木。
大人三人が手をつないでも囲むことは出来ぬほどに幹は太く、その高さは見上げても頂は見えなかった。
もともと二本の木だったのか、幹は根元で二つに分かれ、広がるように枝を伸ばして天蓋を覆っている。
昭平は木を見上げた。
幾度となく見上げてきたが、これが最後になるのだろう。
胸に去来する感情は別れを偲ぶ哀惜の念だったかもしれない。
不思議と恐怖はなかった。
これから死出の旅路に向かうというのに心は妙に落ち着いていた。
それは今までの苦汁の人生から解放されるという悦びの所為かも知れないと、昭平は自分を納得させた。
昭平は周りを見渡す。
人の気配はない。
木々の合間から街の光がかすかに明滅していた。
それも見納めだと、昭平は網膜に焼き付けるように見つめた。
そして昭平は封筒を胸のポケットにしまって、ゆっくりと木に登りはじめる。
枝がかなり下から張っているおかげで、幹が太くても足がかりには困らなかった。
手にしたロープで小さな輪を作ると、手ごろな枝に縛りつけた。
あとはこの輪に首を掛けて飛び降りれば総てが終わる。
もう理不尽な暴力にも、孤独感に呵まれることもなくなるのだ。
昭平は息を吸い込んだ。
「待て」
その声はそんな昭平を貫いた。
昭平は慌てて周囲を見た。
確かに人の声がした。
誰もいないはずのこの公園で、だが声は昭平を制止した。
昭平はどっと体中から汗が吹き出るのを感じた。
初めて昭平は恐怖した。
喉が渇く。生唾を嚥下するのにすら苦労したが、
「……だ、だれ?」
辛うじて絞り出た声は大きくはあったが、語尾の震えはごまかせない。
しん、と静まり返った林の中で虫の声だけが聞こえた。
「誰か居るの?」
木を降りながら昭平はもう一度闇に問いかけた。
がさり―
不意に昭平の左手の叢(くさむら)が音を立てる。
昭平は心臓が止まったかと思えるほどに肝を潰した。
叢から影が伸びる。
いや、身を起こしたというべきだろう。
身構えるようにして暗がりを凝視した昭平だったが、影は闇より暝い漆黒に塗り込められてその姿を顕さなかった。
どれくらいの時間が過ぎたか昭平には分からなかった。
無限のようであり、一瞬のようにも感じられた時間は、影の声でようやく動きはじめた。
「自殺するなら他でやってくれ」
その声は錆を含み、やや嗄れていた。
どうも老人のようだ。
こんなところにこの時間いるということはホームレスか何かだろう。
昭平は徐々に落ち着きを取り戻しはじめていた。
昭平が老人を確かめようと足を出すと、影は昭平を無視して再び横になった。
「こんなところで死なれちゃ寝つきが悪い」
昭平は老人の元に歩み寄りながら段々と腹が立っている自分に気づいた。
人が思い詰めて死を選ぼうとしているのに、向こうへ行って死ねとはどういう了見か。
せめて引き留めるくらいのことはしないのか?
老人は草陰に薄い毛布一枚を体に巻き付けて横になっていた。
昭平は、ああやっぱり、という憐憫にも侮蔑にも似た視線を投げ掛けた。
「ぼくの思い出の場所で人生を終えて何が悪い? 第一、ここはおっちゃんの土地じゃない。」
老人は邪魔臭そうに薄目を開けた。
「それを言うなら小僧の土地でもなかろうが」
昭平は言い返せなかった。
「おまえがここを思い出の場所にするのは勝手だが、こんなところで首なんか括られたら臭くてかなわん」
そういえば昭平も首を括ったら糞尿が垂れ流しになると聞いたことはある。
「それだけ?」
昭平は怒りに震える声で訊いた。
「……他に何かあるのか?」
老人は再び目を閉じた。安眠をこれ以上妨害するなという冷厳な拒絶であった。
「……人がこれから死のうって言うのに?」
自分の命がそれほど軽んじて見られているのが、昭平には我慢できなかった。
老人はいい加減面倒くさそうに寝返りをうつと、
「おまえは阿呆か。自分の人生くらい自分で責任持て」
昭平と反対の方向へ向いた老人はぶっきらぼうに言った。
阿呆とまで言われて昭平は頭に血が上るのを感じた。
「だったらここでぼくが死ぬのもぼくの責任で自由って訳だ」
昭平は強がってみせた。
老人はやれやれといったふうに息をつくとのそりと起き上がった。
立ち上がった老人は意外にがっしりとした体格をしていた。
百八十センチ近くはあるだろう。
枝の合間から差し込む月明かりが老人の貌(かお)を照らし出した。
真っ白な髭を蓄えた深いしわが印象的だった。
長い白髪は後ろできつくまとめられた、ホームレスというにはこざっぱりした身なりの七十歳くらいの老人であった。
白く太い眉の奥にぎらりとした光を認めて昭平はたじろいだ。
老人は近くに置いてあった自分の荷物をまとめると最早昭平には一瞥もくれずに踵を返した。
「ちょ……、どこ行くのさ?」
昭平は慌てて訊いた。
「儂ぁあちらで寝る。そこで死にたきゃ好きにするんだな」
老人は吐き捨てるように言うと、振り向くこともなく更なる闇へと消えていった。
昭平は思いだした。
そちらはちょっとした崖になっているのだ。
「あ、ちょっと待ってよ!」
昭平は駆け出していた。
後で思えばなぜ駆け出したのか分からない。
「自分の人生に責任を持て」と言ったのは老人なのだ。
ならば自分の過失で崖を転がり落ちようが昭平の責任ではない。
否、それ以前に老人の態度は昭平にとって明らかに不愉快なものではなかったか。
老人のことなど、昭平にとってもどうでもよい亊だったはずなのだ。
しかし、昭平は駆け出した。
この森は知悉している。
かすかに踏みしだく草の音を頼りに暗い森を走り抜け、程なく老人に追いついた。
「……何かまだ用か?」
老人は訊いた。
穏やかな声であった。
「そっちは……」
言いかけて昭平は口を噤んだ。
老人が腰を下ろしたからだ。
「……そっちは?」
老人の問いに昭平は無性に腹が立った。
「もういいよ! そっちは崖になってるから注意してあげようと思っただけだから!」
老人はやはり毛布にくるまりながら横になると、ちらりとだけ昭平を見た。
「……そいつはすまんな」
たったそれだけの言葉だったが、昭平は胸のしこりがほぐれていくのを感じていた。
つくづく不思議な老人だった。