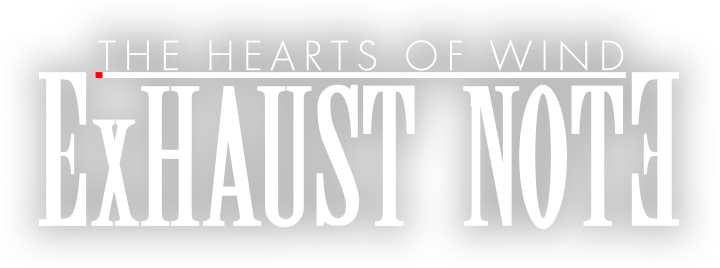novels
残響
第2章
知らず知らずのうちに昭平は老人の傍らに座り込んでいた。
森の夜はしっとりと更け、虫の声が二人を包み込むように音楽を奏でるのだった。
老人は毛布にくるまって昭平に背を向けるようにして横になっていた。
長い沈黙の後、虫の声に重ねるように昭平が口を開いた。
「ぼくのうちは父さんが早くに事故で亡くなって、ずっと母さんが一人で家を支えてくれたんだ。父さんが死んだのはぼくがまだずっと小さい頃だったけど、その時のことをぼくは、はっきり憶えているよ。」
昭平の声は、誰に向けられてのものかはっきりしないまま、森の露と消えた。
はっきり言えることは、老人に向けての言葉ではなかったということだ。
ただ、この心情を吐露したかったのかもしれないと、昭平はぼんやり思った。
「母さんは気丈な人だった。それまでの生活を守るために、それからの生活のために、母さんは涙一つ見せずに仕事に打ち込んでいったよ。そして、今も」
昭平は天を仰いだ。
「父さんの保険もおりたし、家や土地を売っちゃえばそんな苦労なんてしなくてもいいのにね」
寂しげな笑みが昭平の頬を引きつらせたが、老人は振り向いてはくれなかった。
「ぼくは寂しかったんだよ。生活には不自由しなかったけど、その代償はぼくには大き過ぎたんだよ。でも、ぼくは母さんがもっと寂しい思いをしてるのを知っていたからずっと何も言えなかった……。ぼくは、母さんは気丈なんじゃなくてそう振る舞ってるだけなのを、もうずっと前から気づいていたから」
老人はやはり無言であった。
聞いているのか、いないのか。それより起きているのか寝ているのかさえ分からなかった。
だからこそ昭平はその続きを話すことが出来たのかもしれない。
「中学に上がるとお昼はそれまでの給食から弁当に変わったけど、仕事が忙しくて週の半分くらいは帰ってくることさえ出来ない母さんに、弁当を作ってほしいなんて言えなかった……。いつだってお昼は食堂やパンで済ませてた。でも、それが嫌だったんじゃないんだ。本当に嫌なのはその様子をずっと見ていたあいつらさ……」
そういって昭平は視線をふいっと横へ投げた。
眉根をひそめて……。
「あいつらはぼくの事をずっと調べてたみたい。家に父さんの遺産があることも、ね」
言葉尻がかすかに震えるのは、怒りの所為に相違なかった。
幾許かの時間が無言のうちに流れる。
「あいつらは五人がかりでぼくをボコボコにした揚げ句に、ゲーセンやカラオケにぼくを連れ回して支払だけ押し付けた。そのうち連れ回すのも面倒になったのか、「上納金」とか言って金を巻き上げるようになったんだ。最初のうちはぼくの小遣いで賄えたけど……すぐ足りなくなって貯金を崩すようになって……それでも足りなくて、とうとう父さんの……」
声は徐々に潤んでいった。
「相談したくても母さんは仕事でいないし、話を聞いてくれる友達もいない。先生だけが頼りだったのに……。口では偉そうなことを言っても結局何もしてくれなかった……。だれも……、誰もぼくを助けてはくれなかったんだ!」
昭平は封筒をとりだした。
「これには今までぼくが受けた、いわれのない仕打ちとぼくを追いつめた人間の名前が書いてある。……ぼくはここで死ぬけど、これでやつらも社会的制裁を受けるだろう……。天が裁かないなら、ぼくが命を使って裁く……。……これは復讐なんだ」
それからどれほどの時が刻まれただろうか。
昭平はやがて立ち上がった。
「もう、逝くよ。そろそろ夜が明けちゃうから」
ロープと封筒を確認した昭平は踵を返した。
「誰かに話したかった……。聞いてくれてなくても嬉しかったよ、ありがと」
昭平が歩きはじめる、と
がさり
昭平の背後の草が動いた。
昭平が振り返ると、巌のような影が大きな伸びをしていた。
「あ……」
何かを言いかけ、昭平はしかし不意に言葉を失った。
老人は気にするふうでもなく、手早く荷物をまとめると昭平の脇を通りすぎていった。
まるで昭平の存在を意に介さないように。
昭平は唇を噛んだ。
何ひとつ……何ひとつ変えることは出来なかったのだ。
だが、
「ついてこい。俺の相棒を紹介してやる」
老人の嗄れた声が届くとき、昭平はなぜか報われたような気がした。
彼の言う『相棒』とやらがきっと自分を助けてくれそうな、そんな気がしたのだ。
公園の森をしばらく歩くと木々はまばらとなって、やがてサイクリングコースにでた。
天蓋は徐々に東の空から白みはじめていた。
新聞配達らしいバイクの排気音が聞こえてくる。
ゆっくりと街は目覚めようとしていた。
公園の出口にさしかかろうというとき、不意に
「こいつだ」
老人が顎をしゃくった。
昭平は訳もわからず周囲を見渡す。
無論人影はない。
あるのは放置された自転車やスクーター、オートバイばかりであった。
その中で一台、昭平の目に留ったものがあった。
それは昭平の知る「オートバイ」とは明らかに違っていた。
否、『違う』という『オーラ』のようなものを発散していた、と言ったほうが分かりやすいかもしれない。
まず、形が昭平の知るオートバイとは違った。
どう見ても自転車にエンジンが載っているようにしか見えない。
武骨な鉄パイプで作られた車体は呆れたことにリアサスペンションというものが見当たらず、前輪も鉄パイプとむき出しの撥条(ばね)が組み合わされたひどく簡素なサスペンションで支えられている。
エンジンには自転車のようなペダルがついており、ご丁寧にシートは自転車のサドルのちょっとばかり大きなものがついているに過ぎない。
隣に置いてある250ccのオートバイの方が大きく見えるほどに車体は小さく、だがその存在感は他を圧倒した。
ブルーの車体色は所々剥げているが、手入れの行き届いた車体に錆はほとんど見当たらない。
色のくすみ具合から相当昔のオートバイと推察できたが、一体どれほど昔のものか想像できなかった。
少なくとも昭平の生きてきた十四年を遥かに超えることは確かなことだった。
もし旧車に興味のあるものならば、必ずや足を止めその姿に見入ってしまうだろうが、残念ながらと言うべきか昭平にとっては価値を見出すことはなかったものだった。
「もしかして?」
昭平は幾分失望を隠しきれない様子で訊いた。
老人は頷いた。
「1948年型ハーリィ・ディヴィッドスンFL……ハーレー・ダビッドソンと言ったほうが分かりやすいか?」
老人はゆっくり愛車へと歩み寄ると、ハンドルに手をかけた。
「こいつはマニアの間で『ヨンパチ』と呼ばれるレア物でな(註)。儂のかけがえのない相棒さ」
「……ふーん」
昭平はぞんざいに頷いた。
彼の興味は彼の境遇を救ってくれるものであって、今老人が目を輝かせて見つめる鉄の塊ではないのだ。
老人は昭平をじっと見つめた。
その視線に昭平は何故か居心地の悪さを覚える。
「ときに少年、旅をしたことはあるかな?」
昭平はその時気づいた。
老人は昭平をただ見つめていたのではないことを。
昭平はさらに狼狽した。
眼前の老人に今まで生きてきた時間を総て見透かされた様な気になったのだ。
「え……?、あ、しゅ、修学旅行なら……」
「儂は『旅をしたことがあるか?』と訊いたんじゃ。『旅行』じゃぁない」
そう言ってから老人は破顔した。
「まぁ、今時のことだ。その歳で旅をしろというほうが無理かも知れんがな」
この男も笑うのかと昭平は少し意外な気がしたが、その目が笑っていないことはある意味予想通りと言えた。
この老人は昭平を憐れんでいるのではないのだ。
「なら質問を変えよう。お前は今の自分が世界一不幸だと思うか?」
「そ……それは……」
昭平は言葉に詰まった。
確かに今自分は不幸だが、世界一かと問われれば正直分からない。
「答えられまい?」
老人は責めるでも見下すでもない、むしろ確かめるような口調で言うと徐に愛馬に寄り添うように立った。
タンク上部についた燃料コックを開け、車体左サイドのキャブレターに付いているアイドルスクリューを気持ち開けてから、ティクラーを押し下げる。
ぽたぽたとガソリンが溢れるのを確認した老人は、チョークノブを2ノッチ引き上げて自転車のペダルのようなキックペダルを引きだすと、右足を掛けて軽く踏み込む。
空気の塊がボフッという音を伴ってマフラーエンドから吐き出された。
昭平は訳もわからずその様子を眺めていた。
この一連の作業は何なのか、その意味すら分からない。
そもそも、たかが単車を走らせるのにこれほどいろいろ作業が必要なのか、理解に苦しむ。
なのに
昭平はその時素直に作業に見入っていた。
何より物珍しかったのもあるが、熟練した者でなくては始動すら許さぬ機械と、それを操る老人の職人じみた姿に、何か得も言われぬ感情を呼び起こされたのだ。
老人は懐から初めてキィを取りだした。
キィはその年月を物語るようにやせ細り、メッキは剥げていた。
老人は微かに昭平に微笑むと、タンク上のメーターダッシュのフタを開けてキィを差し込む。
かきん。
小さな音を立ててキィが回った。
現代のバイクのようにそれで劇的にメーターにライトが灯ったり、チィチィとモーターが唸るわけでもない。
老人は殊更アクセル開度を気にしながら、右足を掛けたキックペダルの上に飛び乗るように勢いを付けてキックアームを踏み抜いた。
ぐるり、という音が昭平に聞こえたわけではない。
しかし、正しく『ぐるり』とキックアームは廻った。
昭平は次の瞬間しりもちを付いた。
さえずる小鳥がパッと飛び立つ。
キックペダルが降りた瞬間轟いたエグゾーストノートは、「炸裂」という形容こそが相応しい大音声だったのだ。
張り詰めた巨大な和太鼓の連打を至近距離で聞いているかのようだと昭平は耳を押さえながら思った。
だが、耳を押さえても音は昭平を捉えて離さない。
アスファルトの地面が拍動にあわせて揺れ、周囲の空気は容赦なく衝撃波を撒き散らす。
周りに置いてある自転車はかちゃかちゃと情けない音を立て、ハーレーの真横にいるはずの昭平の腹へ立て続けに軽いボディーブローが放たれた。
今までにも煩いバイクは数多いたが、これは別格だった。
エンジンが掛かると老人はチョークノブを1ノッチ戻してしばらく暖機し、頃合いを見計らってチョークとアイドルスクリューを元の正位置へと戻した。
するとハーレー独特のドドン、ドロドンという不規則な鼓動を打ち始める。
昭平は耳を押さえていた手を放す。
不思議なことに音量は手があってもなくても殆ど変わらない。
耳につく甲高い成分の全くない重低音は、直接魂を揺さぶっているかのようだった。
昭平は今までモノを擬人化したりするようなことはなかったが、空気を震わせながらアイドリングをゆったりと続けるその鉄塊が生きているような気がしてならなかった。
「儂はこいつと一緒に旅を続けている」
老人の声が昭平を現実に連れ戻した。
「儂はこいつと日本中はもとよりアメリカ、ヨーロッパ、オーストラリアも走った。いろんな所でいろんな人に出会った。嬉しいこと楽しいことはもちろん、気に入らないこともあったし酷い目に遭って涙にくれたこともある。だがそれさえも今となっては懐かしい、それ以上に輝かしい人生の財産じゃないかと思うとる」
老人はそう言うとくしゃくしゃの巻きタバコに火を付けた。
ぽかりと紫煙が宙を舞う。
「人間は……この世界はお前さんが思っているほど小さくはない。ただお前さんは知らないだけだ」
昭平の目が老人の視線と交差した。
その瞳が見つめてきたものは、刻み込まれた皺よりも深く数多いに違いなかった。
老人は鉄の愛馬に跨がると、ハンドルに無造作に架けられていたハーフキャップのヘルメットをゆっくりと被った。
それが老人の別離の合図。
「ま……待って!」
昭平の声は混乱と、そして未練を孕んでいた。
老人は口元に微かな笑みを刻む。
「その先を見ることができるかどうかは、お前次第だ」
そう言った老人はエンジンに一つ鞭打って、遂に昭平に名前すら告げずに走り去った。
朝焼けの街外れにいつまでもその咆哮は木霊した。
昭平は立ち尽くしていた。
「旅……か」
老人の言葉を反芻するように独語する。
無論それが現実逃避を意味するものでないことは、はっきりしている。
老人の真意は、旅に出てやつらの前から姿を消すことではなかった。
老人は見抜いていた。
昭平の中にある、子供の殻に閉じ籠もる事に安寧を求めていた「甘え」を。
彼にはまだまだ出来ることが在る筈なのだ。考えることを放棄してはならないのだ。
老人にとって昭平は既に子供ではなかった。
父を早くに亡くした昭平はいつまでも子供でいることが許されないのだ。
昭平は老人が消えた、靄の残る車道をずっと見つめていた。
「父さん……」
少年はぽつりと呟く。
胸に熱いものを宿して少年は歩き出す。
旅に出よう。
そう、いつかきっと。
今はまだ遠くまで行けないかも知れないけれど、数年もすればどこまでも行けるようになる。
あの、生ける鉄馬ならばどこまでも行けるとも。
そう、いつかきっと。
時間はゆっくりと、だが確実に流れるものだから。
そして少年の旅は始まる。
完